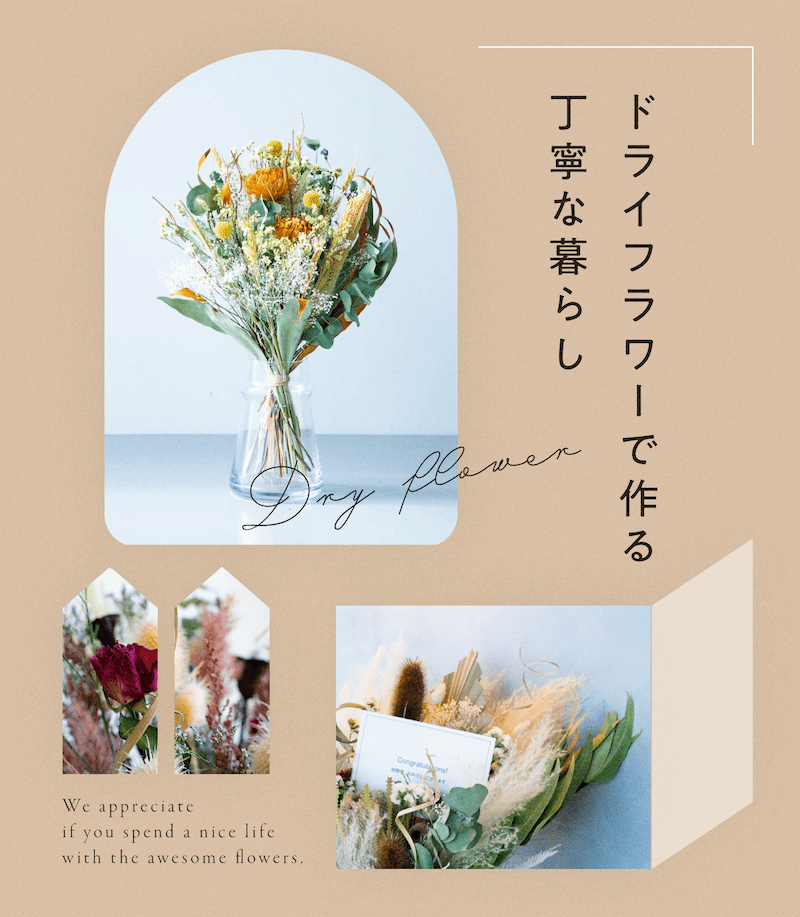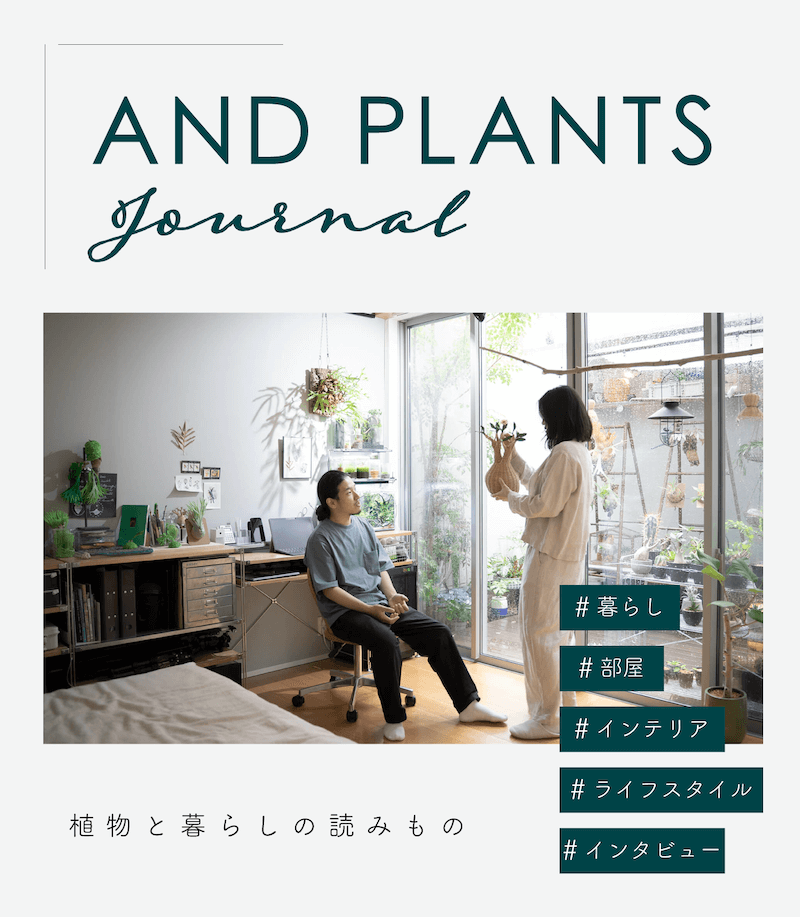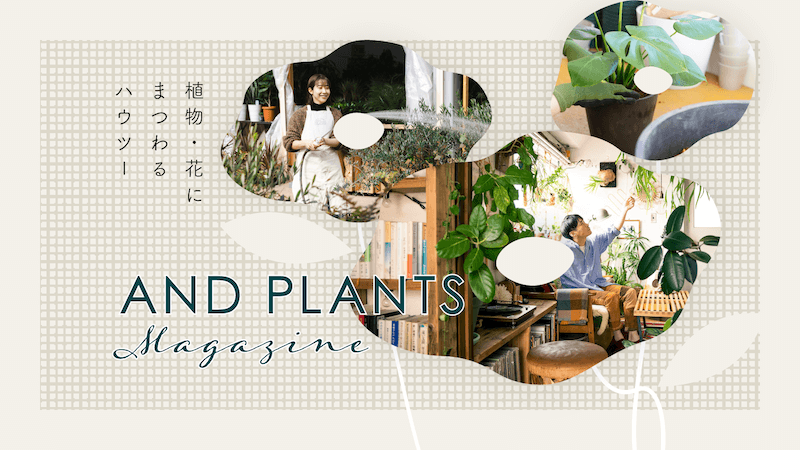「庭の木が伸びてきたけど、いつ切ればいいんだろう…」「下手に剪定して、大切な木を枯らしてしまったらどうしよう…」そんな不安を感じて、剪定ばさみを握る手が止まっていませんか?
剪定のタイミングを一度間違えるだけで、翌年花が咲かなくなったり、樹形が乱れてしまったりと、後悔につながることも少なくありません。
この記事では、そんな不安を解消するため、単なる時期の一覧だけでなく、なぜその時期に切るべきなのかという「理由」から徹底解説します。
最後まで読めば、もう剪定時期に迷うことなく、自信を持って大切な庭木の手入れができるようになるでしょう。
庭木の剪定時期|年2回「夏」と「冬」に行う
庭木の剪定は、やみくもに行うのではなく、木の成長サイクルに合わせた「冬季剪定」と「夏季剪定」の年2回行うのが基本です。それぞれの時期で剪定の目的が異なり、正しく行うことで庭木を健やかに育てられます。
ここでは、それぞれの剪定の役割と、絶対に避けるべきNG時期について見ていきましょう。
- 休眠期に行う「冬季剪定(基本剪定)」の役割
- 成長期の行う「夏季剪定(軽剪定)」の役割
- 重要|剪定してはいけないNG時期
休眠期に行う「冬季剪定(基本剪定)」の役割
冬季剪定は、木の成長が止まる休眠期(12月~2月頃)に行う、剪定の基本となる作業です。
この時期は葉が落ちているため、枝の混み具合や木の骨格が一目瞭然になります。不要な枝を大胆に切り落とし、理想の樹形に整える絶好の機会と言えるでしょう。
木への負担が少ない時期なので、太い枝を切る「強剪定」も可能です。春からの新しい芽吹きに備え、木の骨格をしっかりと作り上げてあげましょう。
成長期の行う「夏季剪定(軽剪定)」の役割
夏季剪定は、木の成長が活発な時期(7月~9月頃)に行う、いわば「身だしなみを整える」ための軽めの剪定です。
この時期に強く剪定しすぎると木が弱ってしまうため、伸びすぎた枝や混み合った枝を軽く間引く程度に留めます。
主な目的は、日当たりや風通しを改善し、病害虫の発生を予防することです。木の内側まで光が届くようになると、樹勢もよくなります。あくまで補助的な剪定と捉え、深追いは禁物です。
重要|剪定してはいけないNG時期
庭木には、剪定を避けるべき「NG時期」が存在します。特に注意したいのが、猛暑が続く真夏(7月下旬~8月)と、寒さが厳しい真冬(1月~2月上旬)です。
これらの時期に剪定を行うと、切り口から木が弱るだけでなく、最悪の場合枯れてしまう危険性があります。
また、桜や梅といった花木は、花芽が作られる時期に剪定すると翌年花が咲かなくなってしまいます。大切な木を長く楽しむためにも、剪定に適した時期を守ることが何よりも大切です。
庭木タイプ別|剪定時期カレンダー早見表
ご自宅の庭木はいつ剪定すれば良いのか、まずはこちらのカレンダーで確認してみましょう。庭木は大きく「落葉樹」と「常緑樹」に分けられ、それぞれに最適な手入れの時期があります。
この早見表を見れば、あなたの庭木に合った剪定時期が一目でわかります。おおよその時期を把握したら、それぞれの樹木タイプの詳しい解説へ進み、より深く剪定のコツを学んでいきましょう。

樹種別|主要な庭木の剪定時期

庭木と一口に言っても、その種類はさまざまです。最適な剪定時期は、葉を落とす「落葉樹」か、一年中葉をつける「常緑樹」か、さらにその中でも葉の形で大きく分けられます。
ご自宅の庭木がどのタイプに当てはまるかを確認し、木に合ったベストなタイミングでお手入れをしてあげましょう。
- 落葉広葉樹(モミジ、アジサイなど)の剪定時期|12月〜2月
- 常緑広葉樹(キンモクセイ、オリーブなど)の剪定時期|3月下旬~6月
- 常緑針葉樹(松、コニファーなど)の剪定時期|3月~4月
落葉広葉樹(モミジ、アジサイなど)の剪定時期|12月〜2月
モミジやアジサイなどの落葉広葉樹は、葉が完全に落ちて活動を休止する、冬の12月~2月が剪定の最適期です。
休眠期は木の成長が止まっているため、剪定によるダメージを最小限に抑えられます。何より、葉がないことで木の骨格がはっきりと見え、理想の形をじっくり考えながら作業できるのが大きなメリットでしょう。
どこにハサミを入れれば春以降に美しい樹形になるか、イメージしながら不要な枝を整理してあげてください。
常緑広葉樹(キンモクセイ、オリーブなど)の剪定時期|3月下旬~6月
キンモクセイやオリーブに代表される常緑広葉樹は、寒さにやや弱い性質を持つため、厳しい冬を避けた3月下旬から6月頃に剪定するのが基本です。
この時期は、木がこれから成長しようとエネルギーに満ち溢れています。そのため、新芽が動き出す力強さを利用して、剪定後の回復を早めることができるのです。
真夏になると木が弱りやすくなるので、梅雨入り前までには作業を終えるのが理想的。木への優しさを第一に考えた剪定時期と言えるでしょう。
常緑針葉樹(松、コニファーなど)の剪定時期|3月~4月
松やコニファーといった常緑針葉樹の基本剪定は、新しい芽が本格的に動き出す直前の3月~4月に行いましょう。
この時期に剪定する目的は、春から夏にかけて伸びる新芽の量を調整し、樹形が大きく乱れるのを防ぐことです。本格的な新芽が伸びる前に基本の形を整えておくことで、一年を通して美しい姿を保ちやすくなります。
特に松は「みどり摘み」など独特の手入れが必要ですが、まずはこの時期に不要な枝を整理することが、美しい松作りの第一歩です。
初心者にもできる庭木剪定の基本

いざハサミを持っても、どこをどう切ればいいか迷いますよね。しかし、剪定には基本となる切り方があり、まずは2つの方法を覚えるだけで、見違えるほど樹形が整います。
ここでは、初心者の方が最初にマスターすべき「透かし剪定」と「切り戻し剪定」のコツをご紹介します。
- 基本の切り方①|不要な枝を取り除く「透かし剪定」
- 基本の切り方②|木の大きさを整える「切り戻し剪定」
基本の切り方①|不要な枝を取り除く「透かし剪定」
「透かし剪定」は、その名の通り、混み合った枝を間引いて、木の内側まで光や風が通り抜けるようにする剪定方法です。
日当たりや風通しが良くなると、病害虫の発生を抑え、木が健康に育ちます。まずは、他の枝と交差している枝や、内側に向かって伸びている枝など、不要な枝を根元から切り落としてみましょう。
見た目がすっきりするだけでなく、木そのものの健康につながる、最も基本的で重要な作業です。
基本の切り方②|木の大きさを整える「切り戻し剪定」
「切り戻し剪定」は、伸びすぎた枝を途中で切り、木の大きさをコンパクトに整えるための技術です。
ただ短くするのではなく、枝の途中にある芽(外芽)の少し上で切るのがポイント。外側に向いている芽を残すことで、次の枝が外に伸び、美しい樹形を保てます。
木の大きさをコントロールし、理想の形に誘導していくのがこの剪定の役割です。大きくなりすぎたな、と感じる枝があれば、この方法を試してみてください。
庭木剪定に必要な道具

庭木の剪定は、適切な道具を揃えることで、作業効率が格段に上がり、安全性も高まります。闇雲に高価なものを揃える必要はありません。まずは基本となる道具から準備しましょう。
ここでは「切断道具」「安全装備」「後片付け道具」の3つのカテゴリに分けて、揃えておきたいアイテムをご紹介します。
- 基本の切断道具
- 安全を守るための必須装備|脚立・手袋・保護メガネ
- 作業が楽になる後片付けの道具
基本の切断道具
剪定で最も基本となるのが、枝を切るための道具です。主に「剪定ばさみ」と「剪定のこぎり」の2つがあれば、ほとんどの作業に対応できます。
剪定ばさみは、指くらいの太さまでの枝を切るのに使います。自分の手の大きさに合った、握りやすいものを選びましょう。それ以上の太い枝は、剪定のこぎりの出番です。
無理にハサミで切ろうとすると、手や木を傷める原因になります。道具を正しく使い分けることが、美しい仕上がりへの第一歩です。
安全を守るための必須装備|脚立・手袋・保護メガネ
剪定作業では、思わぬ怪我を防ぐための安全装備が欠かせません。特に重要なのが「脚立」「手袋」「保護メガネ」の3点です。
脚立は、不安定な場所に立って作業することの危険性を減らしてくれます。必ず安定した三脚タイプを選びましょう。
また、剪定ばさみでのマメ防止や、枝による切り傷を防ぐために手袋は必須です。切った枝が目に跳ね返る危険もあるため、保護メガネも忘れずに装着し、安全第一で作業に臨んでください。
作業が楽になる後片付けの道具
剪定作業で意外と大変なのが、切った枝や葉の後片付けです。作業をスムーズに終えるためにも、後片付け用の道具を準備しておくと良いでしょう。
あらかじめ木の根元にブルーシートを敷いておけば、切った枝葉が散らばらず、一気にまとめられるので非常に効率的です。
熊手やほうき、ちりとりも用意しておくと、地面に落ちた葉をきれいに集められます。剪定から後片付けまでを一つの流れとして捉え、準備を万全にしておきましょう。
庭木の剪定を失敗した際の対処法

丁寧に作業していても「切りすぎてしまった」「時期を間違えたかも」と不安になることはあるでしょう。しかし、過度に心配する必要はありません。植物には自ら回復しようとする力が備わっています。
万が一失敗してしまった場合、最も大切なのは慌てずに、まずは木の様子を見守ることです。
切り口には癒合剤を塗って雑菌の侵入を防ぎ、回復を助けてあげましょう。明らかに枯れてしまった枝は取り除きますが、すぐにまた剪定するのは避けてください。樹勢が弱っている時にさらに枝を切ると、回復の妨げになります。
どうしていいか分からないほど弱ってしまった場合は、専門の業者に相談するのも一つの手です。
庭木の剪定時期に関するよくある質問

ここでは、庭木の剪定時期について、初心者の方が抱きやすい疑問にお答えしていきます。
剪定の基本は「木の成長サイクルに合わせること」ですが、例外や特殊なケースもあります。よくある質問への回答を参考に、より深く剪定への理解を深めていきましょう。
- 剪定時期を気にせずに、剪定をしても大丈夫?
- 松も年2回くらいの剪定を行うのがいいの?
剪定時期を気にせずに、剪定をしても大丈夫?
結論から言うと、剪定時期を無視するのはおすすめできません。なぜなら、不適切な時期の剪定は、木に大きなダメージを与えてしまうからです。
例えば、真夏に強い剪定を行うと、木が弱り、最悪の場合枯れてしまいます。また、花木の剪定時期を間違えれば、翌年花が咲かなくなることもあります。
枯れてしまった枝や、通行の邪魔になる枝を少し切る程度なら問題ありませんが、木の形を整えるような本格的な剪定は、必ず適した時期に行うようにしましょう。
松も年2回くらいの剪定を行うのがいいの?
松は、他の多くの庭木とは異なり、特殊な手入れが必要な樹木です。そのため、単純に「夏と冬の年2回」という考え方は当てはまりません。
松の美しい姿を保つためには、年に2回の重要な作業があります。
春(4月~5月)に行う新芽を摘む「みどり摘み」と、秋から冬(11月~2月)にかけて古い葉をむしり取る「もみあげ」です。
これらの繊細な作業が、松独特の優美な枝ぶりを作り上げます。基本の剪定とは少し違う、松ならではのお手入れが必要だと覚えておきましょう。
まとめ
今回は、庭木の剪定時期について、基本の考え方から樹種別の最適なタイミング、具体的な剪定方法までを解説しました。
最も大切なことは、剪定が木の成長サイクルに寄り添う「対話」であると理解することです。なぜ冬に切り、夏に整えるのか。その理由がわかれば、大きな失敗は格段に減るでしょう。
忌み枝を見つけ、透かし剪定で風と光の通り道を作ってあげる、その一つ一つの作業が、庭木を健やかに育てます。