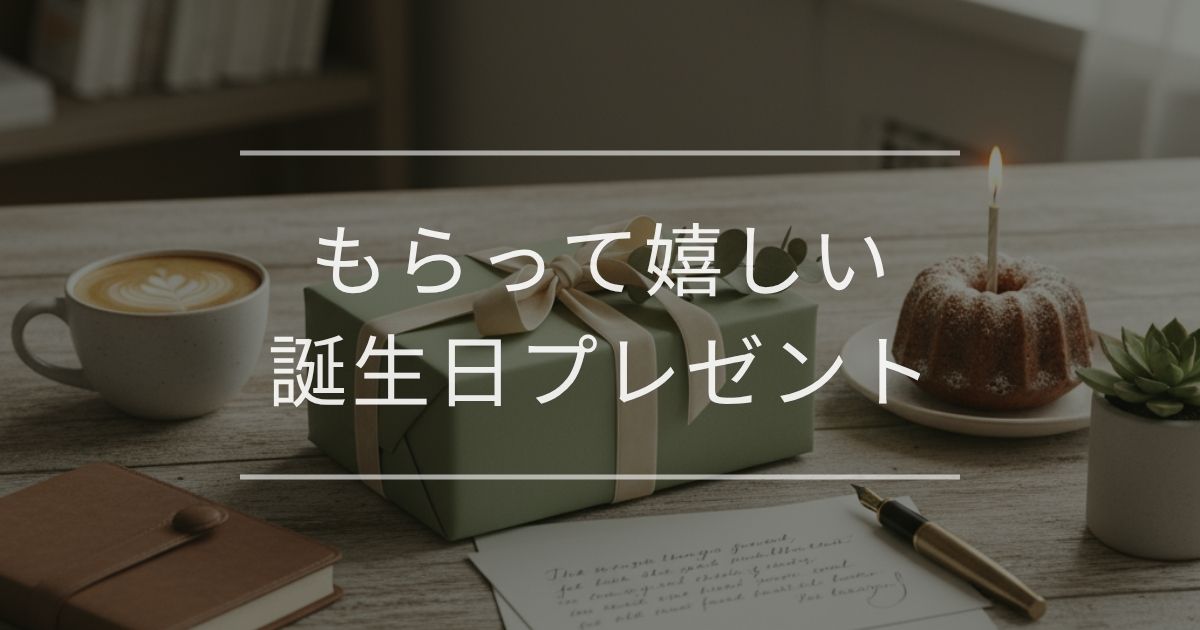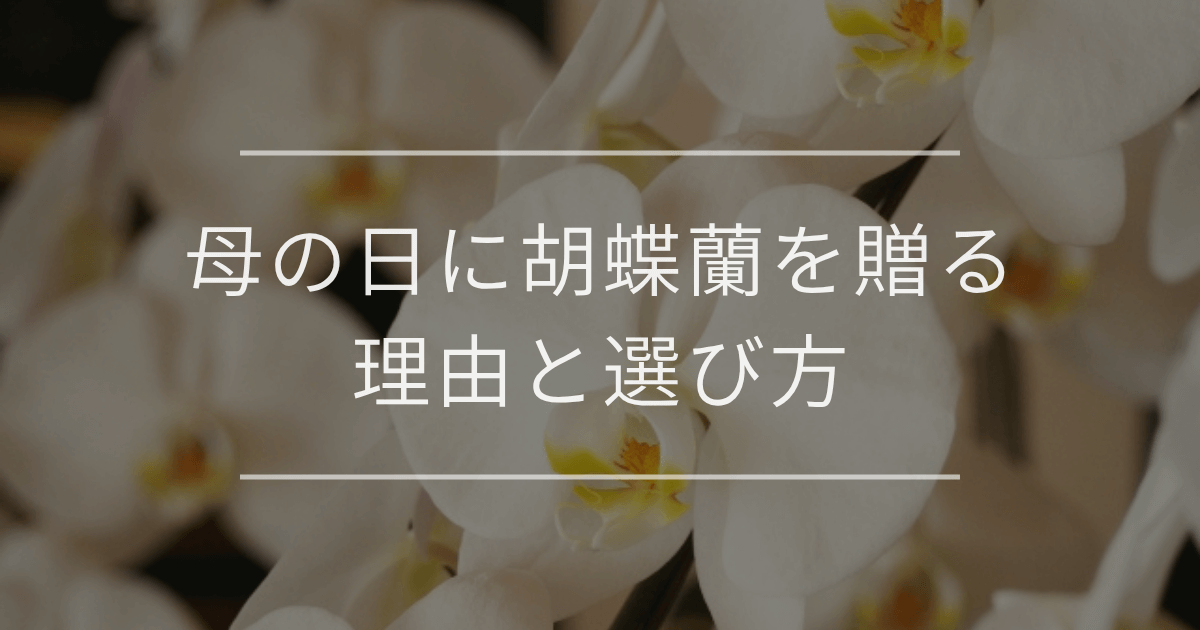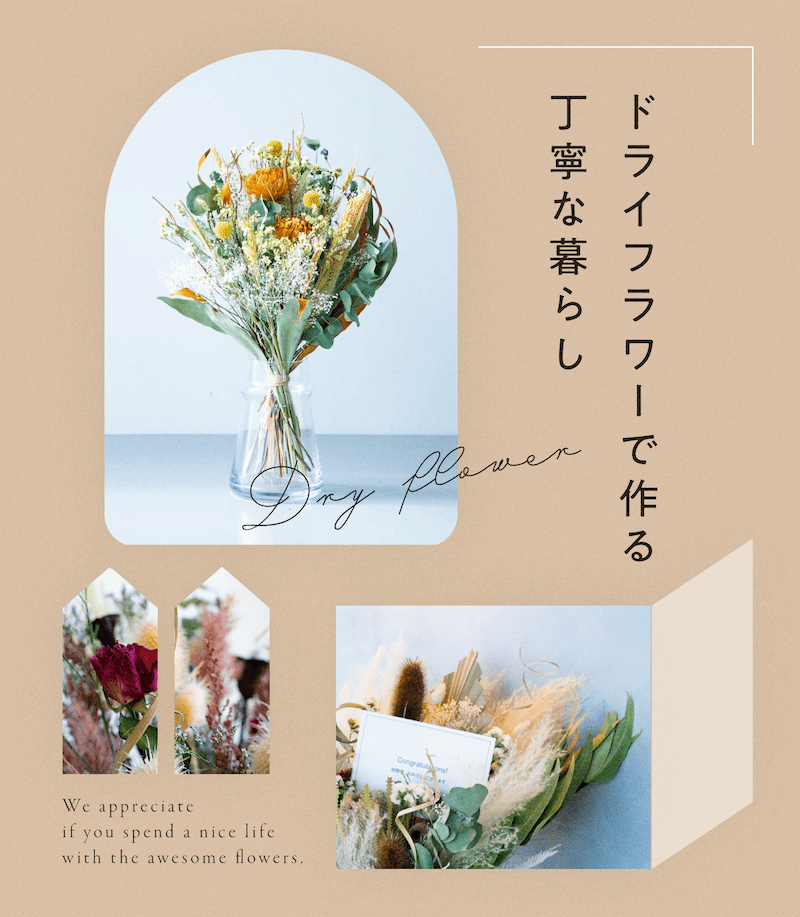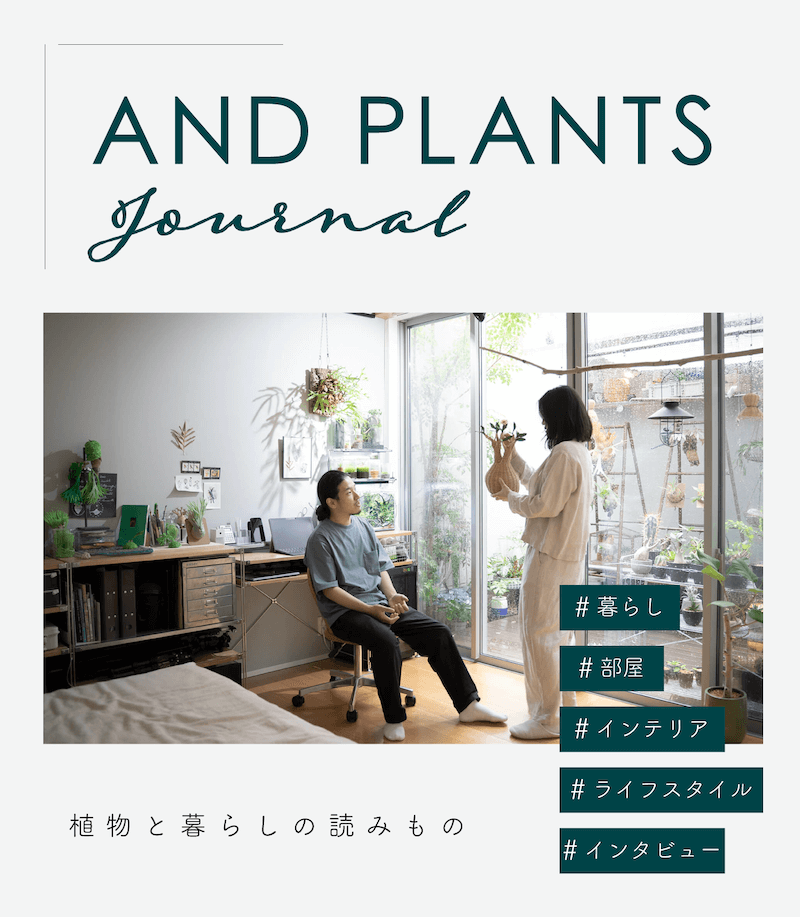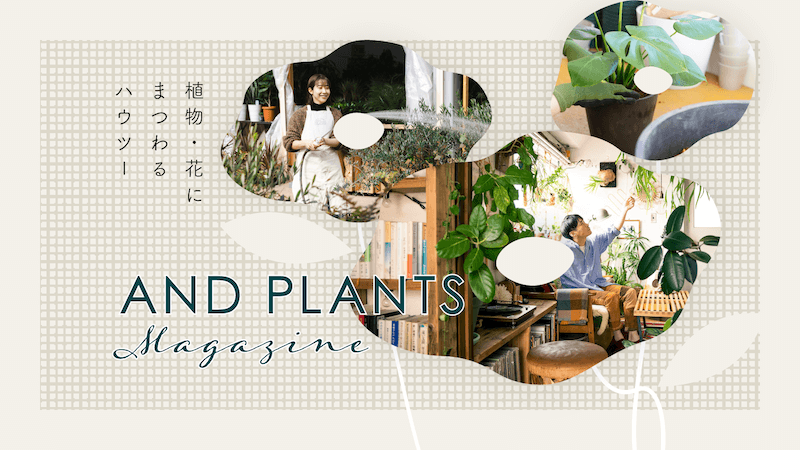大きく育ちすぎて、ひょろひょろと徒長してしまったモンステラ。樹形を整えるために剪定)したいけれど、切った茎をそのまま捨てるのは忍びない…。そう感じていませんか?
その茎、実は新しい命を生み出す「宝物」です。「茎伏せ」は、その茎の「節(ふし)」に眠る生命力を引き出し、新しい株を育てるテクニック。しかし、「どうせ腐らせてしまいそう」「カビが生えたらどうしよう」と、不安に思うかもしれません。
この記事では、失敗しやすい「腐敗」や「カビ」を防ぐ具体的な管理方法から、水苔を使った正しい手順、発芽後の鉢上げまでを徹底的に解説します。
[https://andplants.jp/collections/monstera]そもそもモンステラの「茎伏せ」とは?
「茎伏せ(くきふせ)」とは、モンステラの剪定(せんてい)などで出た「葉のついていない茎」だけを使って、新しい株を育てる増やし方です。
大きく育ちすぎて樹形が乱れたり、間延び(徒長)したりしたモンステラを仕立て直すとき、どうしても元気な茎をカットする必要があります。その捨ててしまうはずだった茎にも、生命は眠っているのです。
モンステラの茎には「節(ふし)」と呼ばれる少し膨らんだ部分があり、そこには「成長点」が隠されています。茎伏せは、この成長点を土や水苔(みズごけ)の上に伏せる(寝かせる)ことで、成長点から新しい芽と根が同時に出てくるのを待つ方法です。
葉がついた先端部分を水に挿す「水挿し」や、土に挿す「挿し木」と違い、茎だけの状態からスタートするため、見た目は少し地味かもしれません。しかし、何もない棒のような茎から、小さな緑の芽が力強く顔を出す瞬間は、まさに生命の神秘を感じる感動的な体験となるでしょう。
茎伏せは、植物の生命力を最後まで活かしきる、サステナブルな園芸の楽しみ方の一つ。あなたのモンステラの「かけら」から、新しい命を紡いでみませんか。
モンステラの茎伏せを行う最適な時期と必要な道具

モンステラの茎伏せは、植物が持つエネルギーを最大限に引き出すため、「いつ」行うかが成功を大きく左右します。
最適な時期は、モンステラの成長期にあたる5月〜9月頃です。最低気温が安定して20℃を超えるようになると、発根・発芽の活動が最も活発になります。
逆に、気温が下がる秋以降や冬場は休眠期に入るため、茎伏せを行っても芽が出ず、そのまま腐ってしまうリスクが非常に高くなります。暖かい季節を選んで挑戦しましょう。
作業を始める前に、必要な道具を揃えておくとスムーズです。特に雑菌の侵入は失敗(腐敗)の最大の原因となるため、刃物類は必ず消毒してから使ってください。
以下に、茎伏せに必要な道具のリストを示します。
- 節(ふし)のあるモンステラの茎
- 清潔なカッターナイフや園芸バサミ(アルコールや熱湯で消毒済みのもの)
- 用土(水苔、赤玉土、ベラボンなど)
- 茎を並べる容器(透明なプラスチックトレーやジップロックが観察しやすくおすすめ)
- (※任意)発根促進剤(メネデール、ルートンなど)
- (※任意)切り口の保護剤(トップジンMペーストなど)
道具の準備、特に「清潔さ」の確保が、新しい芽を迎えるための第一歩です。
モンステラの茎伏せを行う手順

道具が揃ったら、いよいよ茎伏せを実行します。ここからは、成功率を上げるための具体的な3つのステップを解説します。難しい作業はありませんが、一つひとつの工程を丁寧に行うことが大切です。
- 用土を決める
- 茎をカットし、清潔な用土に配置する
- 発根発芽を待つ
用土を決める
茎伏せのベッドとなる用土は、発根・発芽の成功を左右する重要な要素です。主に「水苔(みズごけ)」を使う方法と、「赤玉土(小粒)」などの清潔な土を使う方法があります。
どちらも可能ですが、初めて挑戦する方や、失敗したくない方には「水苔」を強くおすすめします。
水苔の最大のメリットは、発根や新芽の状態が観察しやすく、適度な湿度を保ちやすい点です。茎が腐っていないか、小さな根が出てきたかを目で見て確認できるため、管理が非常に楽になります。また、水苔自体が持つ抗菌作用も、腐敗防止に役立つと言われています。
土を使う場合は、排水性が高すぎて乾燥しやすかったり、逆に水持ちが良すぎて腐敗の原因になったりする調整が少し難しい側面があります。
使用する水苔は、あらかじめ水に浸して十分に吸水させた後、手で「しっとりする程度」に軽く絞ってから使いましょう。ビショビショの状態だと、茎が呼吸できずに腐る原因になるので注意が必要です。
茎をカットし、清潔な用土に配置する
準備したモンステラの茎を、いよいよカットしていきます。ここで最も重要なルールは、カットする一つひとつの茎に、必ず「節(ふし)」が含まれるようにカットすることです。
節は、茎の途中にある少し膨らんだ部分や、古い葉が落ちた跡の「V字」模様の部分です。新芽と根は、この節からしか出てきません。節がなければ、いくら待っても芽吹くことはないのです。
清潔なカッターで、1つの節(または2つ)を含むように、長さ5cm〜10cm程度にカットしていきます。葉が残っている場合は、蒸散を防ぐために根元から切り落とすか、葉を半分にカットします。
カットできたら、準備した水苔の上に茎を配置します。このとき、茎を完全に埋めてしまわないように注意してください。茎の半分程度が水苔に触れるくらいに、軽く押し込むように「伏せ」ます。節の向きが分かりにくければ、横向きに寝かせておけば問題ありません。気根(茶色い根)がついている場合は、気根ごと水苔に伏せると発根が早くなります。
発根発芽を待つ
茎の配置が終わったら、ここからは「待つ」管理が始まります。茎伏せの成功は、この管理フェーズにかかっていると言っても過言ではありません。
最も重要な管理ポイントは、茎を乾燥させないよう、湿度を高く保つことです。葉がない茎は水分を保持する力が弱いため、乾燥するとすぐにシワシワになってしまいます。
容器に蓋をしたり、食品用ラップをかけたり、あるいはジップロックのような密閉できる袋に容器ごと入れることで、内部の湿度を簡単に80%〜90%以上に保つことができます。これが「腐らせず、乾かさない」ための最大のコツです。
置き場所は、直射日光が当たらない「明るい日陰」が最適です。レースのカーテン越しの光などが良いでしょう。温度は引き続き20℃以上をキープしてください。
水やりは、水苔の表面が乾いてきたら霧吹きで湿らせる程度で十分です。密閉している場合は、数週間水やりが不要なこともあります。早ければ2週間、通常1ヶ月ほどで節の部分から白い根や緑色の新芽が動き出します。焦らず、静かにその時を待ちましょう。
モンステラの茎伏せ後の管理方法

無事に発芽・発根し、新しい鉢に植え替えた(鉢上げした)後のモンステラは、人間でいえば「生まれたての赤ちゃん」と同じ状態です。環境の変化に非常にデリケートなため、ここからは「養生期間」と捉え、丁寧な管理で新しい環境に慣らしてあげましょう。
置き場所は、茎伏せをしていた時と同様に、直射日光が当たらない「明るい日陰」が最適です。いきなり強い光に当てると、まだ力の弱い新しい葉が「葉焼け」を起こしてしまいます。
水やりは、植え替えに使った土の表面が乾いたタイミングで、鉢底から水が流れるまでたっぷりと与えてください。ただし、まだ根の吸水力は弱いため、常に土が湿っている状態(過湿)になると根腐れしやすいため注意が必要です。
最も重要なのが「肥料」です。植え替え直後のデリケートな根に肥料を与えると、肥料焼けを起こして枯れてしまう原因になります。新しい葉がしっかりと展開し、成長が軌道に乗るまでは肥料は一切与えません。
鉢上げから最低でも3〜4週間が経過してから、規定よりも薄めた液体肥料を少量から与え始めるのが安全です。
モンステラの茎伏せによくあるトラブルと対処法

モンステラの茎伏せは、高い湿度と温度を保つため、残念ながらトラブルが発生することもあります。しかし、その多くは原因を知れば予防・対処が可能です。
ここでは、「よくある失敗例」を3つのパターンに分けて解説します。焦らず、原因を突き止めて対処しましょう。
- 茎が腐る・黒くなる・ブヨブヨする
- 水苔や切り口にカビが生える
- いつまで経っても芽が出ない・根が出ない
茎が腐る・黒くなる・ブヨブヨする
茎伏せで最も多い失敗が「腐敗」です。茎が黒ずんだり、触るとブヨブヨと柔らかくなったり、酸っぱい異臭がしたりする場合は、腐敗が進行しています。
主な原因は、「水のやりすぎ(過湿)」、「温度不足」、そして「雑菌の繁殖」の3つです。特に、水苔をビショビショにしすぎると茎が呼吸できなくなり、そこに気温の低さ(20℃以下)が加わると、茎は活動を停止し、雑菌が一気に繁殖してしまいます。
腐敗やブヨブヨした部分を見つけたら、迷わずその茎を取り出してください。 手遅れでなければ、まだ間に合います。清潔なカッターで、腐敗している部分を健康な緑色の組織が見えるまで完全に切り落とします。その後、切り口を数時間乾かすか、殺菌剤(トップジンMペーストなど)を塗布してから、新しい清潔な水苔で再挑戦しましょう。
水苔や切り口にカビが生える
容器の中の湿度を高めていると、水苔の表面や茎の切り口に「白いフワフワとしたカビ」が発生することがあります。
これは腐敗とは異なり、主に「空気の停滞」によって引き起こされます。高湿度を保つことは重要ですが、空気がまったく動かない状態が続くと、カビ菌が繁殖しやすくなるのです。
カビを発見したら、まずはその部分をピンセットなどで物理的に取り除きます。少量であれば、アルコールを染み込ませたティッシュなどで軽く拭き取るのも有効です。ただし、カビが広範囲に広がっている場合は、茎を取り出して水洗いし、水苔をすべて新しいものに交換してください。
予防策としては、1日に1〜2回、数分程度で良いのでラップや蓋を開けて換気を行い、新鮮な空気に入れ替えることが効果的です。ただし、長時間開けっ放しにして湿度を下げすぎないよう注意しましょう。
いつまで経っても芽が出ない・根が出ない
「もう1ヶ月以上経つのに、何の反応もない…」そんな時、考えられる主な原因は「温度不足」または「節(成長点)の不在・不具合」です。
モンステラが活動を開始するには、最低でも20℃、できれば25℃前後の安定した気温が必要です。特に春先や秋口など、日中は暖かくても夜間に冷え込む時期は、植物が休眠モードに入ってしまい、発芽・発根のプロセスが停止することがあります。
もう一つの可能性は、カットした茎に「節(成長点)」が正しく含まれていなかったケースです。節がなければ、残念ながらいくら待っても芽は出ません。
まずは、置き場所の温度が20℃以上を安定してキープできているか再確認してください。 もし温度が低いようであれば、より暖かい場所へ移動させましょう。温度も節も問題ないのに動かない場合は、茎自体の体力が尽きかけている可能性もありますが、茎がシワシワになっていなければ、諦めずに気長に待ち続けることも大切です。
モンステラの茎伏せに関するよくある質問

茎伏せの基本的な手順やトラブル対処法をご説明してきましたが、実際に作業しようとすると、さらに細かな疑問が湧いてくるものです。
ここでは、茎伏せに挑戦する多くの方が抱く「よくある質問」にお答えし、皆さんの不安を解消していきます。
- 茎伏せは冬でもできる?
- 葉が付いたままでも茎伏せは可能?
- メネデールは使った方がいいの?
茎伏せは冬でもできる?
結論から言うと、モンステラの茎伏せを冬に行うことは推奨できません。
理由は、冬がモンステラの「休眠期」にあたるからです。この時期、植物は成長をほぼ停止しており、発根や発芽といった新しい活動を起こすためのエネルギーが不足しています。
気温が20℃を下回る(特に15℃以下になる)環境で茎伏せを行っても、茎は活動できず、そのまま体力を消耗します。さらに、低温と(水苔の)湿気が組み合わさることで、芽が出る前に腐敗してしまうリスクが非常に高くなります。
もし冬場に剪定が必要になった場合は、カットした茎は春まで水挿しなどで保管しておくのが無難です。24時間体制で20℃以上を保てる温室のような特別な環境がない限り、茎伏せは成長期である5月以降の暖かい季節まで待ちましょう。
葉が付いたままでも茎伏せは可能?
葉が付いた茎を伏せること(厳密には「挿し木」に近い方法)も可能ですが、成功率を高めるためには処理した方が賢明です。
植物は、葉の表面から水分を蒸散(じょうさん)させています。茎伏せの段階では、まだ水を吸い上げるための「根」がありません。その状態で大きな葉が付いていると、茎が持つわずかな水分が葉からどんどん奪われてしまい、発根する前に茎自体が乾燥してシワシワになってしまいます。
新しい芽や根を出すことにエネルギーを集中させるため、葉は思い切って茎の根元から切り落としてしまうことを強くおすすめします。
どうしても葉を残したい場合は、水分の蒸散量を減らすために、付いている葉をハサミで半分ほどの大きさにカットする処置が最低限必要です。茎伏せは、あくまで「茎」の生命力に期待する方法だと割り切りましょう。
メネデールは使った方がいいの?
メネデールに代表される植物活力剤(発根促進剤)は、茎伏せにおいて必須ではありません。しかし、使用することで成功率を高め、作業の「お守り」として精神的な安心感を与えてくれます。
メネデールは肥料とは異なり、鉄イオンなどを含んだ「活力液」です。植物が新しい根を出す際のストレスを和らげたり、発根を促したりする効果が期待できます。
使い方は簡単です。水苔を浸す水や、日々の霧吹きに使う水に、規定の倍率(通常100倍希釈)で薄めて使用するだけです。カットした茎の切り口を、薄めたメネデール液に数時間浸けてから伏せる(水揚げ)のも非常に効果的です。
特に、茎の元気がなさそうに見える場合や、斑入り品種のようなデリケートなモンステラで挑戦する際には、使用を検討する価値は十分にあるでしょう。
まとめ
モンステラの「茎伏せ」は、徒長した株の仕立て直しや剪定で出た茎を、新しい命として再生させる素晴らしい方法です。
成功のための最も重要なポイントは、①新芽と根の源である「節(ふし)」を必ず含めること、②雑菌が繁殖しないよう「清潔な道具と用土」を使うこと、そして③活動期(5月〜9月)に「湿度と温度(20℃以上)」を保ち、乾燥と腐敗を防ぐこと。この3点が成功の鍵となります。
単なる作業としてではなく、棒のような茎から小さな芽が顔を出すまでの静かな時間を楽しむプロセスとして、ぜひ茎伏せに挑戦してみてください。あなたの手で、新しい緑のパートナーを育てる喜びが待っているはずです。
[https://andplants.jp/collections/monstera]