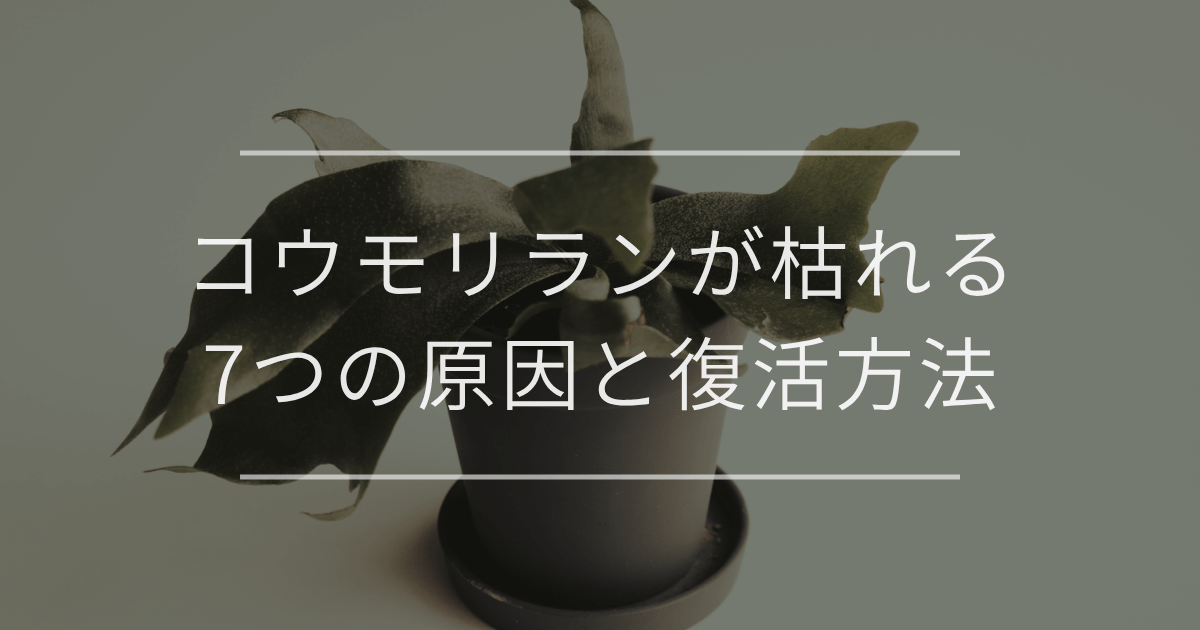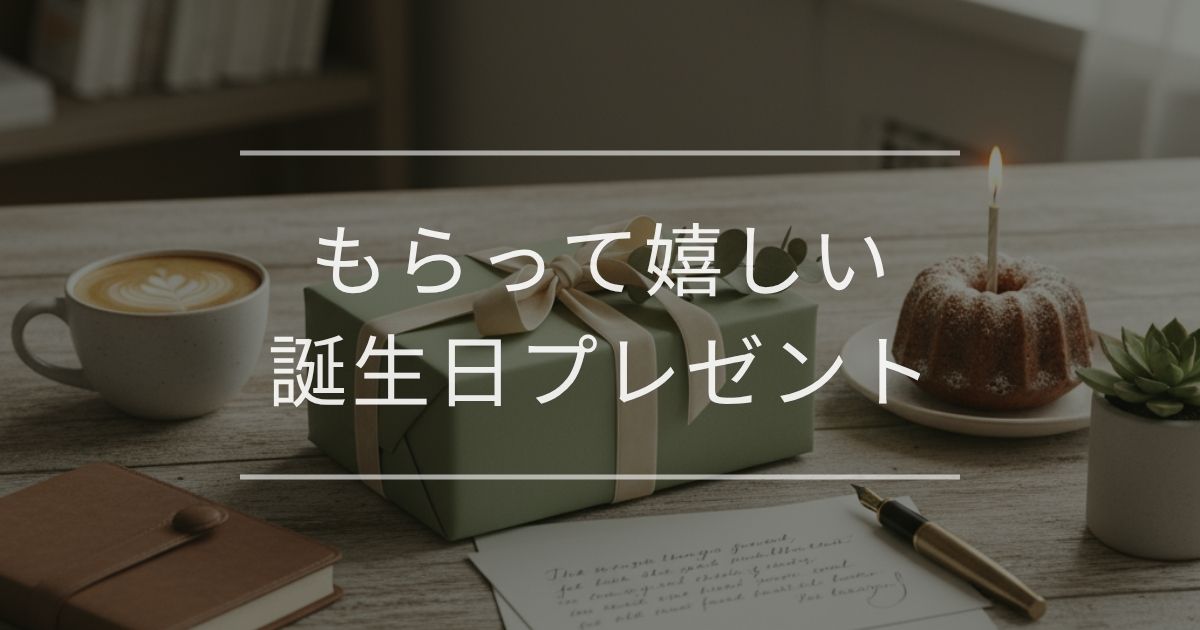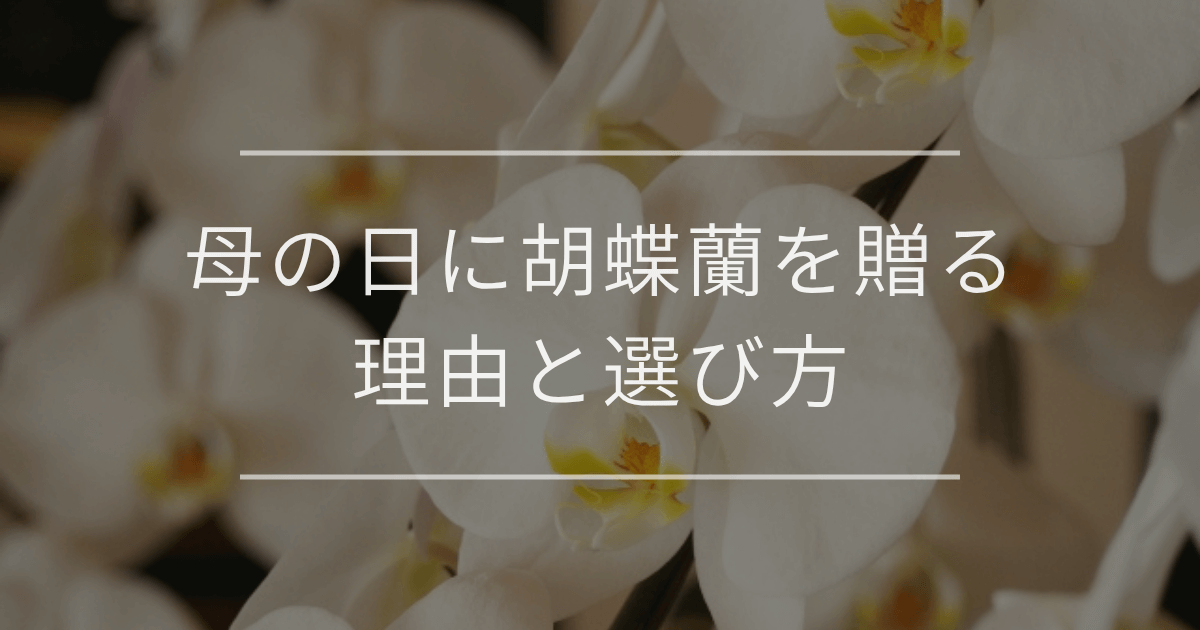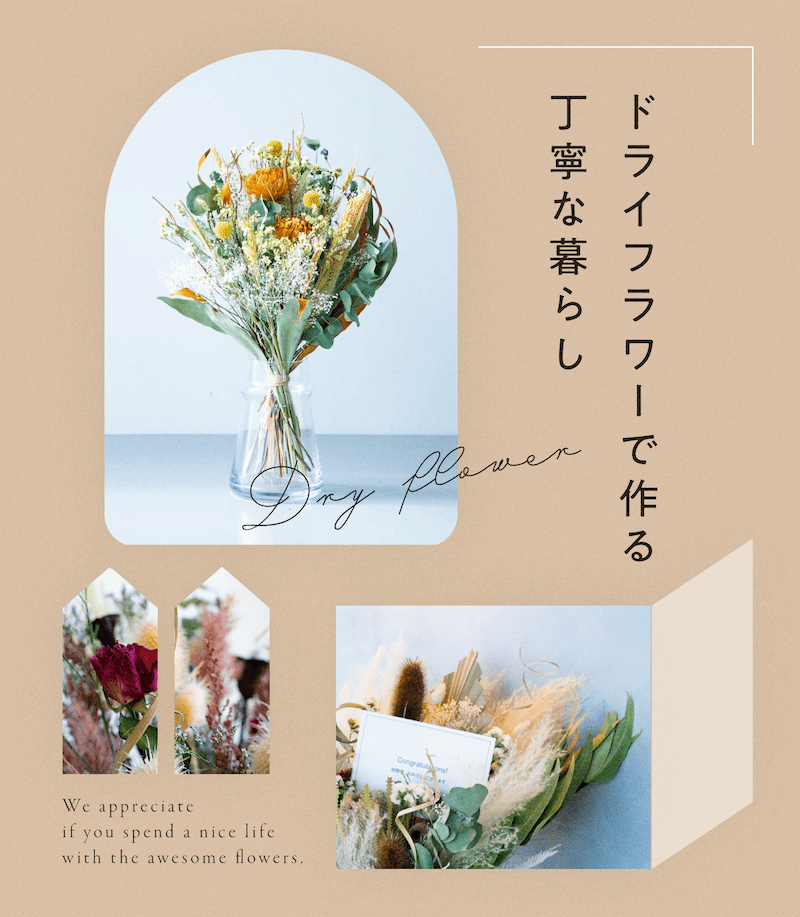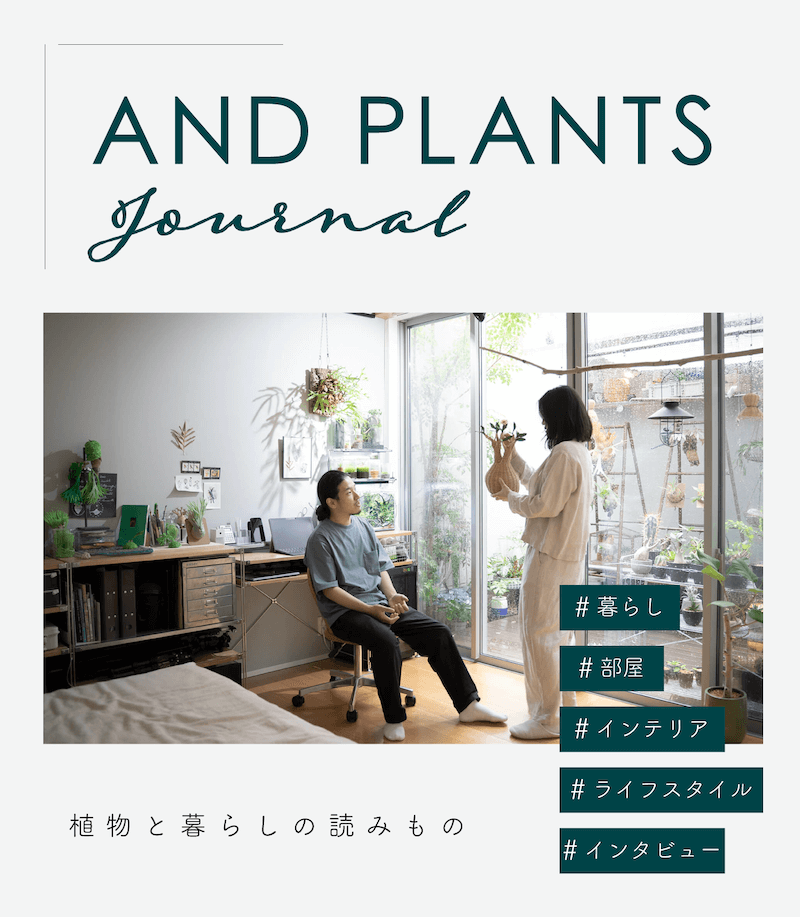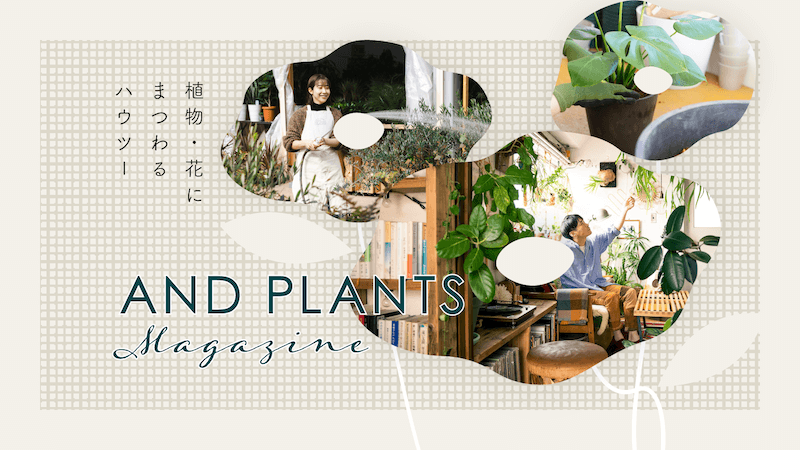「コウモリランの葉がふにゃふにゃになって垂れる」
「葉にシミが出来て枯れる」
と、コウモリランが枯れることに悩んでいませんか?インテリアグリーンとして育てる方も多いため、つい飾りっぱなしで枯らしてしまう方もいるかもしれません。
今回はコウモリランが枯れる7つの原因と復活方法を詳しく解説します。枯れそうなサインも紹介しているので、同様のサインを見つけた場合は、すぐに対処しましょう。
枯れそうなサインをあらかじめ知っておき、紹介している復活方法を試せば、すぐに元気になりやすいです。いつも元気でおしゃれなコウモリランを楽しむためにも、ぜひ最後までご覧ください。
コウモリランが枯れる7つの原因
コウモリランが枯れる主な原因には、以下の7つがあります。
- 水のやりすぎ(やらなすぎ)
- 10℃以下、30℃以上の温度
- 風通しの悪さ
- 日当たり過不足
- 肥料の与え過ぎ
- 病害虫
- 室内の日陰から屋外の日向への移動
それぞれの原因を詳しく見ていきましょう。
①水のやりすぎ(やらなすぎ)
コウモリランが枯れる原因の1つに水やり加減があります。水のやりすぎ、またはやらなすぎによって、枯れるケースが多い植物です。
水のやりすぎは、根腐れを引き起こします。根腐れが進むとコウモリランは枯れるので注意してください。
また、コウモリランはインテリアグリーンとして非常に人気のある植物です。そのため、板付けして壁に飾ったりハンギングで吊るしたりしている方も多いのではないでしょうか。
インテリアのように飾っていると、つい水やりを怠ってしまいがちになります。水苔や土が乾きすぎると、徐々に葉色が薄くなり始め、枯れていきます。
季節に応じて、土や水苔の乾燥具合を確認して水やりしましょう。
②10℃以下、30℃以上の温度
コウモリランが枯れる原因は、温度にもあります。品種によって耐寒性・耐暑性は異なりますが、基本的な生育適温は、およそ15~30℃です。
15℃以下では生育が緩慢になり、10℃以下の寒さでは枯れる可能性が高くなります。冬は暖かい場所で管理してください。
寒さだけではなく、真夏の暑さにも注意が必要です。近年、日本の夏は30℃を超える日が多く、コウモリランにとっても枯れるリスクが高くなっています。
30℃を超えると暑さと蒸れによって枯れやすいので、なるべく涼しい場所で管理してください。
③風通しの悪さ
コウモリランは、締め切った室内のような風通しのない環境では枯れやすい植物です。風通しは、植物の生育に欠かせないポイントであり、病害虫や蒸れを防止する役割があります。
風通しがなければ、水やり後にコウモリランが蒸れやすいです。夏の水やりでは、特に暑さも相まって、致命的なダメージとなります。
日頃から、窓を開けたりサーキュレーターを設置したりして空気を動かすように心がけましょう。
④日当たりの過不足
コウモリランが枯れる原因には、日当たりも関係しています。植物である以上、光合成が必要なので、まったく日差しが差し込まない暗い環境では育ちません。
かといって、コウモリランは直射日光を好まないため、屋外の日当たりの良い環境では枯れやすいです。
直射日光が当たらない、明るい環境で管理するようにしてください。日差しが直接当たる場合は、レースカーテンやシェードで日差しを弱めたり、当たらない場所に移動させたりしましょう。
⑤肥料の与え過ぎ
コウモリランに過剰な置き肥や濃度の高い液肥を与えると、根傷みをして枯れる可能性があります。早く大きくしたいからと言って、肥料を与えすぎることがないように気を付けましょう。
吸収されなかった過剰な栄養分は、土や水苔に残り続けて根を傷めるだけでなく、土壌環境を悪化させます。根が水分を吸収できなくなり、水切れと同じような症状を表すことも。
肥料の種類によって与える量やペースは異なるため、記載されている用量用法を守ってください。
⑥病害虫
コウモリランには以下の病害虫が発生します。そのままにしておくと枯れる原因になるので、注意してください。
- 炭疽病
- ハダニ
- カイガラムシ
炭疽病は葉に斑点が入り、症状が悪化すると斑点に穴が開き始めます。株全体に広がり、枯れる原因となります。
傷口から菌が侵入して発生する病気なので、日頃からコウモリランを丁寧に扱い、傷がつかないように気を付けましょう。カビや細菌が増殖しないように、風通しの良い環境で管理することも重要です。
ハダニやカイガラムシが増殖すると、コウモリランの生育は悪化します。糞が原因で発生するすす病も誘発させる場合もあるので、見つけ次第すぐに取り除いてください。
⑦室内の日陰から屋外の日向への移動
コウモリランは明るい環境を好む植物ですが、室内の日陰から急に屋外への日向へ移動させると枯れる恐れがあります。急な環境変化は、植物に大きなストレスがかかるためです。
暗い日陰で長く育てていたコウモリランを明るい場所に移動させる場合は、中間の明るさに1週間ほど置き、光に慣れさせてください。その後、置きたい明るさの場所に移動させましょう。
急な環境変化は、明るさだけではありません。温度差のある環境に急に移動させると弱りやすいので、いきなり場所を移動させずにワンクッション挟むようにすると安心です。
コウモリランの枯れそうなサイン

コウモリランの枯れそうなサインは、以下の5つです。
- 葉に茶色~黒いシミが現れる(褐斑細菌病)
- 葉が黄色~茶色になる
- 貯水葉が腐る
- 胞子葉がふにゃふにゃと垂れる
- 水苔にカビが生える
枯れそうなサインを把握しておくと、すぐに対処・復活させることができます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
葉に茶色~黒いシミが現れる(褐斑細菌病)
コウモリランの葉に茶色~黒いシミが現れるようになると、枯れそうなサインだと思ってください。主に茶色~黒いシミは、褐斑細菌病(かっぱんさいきんびょう)が原因の症状です。
褐斑細菌病は湿度が高く、風通しが悪い環境、かつコウモリランが弱っていると出やすい病気です。しかし、褐斑細菌病でコウモリランが枯れることはほとんどありません。
重要なポイントは、「弱っている場合に出やすい症状であること」。つまり、今までの環境や育て方が悪かった証拠です。
葉に茶色~黒いシミが出始めたら、環境や育て方を見直して改善してください。生育が良くなり始めると、新しい葉にはシミは現れなくなります。
葉が黄色~茶色になる
コウモリランの葉が黄色~茶色になり始めた時は、枯れそうなサインです。主に黄色~茶色の葉になる症状は、以下の原因が考えられます。
- 水切れ
- 根腐れ
- 根詰まり
- 葉焼け
- 日当たり不足
- 肥料不足
- 病害虫
さまざまな原因がありますが、環境や育て方、水苔や土の湿り具合などをチェックして改善してください。
ただし、古い葉が1枚だけ黄色くなるといった症状の場合は、生育における自然な代謝によるものです。また、葉っぱ1枚が枯れそうだからといって、株全体もすぐにダメになるわけではありません。
筆者が持っているコウモリランの葉も、時折枯れそうになりますが、一方で新芽も順調に出てきているので、問題なく成長しています。
貯水葉が腐る
コウモリランの貯水葉が枯れるのではなく、腐る場合は枯れそうなサインです。
貯水葉は最初は緑色ですが、時間が経ち古くなってくると自然に茶色く枯れます。その後、新しい貯水葉を出し始める仕組みです。
そのため、枯れること自体は心配いりませんが、黒く溶けたように腐る場合は気を付けてください。水やりが多すぎたり蒸れたりして株が傷んでいる可能性があります。
そのままにしておくと枯れるかもしれません。腐った部分は取り除き、風通しの良い場所に移動させて様子を見てください。
胞子葉がふにゃふにゃと垂れる
胞子葉がふにゃふにゃと垂れる場合も枯れそうなサインです。水切れによって現れることがほとんど。
コウモリランは乾燥に弱い植物です。霧吹き程度の水やりでは、まったく吸水できていない可能性があります。
屋外に出して、たっぷりとホースシャワーで水やりしたり、バケツに水を溜めてドボンと漬け込んで吸水させましょう。筆者は、基本ベランダでホースシャワーで水やりして、月に1回は溜め水に1時間程度浸けて吸水させています。
しっかり吸水させると、張りのある葉に戻ります。ただし、あまりにも水切れ期間が長いと、元には戻らないので注意してください。
水苔にカビが生える
コウモリランを水苔で育てている場合に、水苔にカビが出始めたら枯れそうなサインです。風通しが悪い証拠で、水苔そのものが傷み始めています。
水苔内の根が腐っている可能性もあるので、注意してください。カビが発生している部分は取り除き、風通しの良い場所へ移動させましょう。
風通しがよい場所がなければ、扇風機やサーキュレーターを付けてお部屋の空気を動かしてください。エアコンで空気を動かすのも良いですが、エアコンの乾いた風が直接当たらないように気を付けましょう。
枯れそうなコウモリランの復活方法

枯れる原因や枯れそうなサインを把握したら、具体的な復活方法を見ていきましょう。
- 状態の悪い葉は切り取る
- 水苔または土の乾燥具合をチェックする
- 植え替える
- 明るく風通しの良い環境に移動させる
- 発根剤を与える
状態の悪い葉は切り取る
状態の悪い葉は切り取ってください。見た目が悪いだけでなく、他の葉に悪影響を及ぼしたり、風通しの悪化に繋がったりします。
根元からポロっと取れるのであればよいですが、多くの場合、しっかりとくっ付いているため、取り除きにくいはずです。剪定ハサミで、慎重に根元付近を切り取りましょう。
残った部分は、時間が経つと完全に枯れてポロっと取れます。復活し始めると、そのころには新しい葉が伸び始めている頃なので、見た目も気にならなくなるので、安心してください。
葉先だけが枯れている場合は、見た目が不自然にならないように、枯れ込んでいる部分だけを切ると良いでしょう。
水苔または土の乾燥具合をチェックする
コウモリランの復活には、水苔または土の乾燥具合のチェックは欠かせません。状況によって、以下の復活方法をそれぞれ試す必要があるためです。
| 症状 | 復活方法 |
| カラカラに乾燥 | バケツに溜めた水に浸け込む |
| 常に湿っている状態 | 風通しの良い場所に移動させる |
| 湿っているが、葉がふにゃふにゃ | 植え替える |
水苔や土が湿っているにも関わらず、葉がふにゃにゃと垂れている場合は、根腐れしている可能性があります。根腐れして吸水できずに、水切れと同じ症状が出ています。
そのため、根腐れを疑って植え替えをした方が安心です。
植え替える

根腐れや根傷み、根詰まりによって、枯れそうな場合は、植え替えをして復活させましょう。枯れそうな株を植え替える場合は、基本的に同じ用土で植え替えてください。
土で育っているコウモリランを、急に水苔にしないようにしましょう。その逆も同様です。急な環境変化によって、より状態が悪くなる可能性があります。
コウモリランの根は細く、びっしりと張ります。また、根自体も黒っぽいため、枯れている根を判断しづらいです。
明らかに溶けたような根や干からびた根だけを取り除いて植え替えましょう。
明るく風通しの良い環境に移動させる
コウモリランを暗い場所や風通しのない場所で育て続けて枯れそうな場合は、まずは明るく風通しの良い場所へ移動させてください。
ただし、急に直射日光に当てないようにしましょう。急な環境変化にならないようにします。
根腐れや水切れ、病気で枯れそうになっている場合を除けば、適切な環境へ移動させるだけで復活しやすいです。
もし、お部屋の窓やカーテンを開ける機会が少ない場合は、日頃から植物LEDライトで補光しつつ、サーキュレーターで空気を動かしてください。お仕事の関係で外出の機会が多く、お部屋が暗くなりがちな方は、植物LEDライトやサーキュレーターを取り入れることをおすすめします。
AND PLANTSでは、太陽光に近い波長を発する植物育成ライト「TSUKUYOMI 10W ホワイト」を取り扱っています。ライトスタンドと合わせて使うと、室内でもおしゃれ、かつ元気にコウモリランを育てられるでしょう。
[https://andplants.jp/products/tsukuyomi-10w]発根剤を与える

根傷みや根腐れの初期、植え替え後は発根剤を与えて、復活させてください。元気な根が伸びれば、新しい葉がぐんぐんと出始めます。
枯れそうだからと言って、「元気になるように肥料を与える」ことがないように気を付けてください。枯れそうなタイミングで、栄養分が多い肥料を与えても、吸収できずに逆効果です。
まずは、新しい根を伸ばすことに注力しましょう。発根剤を水に薄めてたっぷり水やりしたり、発根剤入りの水に浸け込んで吸水させたりします。
その後は、明るく風通しの良い場所で様子を見ましょう。AND PLANTSでは「微生物の力で植物を元気にする水」を取り扱っています。
光合成細菌の働きによって、弱った植物を元気にする効果もあるので、ぜひ一度使ってみてください。
[https://andplants.jp/products/microorganismswater]コウモリランを枯らさない基本的な育て方

コウモリランを枯らさないためには、基本的な育て方をしっかり守ることが重要です。ここでは、項目別に基本の育て方を表にまとめて簡単に紹介します。
| 項目 | 育て方 |
| 日当たり | 直射日光の当たらない明るい場所に置く |
| 風通し | 密室にせずに、空気が動く環境にする |
| 温度 | 最低10℃以上をキープする |
| 水やり | 春夏:土や水苔の表面が乾いてから 秋冬:土や水苔が乾いてから2~3日後 |
| 肥料 | 緩効性肥料、液体肥料を生育期に少し与える |
基本的なコウモリランの育て方は、「プロが教えるビカクシダ(コウモリラン)の育て方」で解説しています。初めて育てる方は、基本の育て方を確認しておきましょう。
コウモリランが枯れそうな時によくある質問

最後にコウモリランが枯れそうな時によくある質問とその答えを以下にまとめました。
- 枯れた貯水葉は切った方がいい?
- 冬に葉が枯れ始めたら、植え替えてもいい?
それぞれ詳しく見ていきましょう。
枯れた貯水葉は切った方がいい?
枯れた貯水葉は、切らずにそのままにしてください。貯水葉は枯れて幾重にも重なることで、水分や養分を蓄えるスポンジの役割をするためです。
元気なコウモリランは代謝によって、枯れた貯水葉の上に新しい貯水葉を広げます。無理に枯れた貯水葉を切り取ると見栄えが悪くなるので、気を付けてください。
ただし、貯水葉が茶色く乾燥したように枯れるのではなく、湿った状態で腐っているようであれば、確認して切り取った方が良いです。
冬に葉が枯れ始めたら、植え替えてもいい?
コウモリランの葉が冬に枯れ始めても、植え替えは控えてください。冬は生育が緩慢なので植え替えると、植え傷みから回復できずに状態が悪化する可能性があります。
まずは、葉が枯れ始めている原因を突き止めましょう。寒さなのか、根腐れなのか確認することが重要です。
寒さであれば、室内温度を最低でも10℃以上をキープ。15℃程度まで上げられると、より安心です。
根腐れであれば、まずは土や水苔を乾燥気味にして、発根剤を与えながら様子を見てください。最低気温が安定して15℃以上になる5月以降に植え替えをしましょう。
まとめ
コウモリランは日当たりや水やりの過不足、風通しなどによって枯れます。この記事で紹介した原因やサインに注意して復活方法を試していけば、安心して育てられるでしょう。
常に元気に育てるためにも、枯れそうなサインを見逃さずに、明るさや風通し、温度、水やりなどに注意して育ててください。原因とサイン、復活方法を把握しておけば、何かあっても元気な姿を取り戻せるはずです。
イキイキとしたコウモリランのある生活を、ぜひ楽しんでください。
- 初めてでもわかるコウモリランの育て方を確認したい方はこちら
- コウモリランのケアグッズを購入したい方はこちら