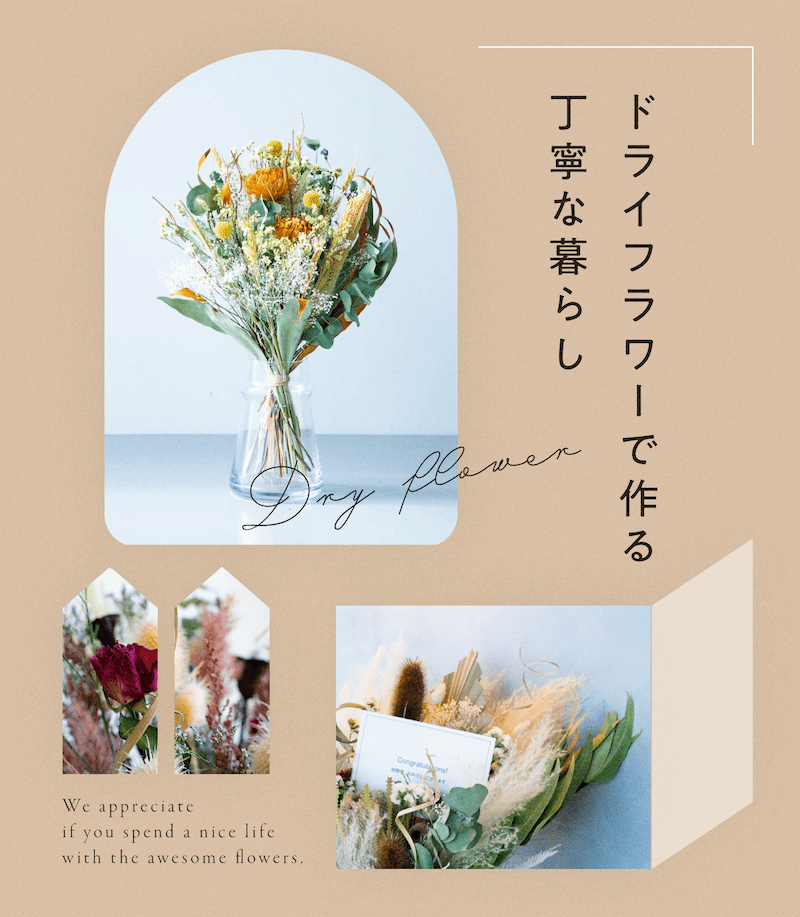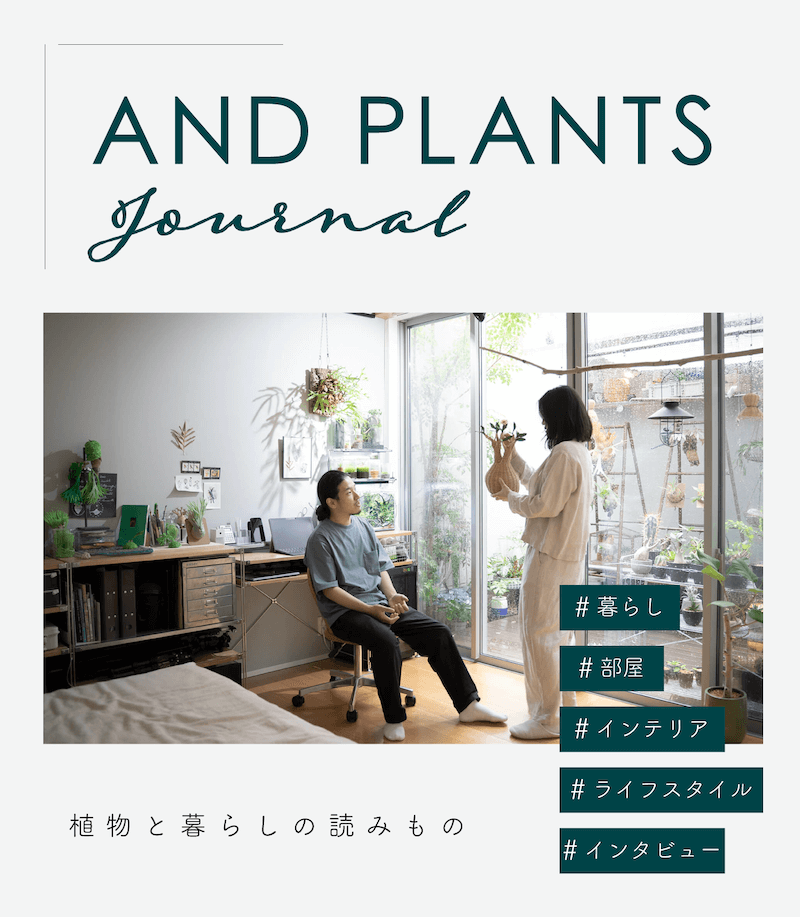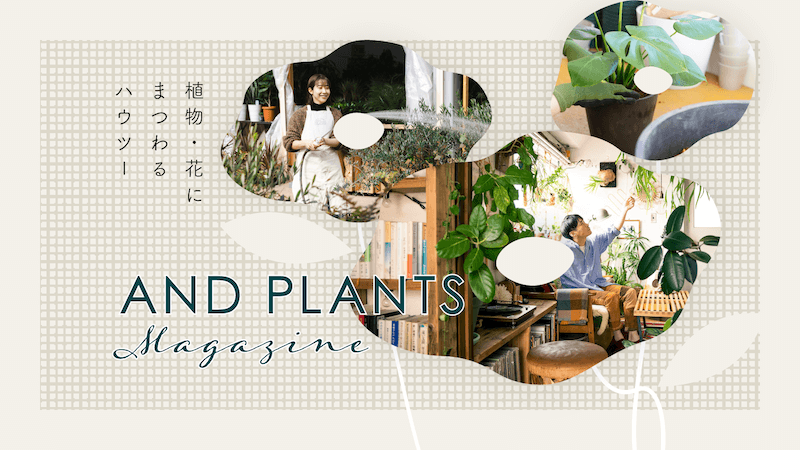| 項目 | 内容 |
| 植物名 | カラー |
| 学名 | Zantedeschia |
| 英名 | Calla lily、 Arum lily |
| 和名 | オランダカイウ(和蘭海芋) |
| 科目/属性 | サトイモ科/オランダカイウ属 |
| 原産地 | 南アフリカ |
| 性質 | 多年草 |
| 草丈 | 30~100cm |
| 日当たり | 日当たりのよい場所を好む |
| 生育適温 | 15~25℃ |
| 耐寒性 | 弱い |
| 耐暑性 | 強い |
| 水やり | 鉢植え:湿地性/乾く前に与える、畑地性/乾いてからたっぷり 地植え:降雨任せ |
| 肥料 | 植え付け時:緩効性の粒状肥料 生育期:地植えはなし、鉢植えは液体肥料 |
| 開花時期 | 6~7月頃 |
カラーの人気の品種や価格相場などについては、下記の特集ページも参考にしてみてください。
[https://andplants.jp/collections/flowers_callalily]カラーの特徴
カラーは、スラリと伸びた茎と先端のくるりと巻いたようなスタイリッシュな姿が魅力です。
実は、花に見える部分は仏炎苞(ぶつえんほう)と呼ばれ、ガク(花を保護する部分)が発達したもの。本当の花は、仏炎苞の中にある黄色い棒状の部分になります。
とはいえ、カラーは見ためが優雅で美しく、鑑賞のしがいがありますよね。
ウェディングシーンでも人気があり、切り花での需要が多いイメージがありますが、鉢植えや庭植えして育てることも可能です。
上手に育てれば、6~7月にかけてきれいな花をたくさん咲かせてくれますよ。
また、ハートや矢じりのような形をした葉も、青々としたみずみずしさで、鉢や花壇を爽やかに彩ってくれるでしょう。
カラーの種類

カラーを育てる前に、次の2つの種類があることを理解しておきましょう。
- 湿地性
- 畑地性
湿地性と畑地性は、好む環境が異なります。特徴とともに主な品種を紹介していくので、育てるときの参考にしてください。
湿地性
湿地性のカラーの特徴は、主に次の通りです。
- 花茎が太く花が大きい
- 花の色は白やピンクが多い
- ハート型の肉厚な葉で光沢がある
- 花茎や葉柄は水分が多く含まれている
- 生育地は湿った場所を好む
- 年間を通して葉が茂っている
湿地性のカラーは、次の園芸品種が主に流通しています。
| 品種 | 花の色 |
| エチオピカ(和名:オランダカイウ) | 白 |
| シルクロード | 白 |
| ドリーミーピンク | 薄いピンク |
畑地性
畑地性のカラーの特徴は、主に次の通りです。
- 湿地性に比べて茎が細いものが多い
- 白やピンク以外に、黄色やオレンジ、赤、紫などカラーバリエーションが豊富
- 葉の形はハート形や細長いタイプなどさまざまで、斑点のある葉もある
- 生育地は水はけのよい場所を好む
- 休眠期になると地上部の葉が枯れる
畑地性のカラーは、次のような園芸品種がよく流通しています。
| 品種 | 花の色 | 葉の特徴 |
| キバナカイウ | 黄色 | 白い斑点がある |
| モモイロカイウ | 桃色 | 斑点なし |
| シラホシカイウ | 白 | 白い斑点がある |
| ピカソ | 白と紫のバイカラー | 白い斑点がある |
カラーの基本的な育て方

次に、カラーの育て方を解説していきます。
- 日当たりと置き場所
- 栽培温度
- 水やり方法と頻度
- 肥料の与え方
- 夏越し方法
- 冬越し方法
きれいな花を咲かせるために、しっかり基本を押さえておきましょう。
日当たりと置き場所
カラーが育ちやすい日当たりと置き場所は、湿地性と畑地性で異なります。それぞれの特徴を考慮した場所を選びましょう。
湿地性
- 日当たりと風通しがよい水辺を好む
- 花壇や鉢植えでも湿り気があればOK
- 大きく育つので、地植えはスペースを広く取るとよい
畑地性
- 日当たりと風通しがよく、水はけのよい場所で育てる
- 乾燥気味を好む
カラーの鉢植えは、室内で育てることも可能です。ただし、日当たりと風通しのよい窓辺に置くなど、環境に気を配りましょう。
栽培温度
カラーを育てるときの適温は、湿地性と畑地性どちらも15~25℃くらいです。
暑さに強いですが、真夏の高温多湿は株が弱りやすくなります。真夏は、半日陰や風通しのよい場所で育てるとよいでしょう。
また、半耐寒性で寒さにそれほど強くないので、冬は防寒対策が必要です。
水やり方法と頻度
カラーの水やりも、湿地性と畑地性で異なります。
湿地性の水やり
- 土が乾く前に、たっぷり水を与える
- 4~6月の成長期に水切れすると花が咲きにくくなるので、鉢植えは腰水栽培がおすすめ
- 腰水栽培とは:受け皿に水を溜めて、底面を湿らせることで水切れを防ぐ方法
ただし、真夏に受け皿の水温が上がるようなら、腰水を中断しましょう。温かい水によって、腐りやすくなるからです。
畑地性の水やり
- 春から夏の生育期:土の表面が乾いたら、たっぷり水を与える
- 秋から冬の休眠期:葉が枯れたら休眠期の合図なので、水やりをストップする
また、地植えは基本的には降雨に任せ、何日も雨が降らない場合は水やりを行います。湿地性と異なり、常に土が湿っていると球根が腐ってしまうので注意しましょう。
肥料の与え方
カラーの肥料の与え方は、湿地性と畑地性で違いはありません。
肥料の与え方
- 植え付け時に、緩効性肥料を与える
- 地植えの場合は、追肥は不要
- 鉢植えは、4~6月の生育期に液体肥料を7~10日に1回程度与える
- 花が終わったら、施肥をストップする
真夏の高温期に肥料分が土に残っていると、球根が腐る原因になってしまいます。花が咲き出したら肥料を控え始め、真夏になる前に中断しましょう。
夏越し方法
カラーは暑さに強いですが、高温多湿に弱い性質を持っているため、夏越しには注意が必要です。
鉢植えと地植えでポイントをまとめたので、参考にしてください。
鉢植え
- 半日陰の風通しがよい場所に移動させる
- 水やりは早朝や夕方行い、温かい水で球根が腐るのを防ぐ
- 雨の日は軒下に移動させて過湿を防ぐ
- 湿地性は土が乾かないように注意する
- 畑地性は土の表面が乾いたら水やりを行う
- 夏の間は肥料を与えない
地植え
- 夏越しさせる場合は、あらかじめ半日陰になる場所に植えておく
- 西日を避けられる東から南向きに植えるのがベスト
- 水やりは早朝や夕方行う
- 湿地性は水切れしないように、土が乾く前に水やりをする
- 畑地性は、土の表面が乾いてから水やりをする
真夏の強い日差しと、過湿になりやすい雨に注意しましょう。
冬越し方法
カラーは半耐寒性球根植物で、寒さに弱い性質があります。温暖な地域では植えっぱなしで越冬できますが、寒冷地では適切な対策が必要です。
また、湿地性のカラーは基本的に常緑ですが、畑地性のカラーは地上部が枯れた状態で越冬します。
鉢植え
- 霜や雪が心配な地域は、室内に取り込む
- 日当たりと風通しのよい場所に置く
- 湿地性は、乾燥しないように控えめに水やりを行う
- 畑地性は水やりなし
地植え
- 温暖な地域は、腐葉土やわらなどで軽くマルチングをする
- 寒冷地は、霜が降りる前に球根を掘り上げる
掘り上げた球根は次の手順で保管し、春になったら植え付けを行います。
掘り上げた球根の管理方法
- 土を落として陰干しをする
- 湿らせた水ゴケや新聞紙に包む
- 5℃以上保てる場所で管理する
畑地性のカラーは、地上部が枯れたら地際でカットし、球根を掘り上げましょう。
カラーの植え付け方法

次に、カラーの植え付け方法を解説します。
- 球根の選び方
- 用土
- 植え付けの適期とやり方
立派に育ったカラーの鉢を買ってきて楽しむのもいいですが、球根から植え付けるのも育て甲斐がありますよ。
球根の選び方
カラーの球根を選ぶときは、次の点をよく確認しましょう。
球根を選ぶポイント
- 発根部分がきれい
- 皮が剥がれていない
- 大きくて重さがある
- 球根全体にハリがある
すでに育っている苗を購入するときは、次の点をチェックしてみてください。
苗を選ぶポイント
- 葉や茎に艶がある
- 花が多い
- 株元がしっかりしている
- 病害虫がついていない
よい球根や苗を選ばないと、上手く育たなかったり病害虫に弱かったりしやすくなるので、しっかり確認してから購入しましょう。
用土
カラーを植え付ける用土は、湿地性と畑地性で異なります。
湿地性のカラーは、水はけと水持ちがよい土を好みます。一方で、畑地性のカラーは、水はけのよさを重要視することが大切です。
湿地性の用土
- 鉢植え:市販の草花用培養土に、パーライトやピートモスを1~2割くらい混ぜる
- 地植え:土壌に腐葉土や堆肥を混ぜておく
パーライトは水はけを、ピートモスは保水性を高めてくれます。また、腐葉土は保水性や保肥力を高め、堆肥を混ぜるのは栄養を与えるためです。
畑地性の用土
- 鉢植え:市販の草花用培養土に、赤玉土や軽石を1~2割くらい混ぜる
- 地植え:土壌に腐葉土や堆肥を混ぜておく
赤玉土は保水と排水のバランスをよくし、軽石は水はけと通気性を高めてくれます。
植え付けの適期とやり方
カラーの植え付けの適期は、暖かくなり始める3月下旬から、気温が安定する4月上旬頃です。
湿地性カラー:球根の植え付け方
- 土を湿らせておく
- 球根の凸凹した側を上にする
- 地表と同じくらいの高さに植え付ける
- 地植えする場合は、球根同士を50~80cmくらい離す
- 7~10日間くらい水やりを控えてから、水を与え始める
苗も、湿った土に球根の頭を地表と同じ高さにして植え付けます。
畑地性カラー:球根の植え付け方
- 球根の凸凹した側を上にする
- 土の表面から3~5cm深くなるよう植え付ける
- 地植えやプランターに植える場合は、球根同士を20cmくらい離す
- 土をかぶせたら、7~10日間は水やりを控える
苗を植えるときも、球根が土の表面から3~5cmくらい埋まるように植え付けます。
カラーのよくあるトラブルと対処法

植物を育てていると、花が咲かなかったり枯れてしまったりなど、さまざまなトラブルに見舞われることもあるでしょう。
ここでは、カラーを育てているときによくあるトラブル4つと、対処法を解説していきます。
- 花が咲かない
- 葉が枯れた
- 根腐れした
- 元気がない
カラーを元気に育てられるように、しっかりチェックしていきましょう。
花が咲かない
カラーの花が咲かない原因としては、主に次のような理由が考えられます。
- 日当たり不足
- 水やり不足
- 栄養不足
カラーは、成長期にしっかり日に当てることで花芽を形成します。また、適切な水やりと肥料も、花芽の形成に必要です。
特に、肥料はリン酸が少ないと花が咲きにくいので、与えている肥料の配合もチェックしてみましょう。
葉が枯れた
カラーの葉が枯れる原因としては、主に次のような理由が考えられます。
- 水やり不足
- 真夏の直射日光
- 高温多湿
- 病害虫による被害
- 寒さ
湿地性のカラーは、湿った土を好みます。畑地性のカラーも、あまりに乾燥しすぎると枯れる原因になるので、水やりを見直してみましょう。
カラーは、真夏の直射日光や高温多湿に弱い性質を持っています。特に、夏は半日陰や風通しのよい場所で育てることが大切です。
また、病害虫によって株が弱り、葉が枯れることもあります。
畑地性のカラーは、寒くなると地上部が枯れるので問題ありません。しかし、湿地性のカラーの葉が冬に枯れたら、寒さによって弱った可能性があります。
鉢植えは室内に、地植えは球根を掘り上げるなど、管理方法を見直しましょう。
根腐れした
カラーの根腐れの原因は、主に次のような理由が考えられます。
- 水の与えすぎ
- 肥料の与えすぎ
- 土壌の水はけが悪い
- 高温多湿
畑地性のカラーは、湿りっぱなしの土に植わっていると腐る原因になります。水は表土が乾いてから与えることと、水はけのよい土に植えることが大切です。
また、肥料が多すぎると肥料焼けを起こすため、適量を与えるようにしましょう。
夏場の高温多湿も根腐れの元なので、半日陰で風通しのよい場所で育てられるよう、環境も見直してみてください。
元気がない
カラーが元気がない原因は、主に次のような理由が考えられます。
- 日当たり不足
- 水やり不足や過多
- 栄養不足
- 病害虫による被害
元気のよいカラーを育てるためには、適切な成育環境と管理が大切です。
足りなかったりやりすぎたりしていないか、もしくは病害虫による被害にあっていないか、よく確認してみましょう。
カラーに発生しやすい病害虫と対処法

次に、カラーに発生しやすい病害虫と対処法を解説していきます。
- うどんこ病
- 軟腐病
- 灰色かび病
- アブラムシ
- アザミウマ
- ハモグリバエ
病害虫の予防や駆除には、適切な栽培管理を行い、発見したらすぐに対処することが大切です。
カラーを含めたお花や観葉植物のケアグッズは下記のページで詳しくまとめています。
[https://andplants.jp/collections/caregoods]うどんこ病
カラーにうどんこ病が発生すると、次のような症状が段階的に発生します。
- 葉に白い粉のような斑点ができる
- 進行すると葉全体が白くなる
- 黄色に変色したり枯れたりする
- 生育不良になり枯れる
うどんこ病の発生時は、次のような対策を行います。
- 病斑のある部分を取り除く
- ベニカXファインスプレーなどの殺菌剤を散布する
うどんこ病は、日当たりと風通しのよい場所で、水はけをよくしておくと予防できます。また、殺菌剤を定期的に散布することも予防に有効です。
軟腐病
カラーに軟腐病が発生すると、次のような症状が段階的に発生します。
- 葉や葉柄に、水に浸したような暗緑色の斑点ができる
- 斑点が拡大すると、葉や茎が軟化して腐敗する
- 腐敗した部分から悪臭が発生する
- 放置すると株全体に広がり、腐敗して枯れる
軟腐病の発生時は、次のような対策を行います。
- 発生したら株ごと除去する
- 発生した場所は土壌消毒を行う
軟腐病が発生すると、治療はほぼできません。
植え付け時は清潔な用土を使い、水はけと日当たりのよい場所で、窒素分が少ない肥料を使うといった、予防を心がけることが大切です。
灰色かび病
カラーに灰色かび病が発生すると、次のような症状が段階的に発生します。
- 花や葉に水が染みたような褐色の斑点ができる
- 病斑が拡大すると腐敗していき、灰色のカビに覆われる
灰色かび病の発生時は、次のような対策を行います。
- 病斑箇所を取り除く
- ベニカXファインスプレーなどの殺菌剤を散布する
灰色かび病は、多湿の環境で発生しやすくなります。日当たりや風通しのよい場所で育てることで予防しましょう。
また、殺菌剤を定期的に散布することも予防に有効です。
アブラムシ
カラーにアブラムシが発生すると、次のような状態が見られます。
- 新芽や葉裏に発生して汁液を吸う
- 葉がモザイク状になる
- 葉が縮れたり、全体が萎れたりする
- 葉や茎がベタベタする
- アブラムシの糞で、すす病を誘発する
アブラムシの発生時は、次のような対策を行います。
- 手や粘着テープなどで取り除く
- 水で洗い流す
- ベニカXファインスプレーなどの駆除剤を散布する
アブラムシは、日当たりと風通しのよい場所で育てることで予防できます。また、オルトランなどの駆除剤を土にまき、予防することも可能です。
アザミウマ
カラーにアザミウマが発生すると、次のような状態が見られます。
- 葉にカスリ状の白や褐色の斑点ができる
- 新芽が委縮したり奇形になったりする
- 花の色がカスリ状に抜けたり、シミや褐変ができたりする
- 花が正常に咲かなかったり、開花後すぐに枯れてしまったりする
アザミウマの発生時は、次のような対策を行います。
- 被害にあった部分を摘み取り、処分する
- 青色や黄色の粘着トラップで捕獲する
- GFオルトラン粒剤や水和剤などの薬剤で駆除する
また、被害を受けないように、次のような防除対策を行うのも有効です。
- 定期的に薬剤を散布して予防する
- 赤色の防虫ネットを張って飛来を防ぐ
- 光の乱反射を嫌うため、シルバーマルチを敷く
- 畝面にマルチを敷き、幼虫が潜むのを防ぐ
特に、5~9月は発生しやすい時期なので、カラーをよく観察して、発見したらすぐに対処しましょう。
ハモグリバエ
カラーにハモグリバエが発生すると、次のような状態が見られます。
- 食害すると葉に白い筋ができる
- 食害が進むと葉全体が枯死する
- 葉の光合成が阻害されるため生育が悪くなる
- 症状がひどいと落葉する
ハモグリバエの発生時は、次のような対策を行います。
- 幼虫を見つけたら、手やピンセットなどで潰す
- 薬剤を散布して駆除する
- 被害のあった葉は、摘み取って処分する
ハモグリバエは雑草の周りに発生しやすいため、カラーの周りの雑草を除去しておくことも大切です。また、オルトランを土壌にまいておくことで予防できます。
網目の細かい防虫ネットを張ったり、黄色の粘着トラップを仕掛けたりするのも有効です。
カラーの育て方に関するよくある質問

最後に、カラーの育て方に関するよくある質問を2つ紹介します。
- カラーの花が終わったらどうしたらいい?
- 球根は植えっぱなしのでも大丈夫?
カラーの花が終わったらどうしたらいい?
カラーの花が終わったら、花茎の根元からカットしましょう。
枯れた花を残したままにしておくと、次の花に栄養が行かなかったり、病害虫の原因になったりします。
きれいに咲いているときに花茎の根元から切り、花瓶に生けて切り花として楽しむのもおすすめです。
また、花が終わっても、葉は黄色くなるまで残しておきましょう。
光合成をして栄養を蓄えることで球根が太り、翌年も立派な花を咲かせやすくなるからです。
球根は植えっぱなしでも大丈夫?
鉢植えのカラーの球根は、植えっぱなしだと根詰まりしてしまうため、2~3年に1回くらいのペースで植え替えるのがおすすめです。
畑地性のカラーの植え替えは、球根が発芽する前の3~4月に行いましょう。
植え替え時に、分球(球根を切り分けること)を行うと、株を増やせます。
湿地性のカラーは地上部が枯れないので、掘り返したら株分けを行って植え替えれば大丈夫です。
まとめ
カラーは、スラリと伸びた茎の先に、くるりと巻いたようなスタイリッシュな花を咲かせます。
カラーには湿った土を好む湿地性と、水はけのよい土を好む畑地性とがあるので、育てるときはどちらの種類か確認することが大切です。
今回は、湿地性と畑地性のカラーそれぞれの育て方や注意点を解説してきました。
管理に少し注意が必要ですが、咲いた花は切り花としても楽しめるので、ぜひ挑戦してみましょう。
カラー人気の品種や価格相場は、下記の特集ページを参考にしてみてください。
[https://andplants.jp/collections/flowers_callalily]