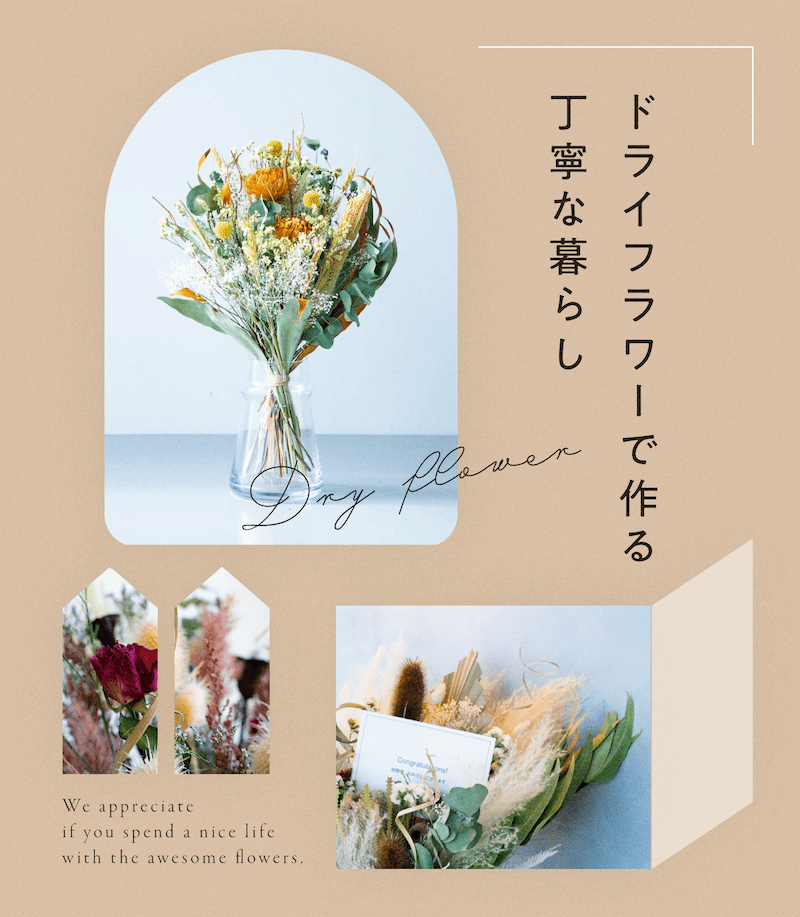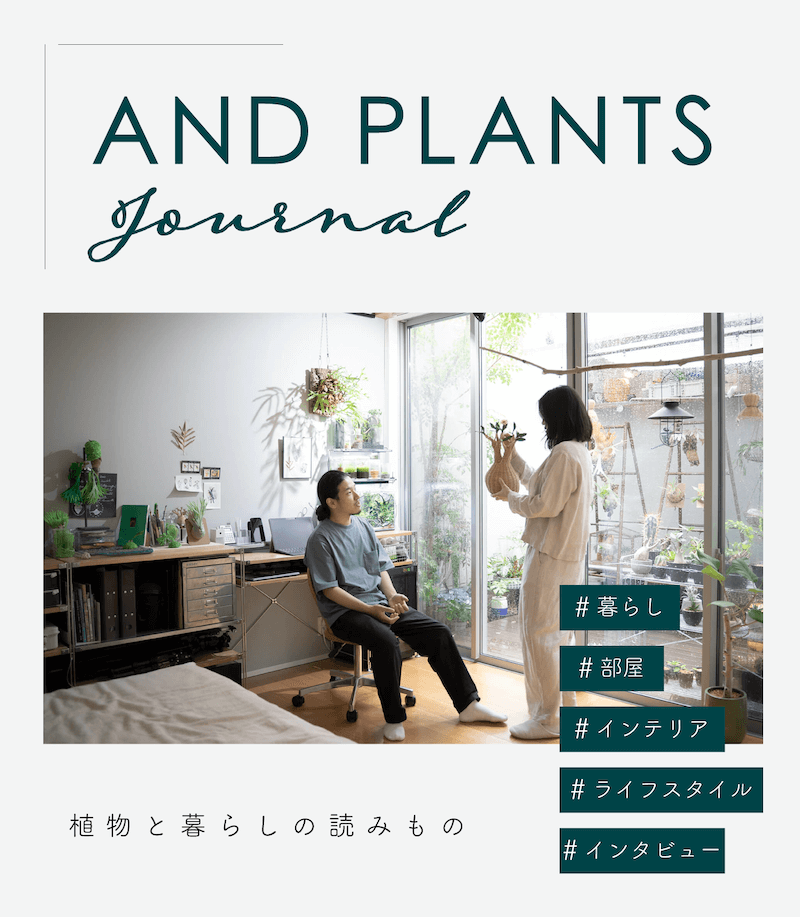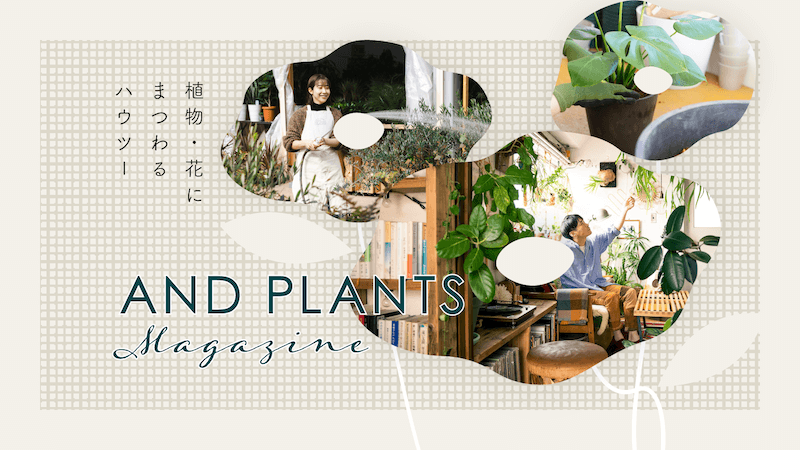お仏壇やお墓にお供えする仏花。
お仏壇があるご家庭も減っているため、仏花を自分で用意や購入をしたことがない若い世代も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、仏花の定義をはじめ、仏花に使うお花の種類や選び方を解説していきます。
初めて仏花を用意する人や、仏花に使うお花について詳しく知りたい人向けにお花の種類をまとめてみました。
仏花の基本から知りたい人は、参考にしてみてくださいね。
[https://andplants.jp/collections/offering-flower]仏花はお仏壇やお墓に供えるお花
仏花とは、お仏壇やお墓にお供えするお花のことです。
一般的には仏教に関するお花で、仏様やご先祖様、故人にお供えします。地域や宗派によって細かい風習の違いはありますが、仏花の意味合いや位置付けは概ね似ています。
まずは以下の2つから、仏花の定義を見てみましょう。
- 「仏花」の読み方と意味
- 仏花・墓花・供花の違い
一様に「仏花」と言っても、人によって指すものが異なることがあります。地域によってお店の表示名も違いがあるため、混乱する人も多いかもしれません。
仏花と墓花、供花などの違いも含めて、解説していきます。
「仏花」の読み方と意味
一般的に、仏花は「ぶっか」と読みます。「ぶつばな」や「ほとけばな」と呼ぶ人もいるようです。
仏花には、広義と狭義の意味合いがあります。
- 広義|お仏壇やお墓など、仏様にお供えするお花全般
- 狭義|お仏壇にお供えする一対のお花
広義では、仏教に関するお供え花全般を指します。お墓のお花やお地蔵さんのお花、アレンジメントのお供え花なども含まれます。
狭義の仏花は、お仏壇の花立てに入れる、ひし形にくくった花束です。一対で飾る人が多いので、左右対称に作った2束のセットで売られています。
仏花・墓花・供花の違い
仏事に関するお花では、仏花のほかにも「墓花(はかばな・ぼっか)」や「供花(くげ・きょうか)」の名称を聞くことがあります。
3つの違いを表にまとめてみました。
- 仏花|お仏壇にお供えする
- 墓花|お墓にお供えする
- 供花|お通夜や告別式などの葬儀に使用する
墓花とは、お墓の両サイドに設けられた花立てに入れる、一対のお花を指します。仏花と同じように基本的には2束のセットで売られています。
供花とは、葬儀の際に置かれるアレンジメントやスタンド花です。
四十九日や命日などに贈るお花は、供花またはお供え花と呼びます。お悔やみのお花とも言われ、主に亡くなった故人やご遺族に向けて贈るお花です。
なお仏花・墓花・供花は、地域や人によって呼び方が混同していることがあります。購入や注文する時は用途をしっかり伝え、トラブルがないように気をつけましょう。
仏花や墓花に入れるお花の種類の選び方

ここからは、お仏壇に供える仏花や、お墓に供える墓花のお花の選び方は、以下の通りです。
- 長持ちするお花
- 故人が好きなお花
- 季節のお花
仏教においてお花をお供えする意味は、3つあります。
1つ目は、ご先祖様や故人への感謝の気持ちを表すためです。
2つ目は、やがて枯れゆく生花の姿から、生きている私たちが命の尊さや儚さを感じるためと考えられています。厳しい環境でもお花を咲かせる姿に、仏教の悟りの教えを重ねているとも言われます。
3つ目は、お参りする私たちが優しい気持ちになり、故人への悲しみを癒すためです。
宗派によって意味合いが微妙に異なるので、お墓参りや法事の際にお坊さんに改めて聞いてみるのもいいですね。それでは、お花をお供えする意味も踏まえて、選び方を詳しく解説します。
①長持ちするお花
仏花や墓花に使うお花の種類に厳密な決まりはありませんが、あまりにも早くしおれてしまうお花はふさわしくないとされています。
お墓やお仏壇を常にきれいに管理するためにも、長持ちするお花を選びましょう。
花びらがすぐに散ってしまうようなお花は縁起がよくないだけでなく、お墓やお仏壇を汚す原因になってしまいます。特に贈答用には、管理する人の手間が増えないお花選びが大切です。
②故人が好きなお花
故人を偲ぶ際には、故人が好きだったお花を入れるといいでしょう。
仏花や墓花のお花の種類は、これでなければいけないといった明確なルールはありません。故人やご先祖様を想って選んだお花であれば、基本はどんなお花でも問題はないとされています。
ただし墓花を選ぶ時は、周囲への配慮が必要です。花びらが落ちやすかったり花粉が多かったりするお花はお墓や通路を汚す可能性があります。お墓参りを済ませたらお花は持ち帰ることを推奨している霊園もあります。
③季節のお花
季節のお花は、自然の移ろいや風情を感じることができます。
もともとお供えのお花は、自分で育てた植物や山で採ってきた季節のお花が使われてきました。現在でも、自宅の畑やお庭で仏花や墓花用のお花を育てている方もいらっしゃいます。
お店で売られるお供え花も、季節のお花が取り入れられていることが多いです。
お庭に咲いた季節のお花をお供えするのもいいですね。ご先祖様や故人と一緒に季節を感じてみてください。
仏花に適したお花の種類

一般的に仏花によく使われるお花の種類は、次の通りです。
- キク
- ユリ
- カーネーション
- スターチス
- デンファレ
- 季節のお花
- お盆やお正月には特別なお花を
お仏壇に供える仏花には、どんなお花を入れてもいいと言われています。
上記のお花でなくてはいけない決まりはありませんが、長持ちしてメンテナンスしやすいことからよく選ばれるお花です。
それぞれの意味や特徴を見ていきましょう。
[https://andplants.jp/collections/offering-flower]関連記事:お彼岸のお花|お墓や仏壇に供えるお花の選び方と、贈る時のマナー
キク
キクは安定して生産できることから、現代では一年中手に入るお花です。
非常によく長持ちするため、日々のお供えのお花として重用されてきました。また、キクのすっきりとした香りは邪気を払う効果があるとも考えられていたようです。
大輪からスプレータイプまでさまざまな品種があり、場所や用途に合わせて飾りやすいのも特徴です。西洋キクも人気で、現代建築やモダンな仏壇にも合います。
キクを切り戻す時は、ハサミではなく茎を手で折るようにすると、よく水を吸い上げて長持ちします。
ユリ
上品な印象のユリは、存在感がある上に長持ちするため、仏花にはぴったりです。ユリの凛とした姿が、故人の生前の姿を思い起こさせるとも言われます。
しかし香りが強いカサブランカは、お線香の香りの妨げになってしまうためお供えにはあまり向いていません。スカシユリやテッポウユリなど香りが少ない種類を選びましょう。
またユリの花粉は、お部屋や衣服に付着するとなかなか取れないことがあります。あらかじめ花粉を取り除いてからお供えしてください。
カーネーション
花びらが散りにくく長持ちするカーネーションも、仏花にふさわしいお花です。
カーネーションは母への感謝の象徴でもあることから、家族を想って選ぶ人も多いようです。
1本の茎にお花がひとつのスタンダードタイプと、枝分かれして小さなお花が咲くスプレータイプの2種類があります。
花色も豊富で、好みの種類を見つけやすいでしょう。仏花らしいはっきりした色合いから優しいパステルカラーまで、故人のイメージや日々の気分に合ったカーネーションをお供えしてみてください。
スターチス
お花がいつまでも色褪せないスターチス。ほかのお花は枯れてしまってもスターチスだけは残ることがあるほど、よく長持ちするお花です。
紫やピンク、クリーム色など、仏花によく使われる花色が揃っています。
ドライフラワーにされることが多い大きめのお花のスターチスのほかに、宿根スターチスと呼ばれる細かいスプレータイプの品種もあります。
デンファレ
デンファレは、肉厚な花弁が気品のあるランの仲間です。
茎が細くてまとめやすく、縦のラインに並ぶお花が合わせやすいことから、仏花によく使われます。ランの仲間は花持ちがよく、花びらが散りにくい特徴があります。
白や明るい紫色の品種があり、どちらも仏花に使いやすい色合いです。
季節のお花
仏花には、季節のお花も入れられます。季節ごとに、仏花に向くお花をまとめてみました。
- 春|アイリス、キンセンカ、マーガレット
- 夏|ジニア(ヒャクニチソウ)、グラジオラス、ヒマワリ
- 秋|リンドウ、ケイトウ、ススキ
- 冬|ストック、ネリネ、シンビジューム
お花屋さんやスーパーの仏花コーナーには、定番の仏花のほかに季節のお花も販売されていることが多いです。いつもの仏花に1、2本足すだけでも、季節感が出て新鮮な印象になります。
お正月やお盆には特別なお花を
お正月用の仏花や、お盆用の仏花があります。
使うお花は地域によって差がありますが、いつもより少し豪華な仏花を用意するおうちが多いようです。
お正月には、マツやウメ、ナンテンなどを入れます。お盆にはハスやホオズキ、ミソハギを入れるのが一般的です。なお初盆の仏花は、白や淡い紫などの優しい色合いでまとめましょう。
仏花に入れる葉っぱの種類

仏花や墓花と一緒に、葉っぱだけが束ねられた花束が売られているのを見たことがあるでしょうか。
東海より南では、仏花や墓花にはお花に葉っぱを添える風習があります。関東と北陸より北の地域では仏花には葉っぱを入れないので、風習の違いに戸惑う人も多いかもしれません。
さらに混乱することに、地域や宗派によって葉っぱの呼び方や、そもそも植物の種類が違います。初めて仏花を用意する人にとっては少し難しいところです。
そこで、仏花に入れる葉っぱの種類や呼び方をまとめてみました。
- ヒサカキ
- ヒサカキは地域によって呼び方が違う
- シキミ(シキビ)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ヒサカキ
ヒサカキとは、モッコク科ヒサカキ属の植物です。
神事に使われたり神棚に飾られたりするサカキに似ており、サカキよりも葉が小ぶりなために「姫榊(ヒサカキ)」と名付けられました。サカキはモッコク科サカキ属なので、サカキとヒサカキとは別の植物です。
しかし関東から北では、ヒサカキを「サカキ」と呼んで神棚に飾ります。サカキは関東以北では自生していないため、ヒサカキを使っていたことが理由です。そして仏花や墓花はお花のみで、葉っぱは入れません。
一方で東海以南では、神事にはサカキを使い、仏事にはヒサカキを使います。宗派や地域によって違いはありますが、仏花や墓花にはお花の後ろにヒサカキを添えます。
地域ごとの風習の違いは以下の通りです。
- 関東・北陸より北|神棚にはヒサカキを使い、仏花には葉っぱは入れない
- 東海より南|神棚にはサカキを使い、仏花にはヒサカキを入れる
しかし宗派によって異なる場合もあります。ヒサカキのほかに、高野槙を入れる風習もあるようです。
分からない場合は、お坊さんに聞いたり、お花屋さんに相談したりして作ってもらうといいでしょう。
ヒサカキは地域によって呼び方が違う
仏花や墓花に添えるヒサカキは、呼び方が地域によって異なります。地域ごとの主な呼び方を以下にまとめました。
| 地域 | 呼び方 |
| 関東・北陸以北 | 使わない |
| 東海 | チラ |
| 近畿 | 下草、ビシャコ |
| 中国・四国 | ササキ、シャシャキ |
| 九州 | シバ |
なお同じ県の中でも、呼び方が変わることがあります。
しかし近年は植物の分類化や大型スーパーの普及により、地域特有の呼称や使い分けが薄れつつあるようです。
シキミ(シキビ)

地域や宗派によっては、ヒサカキではなくシキミを仏花に使うことがあります。
シキミ・シキビは、漢字で「樒」「梻」と書くマツブサ科シキミ属の植物です。ヒサカキよりもさらに葉が小ぶりで、ひとつの節から複数の葉が出ているのが特徴です。
シキミは仏事で使われる葉っぱで、葬儀の儀式や装飾に使われます。一般的に神事にはあまり使用されません。
特に近畿地方で、お墓にシキミのみをお供えする地域や宗派が多く見られるようです。また浄土真宗や日蓮正宗などは、お仏壇に供える仏花にもシキミを使います。
なおシキミには有毒成分が含まれているため、ペットや小さなお子様のいるおうちでは扱いに注意しましょう。
仏花にふさわしくないお花の種類

基本的にはどんなお花を使ってもいいとされる仏花ですが、ふさわしくないと言われるお花もあります。
以下のようなお花は、仏花には避けたほうがいいでしょう。
- 花びらが散りやすいお花
- 香りの強いお花
- トゲのあるお花
- 毒のあるお花
- ツルがあるお花
- 不吉なイメージを連想させるお花
- 食べられるお花
具体的なお花の種類を含めて、ひとつずつ詳しく解説していきます。
花びらが散りやすいお花
サクラやコデマリ、ハギ、キンモクセイなどの花びらが散りやすいお花は、お仏壇やお部屋を汚してしまう可能性があります。
実家や親戚のおうちなど、人に贈る時には気をつけましょう。
また、散った花びらが雨に濡れてお墓や通路に付着すると取れにくいことがあります。墓花に花びらが切りやすいお花はなるべく避けたほうがいいかもしれません。
香りの強いお花
香りの強いお花は、お線香の香りの妨げになると言われます。カサブランカやキンモクセイ、クチナシが代表的です。
強い香りが苦手な方もいるので、贈答用や墓花には入れないようにしましょう。
トゲのあるお花
トゲには殺生のイメージがあるため、仏花には向かないと言われます。バラやアザミ、ボケが挙げられます。
しかしバラを好む人は多く、故人を想ってお供えすることも少なくありません。トゲのあるお花を入れる時は、できるだけトゲを取り除いてお供えしましょう。
毒のあるお花
毒は殺生のイメージがあり、お供えにはふさわしくないと考えられています。
しかし毒のあるお花は、スイセンやスズラン、ヒガンバナ、チューリップ、シャクナゲと意外にたくさんあります。
植物の毒には、動物や虫を寄せ付けない魔除けの効果があるとも考えられてきました。スイセンをお正月の仏花に入れる地域もあり、仏花に添えるシキミも有毒植物です。
もしお供えする時は、扱いには気をつけましょう。中には毒が花瓶の水に溶け出す種類もあるため、ペットや小さなお子さんの手に触れないように注意してください。
ツルがあるお花
ツルには絡みつくイメージがあり、ツルが「成仏の妨げになる」「生きている人を引きずり込む」と言われます。
アサガオやクレマチス、サマースイートピーのようなツルのある植物は避けたほうがいいでしょう。リキュウソウやアイビーといったツル性の葉ものも、あまり適していません。
不吉なイメージを連想させるお花
具体的には、お花の首が落ちるツバキや、すぐにお花がしぼんでしまうムクゲやハイビスカスのような一日花が挙げられます。
不吉なイメージを連想させるだけでなく、お仏壇を汚す可能性があります。また、あまりに短命なお花はメンテナンスも大変です。
食べられるお花
アワやムギ、稲穂のような食用にもなる植物をお供えするのは、ふさわしくないと考えられています。
虫や動物が寄ってくる可能性もあるため、特に墓花に食べられるお花は避けましょう。
ほかにも、オクラやミニパイナップル、アスパラの葉などが切り花でも出回っています。たとえ故人が好きだった食べ物でも仏花に入れるのは避け、お供え物としてお供えするのがおすすめです。
仏花の基本のかたち

地域や宗派によって違いはありますが、仏花を飾る際の基本のかたちは以下の通りです。
- 一対で飾る
- お花の本数は奇数にする
- ひし形に整える
- 色は白・黄・紫・赤・ピンク
具体的に見ていきましょう。
一対で飾る
仏花は、一対で飾るのが基本です。
お仏壇の両サイドにひとつずつ、左右対称に組まれたお花を置きます。お墓にお供えする墓花も同様に、一対用意します。
ただし、必ずしも一対でなくてはいけない決まりはありません。
近年のコンパクトなお仏壇では、花立てがひとつの仕様も多く見られます。お仏壇やお墓の様式に合わせた数を用意しましょう。
お花の本数は奇数にする
仏教では、奇数は縁起が良いと考えられています。
古代の中国において奇数は神聖な数字であり、五行陰陽説では陽と考えられていたことが由来です。また、偶数本より奇数本のほうがバランスよく美しくお花を生けられるといった考えもあります。
仏花に入れるお花は3本、5本、7本を基本にします。豪華にする時は、9本や11本でもいいでしょう。
ひし形に整える
仏花や墓花は、全体がひし形になるように組まれています。
上がやや細く、下にボリュームのあるひし形になるように整えましょう。中心に1本長いお花を置いて、左右のバランスを見ながらお花の位置や長さを調節します。
東海以南では、ヒサカキを土台にして組む方法が基本です。ヒサカキは、仏様の後光を表していると言われています。
色は白・黄・紫・赤・ピンク
仏花や墓花は、白・黄・紫・赤・ピンクを使って3色または5色にまとめられます。
- 3色|白・黄・紫
- 5色|白・黄・紫・赤・ピンク
視覚的に、3色や5色でまとめるとバランスがいいと言われています。
上から「薄い色→濃い色」となるように配色するのが基本です。一番上に白や黄色のお花に入れて、下を赤や紫のような濃い色で締めます。
なお、色数に厳密な決まりはないと言われ、白・黄・紫・赤の4色で作られることもあるようです。宗派や地域によっても違いがあります。
はっきりした色合いが好まれますが、故人の好きな色で用意してもかまいません。 ただし四十九日までは、白を基調にした仏花を用意しましょう。
仏花の作り方

仏花や墓花を作る手順は、次の通りです。
- 花材を3本〜7本程度用意する
- 不要な葉や枝を整理する
- ひし形に組む
- 茎が広がらないように留める
コツを掴めば、仏花を自分で作るのは簡単です。
好きなお花や、造花で自分で作る人も増えているようです。ぜひ作ってみてくださいね。
①花材を3本〜7本程度用意する
お花を3本~7本ずつ用意します。初心者は、茎が滑りにくくて束ねやすいキクやスターチスがおすすめです。
一対で作る時のお花の例を以下に挙げてみました。
- 輪菊:2本
- 小菊:4本
- カーネーション:2本
- スターチス:2本
葉っぱを使う地域は、上記にヒサカキを用意しましょう。お花屋さんやスーパー、ホームセンターに、ヒサカキの枝を5〜6本まとめてひし形に整えたものが販売されています。一対作る時には、2束用意してください。
②不要な葉や枝を整理する
お花が揃ったら、不要な葉や枝を整理します。
まずは水に浸かる部分の葉っぱを取り除きましょう。切り口に近いところで枝分かれしていたら、小枝に分けます。花立てに入れる茎をすっきりさせておくと、飾った時に綺麗です。
葉が密集しすぎているとカビの原因にもなるので、少し透かします。しかし葉を取り除きすぎると寂しい印象になります。組みながらバランスを見て、気になるところを取っていくといいでしょう。
③ひし形に組む
左右対称にひし形になるように組んでいきます。以下の手順のように重ねてみましょう。
- 輪菊(白)を真ん中に置く
- 輪菊の下に小菊(黄色)を1本置く
- 小菊(黄色)の右斜め下に小菊(ピンク)を1本置く
- 小菊(ピンク)の下、中央寄りにカーネーション(赤)を置く
- カーネーション(赤)を挟むように両脇にスターチス(紫)を添える
茎は少し左右にずらしながら重ねていくと、まとめる時にお花がずれにくくなります。
一対作る際は、手順③の小菊(ピンク)を左斜め下に置いて、飾る際に左右対称になるようにすると見た目がよくなります。
④茎が広がらないように留める
最後に花立ての長さに合わせて、茎を切ります。
キクなどの太くてしっかりした茎に輪ゴムをひっかけ、輪ゴムを上にずらします。そして茎の切り口のほうに向かって、ずらしながらぐるぐると巻いていきましょう。下のほうまできたら、もう一度太い茎にひっかけてまとめて出来上がりです。
輪ゴムをきつく巻きすぎると、茎が潰れて水を吸収しづらくなってしまいます。優しく、3周くらい巻くのがちょうどいいでしょう。
仏花をきっちり組む地域もあれば、茎の長さとバランスを調整してラフに入れる地域もあります。自分のやりやすい組み方を見つけて、作ってみてくださいね。
仏花の種類に関するよくある質問

ここからは、仏花の種類に関するよくある質問をまとめてみました。
- 造花やプリザーブドフラワーの仏花を使ってもいい?
- 仏花と墓花は同じものを用意してもいい?
- 庭で栽培しているお花を入れてもいい?
仏花を用意する際の参考にしてみてください。
では順番に見ていきましょう。
造花やプリザーブドフラワーの仏花を使ってもいい?
仏花や墓花には、造花やプリザーブドフラワーを使ってもいいと言われています。
造花やプリザーブドフラワーの仏花なら、いつも色鮮やかに保つことができます。花立ての水が汚れて不衛生になったり、枯れたお花でお仏壇を汚したりする心配もありません。また、お花を頻繁に替えなくていいため、経済的です。
色合いも自由に選べて、現代の住宅やお仏壇の様式にも合うでしょう。
ただしお花をお供えする行為には、「枯れゆく姿に諸行無常を感じる修行」という考えが含まれています。季節のお花を入れることで、時の移ろいを感じることもできます。
時には生花もお供えしながら、ライフスタイルに合わせて選んでみてくださいね。 また、造花やプリザーブドフラワーの仏花を人に贈る時は、相手の考えを尊重して選びましょう。
仏花と墓花は同じものを用意してもいい?
仏花と墓花は、同じお花の種類で用意してもかまいません。
しかし、茎の長さには気をつけましょう。一般的に、お墓の花立てのほうが大きく長い傾向があります。
墓花は周囲に配慮したお花選びを心掛けてください。特に香りが強かったり花びらが散ったり、食べられたりするお花は周囲の迷惑になる可能性があります。故人の好きなお花を使いたい時は、自宅に飾る仏花に入れるのがおすすめです。
なお、お墓から持ち帰ったお花をお仏壇に供える行為はよくないと言われています。お花の使いまわしは、仏様に失礼だとする考え方があるためです。
仏花や墓花の様式は、宗派や地域によっても違いがあります。
近年の大型スーパーでは仏花や墓花がまとめて販売されていて、どれを選べばいいか分からない人も多いかもしれません。迷った時は地域のお花屋さんで、墓花と仏花をそれぞれ作ってもらうといいでしょう。
庭で栽培しているお花を入れてもいい?
仏花や墓花に使うお花は、お庭で栽培しているお花を入れても問題ありません。季節のお花をご先祖さまや故人と一緒に楽しむつもりで、お供えしてみてはいかがでしょうか。
また、自宅で仏花用のお花を育てれば、日々のお花の交換も経済的です。育てる楽しみや、四季折々のお花を楽しめるメリットもあります。
特にお盆やお正月、お彼岸は、市販の仏花や墓花の値段が上がるため、自宅で育てたお花を使う人も少なくありません。ケイトウやジニア(ヒャクニチソウ)、ホオズキ、グラジオラスなどは栽培も簡単で、初心者にもおすすめです。
まとめ
お仏壇やお墓にお供えする仏花について、ご紹介してきました。
仏花や墓花は、地域や宗派によって曖昧な部分も多くあります。
特に地域性の違いは明文化されていないことが多いため、地元を離れると混乱する人は多いでしょう。日々お供えしている方でも改めて仏花のルールについて聞かれると、はっきり答えられないといったケースもよくあります。
初めて用意する時は、自身の宗派のお坊さんに聞いてみたり、昔ながらのお花屋さんに作ってもらったりすると分かりやすいかもしれません。
しかし仏壇やお墓にお花を飾る際は、お供えする気持ちが大切です。ご先祖さまに感謝して故人を想いながら、美しいお花をお供えしてみてくださいね。
[https://andplants.jp/collections/offering-flower]