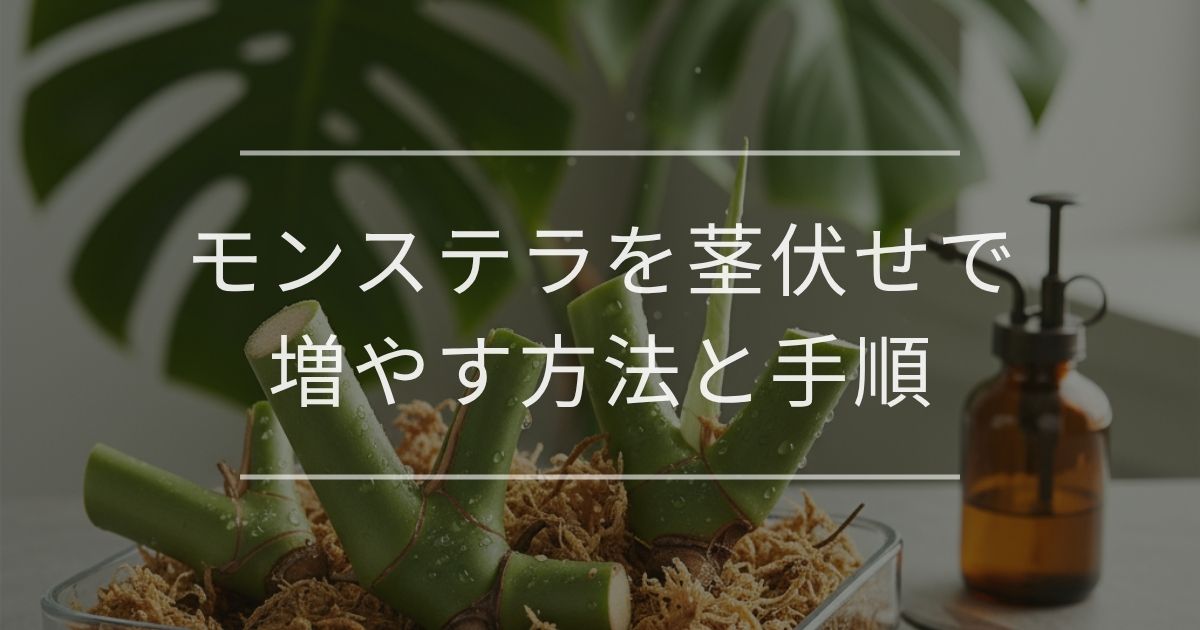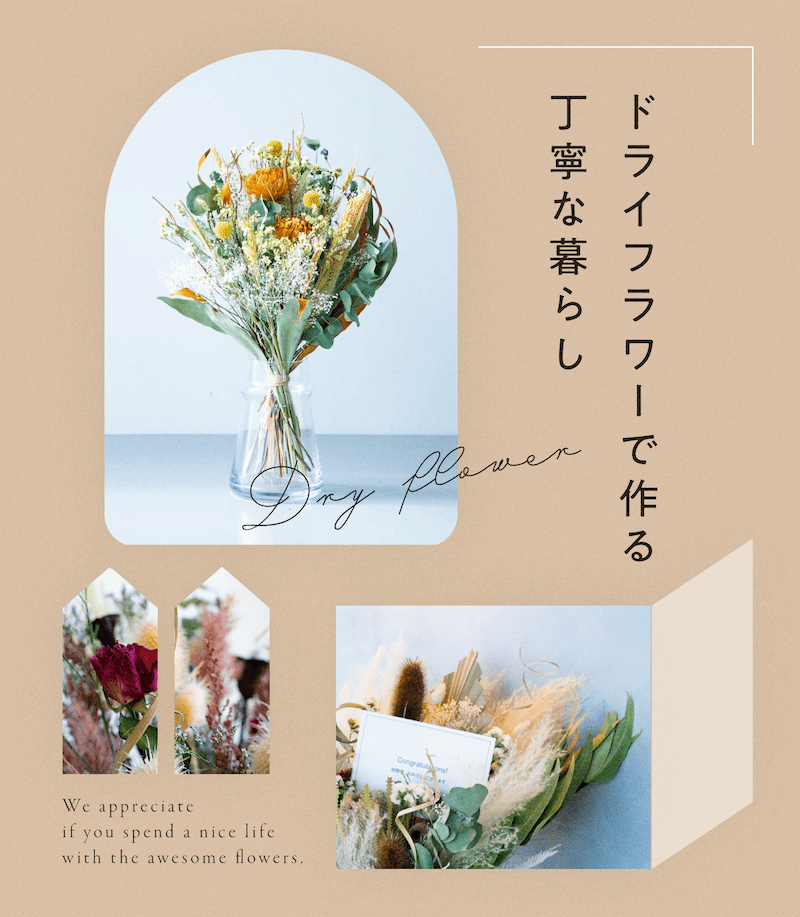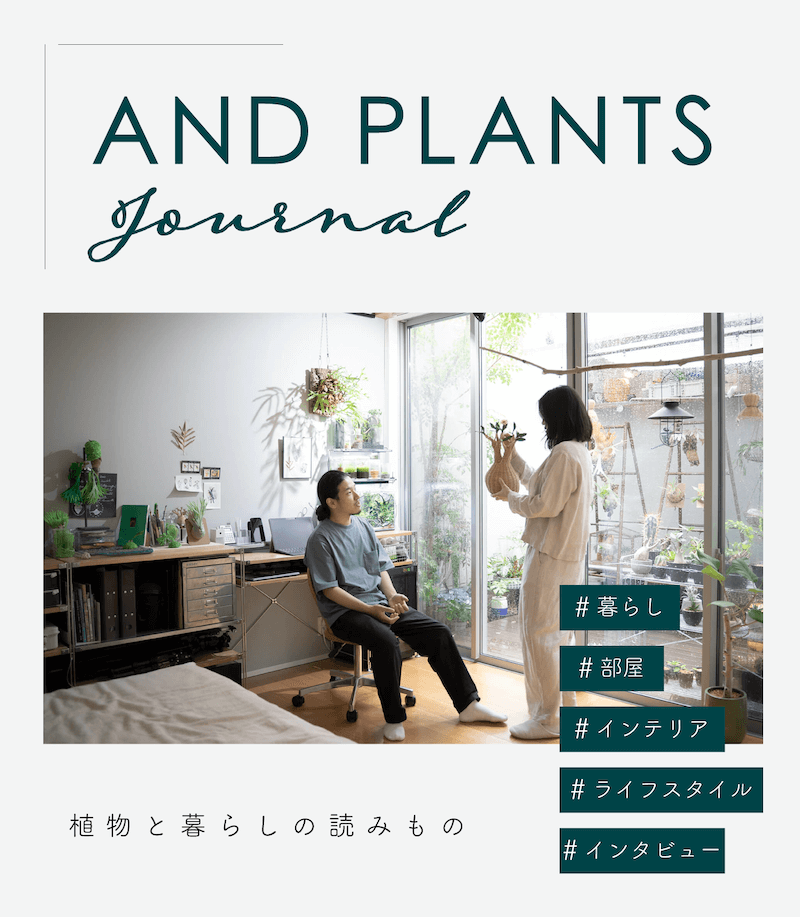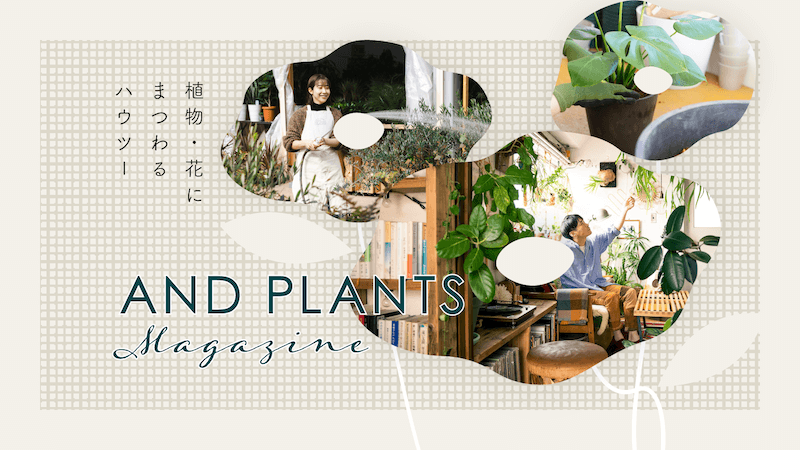ご先祖様や故人に感謝の気持ちを表す仏壇のお花。
しかし、いざ自分がお供えをするとなると、「どこにどんなお花を飾ればいいんだっけ」と分からなくなることもあるかもしれません。
そこで今回は、仏壇のお花の飾り方について解説します。
基本の飾り方や綺麗に生けるポイント、長持ちさせる管理方法のコツもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
AND PLANTSでは、お供えのお花をご用意しています。
故人を偲ぶ気持ちに合うよう、優しい印象で仕上げました。自宅用はもちろん、法事やお彼岸の贈り物にもふさわしいでしょう。
自宅に届くので、買いに行く時間がない時にもおすすめです。ぜひ利用してみてください。
[https://andplants.jp/collections/offering-flower]仏壇のお花の飾り方
まずは、仏壇のお花の基本的な飾り方を見ていきましょう。一般的な作法は、次の4つです。
- 花立てにお花を生ける
- 仏壇の下段に置く
- 花は自分の方に向けて飾る
- 浄土真宗は上段にシキミを飾る
仏壇のお花を購入できる場所は、お花屋さんやスーパー、ホームセンターなどです。
美しく形を整えた仏花(ぶっか)や、仏壇にふさわしいお花を数本セットにした組花(くみばな)が販売されています。
仏花を購入できる場所や値段については、仏花の値段相場の記事に詳しくまとめています。購入場所によって値段相場も異なりますので、お店選びの参考にしてみてくださいね。
では、基本の飾り方を順番に解説していきます。
①花立てにお花を生ける
仏壇のお花は、花立てに生けましょう。
花立ての種類は、仏壇の種類や宗派によっても違いがあります。
浄土真宗では、本願寺派(西)はこげ茶色または黒色、真宗大谷派(東)は金色の花立てを使用します。分からない場合は、檀家や仏具屋さんに相談してみるといいでしょう。
宗派で決まりがない場合は、仏壇に合わせて好きなものを選んでかまいません。
重厚な印象の伝統型デザインのほか、絵柄入りやシンプルなタイプなど種類豊富に展開されています。素材は真鍮・陶器・銅を中心に、手入れしやすいステンレスやアルミなども人気です。
仏具店やホームセンター、100円ショップでも購入できます。香炉や火立とセットで買うと統一感が出るでしょう。
お花の数は奇数本にする
仏壇のお花は、3本・5本・7本など奇数の本数で生けるのが基本です。
奇数は、古くから神聖な数字と考えられてきました。また、奇数本のほうがバランスよく生けられるといった考えもあります。
一般的には、1つの花立てにつき、5本もしくは7本が適当です。
その際は、お花を入れすぎないように気をつけてください。花立てにお水が十分に入るだけの余裕を残して、お花の本数を決めるといいでしょう。
花色は5色にまとめる
一般的に、仏壇のお花は白・黄色・赤・紫・ピンクの5色で生けます。
しかし、厳密なルールがあるわけではありません。地域や購入するお店によっては3色や4色で作られていることもあります。
上から薄い色→濃い色のグラデーションになる組み合わせが基本です。足元に濃い色を入れることによって、全体が引き締まって美しく見えます。
ただし、四十九日までは白色を基調にした仏花をお供えします。白色のみ、もしくは淡い色合いを使って3色程度にまとめましょう。
②仏壇の下段に置く
仏壇のお花を飾る位置は、仏壇の一番下の段です。香炉や火立、りんなどと一緒に花立てを置いてください。
仏壇の中に置くスペースがない場合は、仏壇の前に台や机を設置して、香炉や火立てと一緒に置きます。
近年はコンパクトな仏壇が増えており、従来通りに置けない場合も多く見られます。仏具屋さんや檀家に相談しながら、可能な範囲で置き方を再現するといいでしょう。
また、仏具の種類によっても、花立ての数や飾り方が異なります。代表的な三具足と五具足について、次に詳しく解説します。
三具足|左側に花立て1つで置く
三具足(みつぐそく・さんぐそく)とは、香炉1つ・花立て1つ・火立1つのセットを指します。
「香」「灯明」「花」は仏様をお参りする際に欠かせないものです。そのため、香炉・花立て・火立は供養における重要な道具であり、基本の仏具といわれています。
中央に香炉、右側に火立てを置き、左側に花立てを1つずつ置きます。
日々のお供えは三具足でのお供えが一般的です。
五具足|香炉を中心に左右対称に花立てを置く
五具足(ごぐそく)とは、香炉1つ・花立て2つ・火立て2つのセットを指します。
中央に香炉、すぐ両脇に火立て一対、外側の両脇に花立てを一対飾ります。
三具足よりも丁寧なお供えで、華やかに見える形式です。
しかし、五具足を揃えるには、十分なスペースが必要です。お花も一対必要になるため、費用や管理も大変になってしまいます。そのため、普段は三具足でお供えして問題ないと言われています。
法要や行事など華やかにお供えしたい時には、五具足で飾るといいでしょう。
③花は自分の方に向けて飾る
お花は、お供えする自分の方に向けて飾りましょう。
「仏様や故人にお供えするのに、なぜこちら向きに飾るの?」と疑問に思う人もいるかもしれません。お花を自分の方に向けて飾るのには、次の2つの理由があると言われています。
- 仏壇を美しく彩るため
- お花から慈悲の心を受け取るため
お花をこちら向きに飾ることによって、仏壇が華やかに見えます。仏壇のお花は、浄土の美しさを表現する役割もあります。
さらに、いつか枯れゆくお花と向き合うことは、時の流れや変化を受け入れる修行でもあるそうです。お花は美しさと命の象徴であり、諸行無常の教えを示す「仏の慈悲」とされています。
お花の美しさがお供えする人の心を穏やかにし、優しさを感じさせてくれるでしょう。
④浄土真宗は上段にシキミを飾る
浄土真宗では、花立てのお花のほかに、上段の御本尊の近くにシキミ(シキビ)を飾ります。
強い香りや毒を持つシキミは古くから邪気を払う効果があると言われ、仏教では重要な意味を持つ植物です。シキミを挿した水は「香水」と言われ、浄土の世界に流れる清らかな水を表現していると言われます。
浄土真宗の仏壇には、シキミを生けるための華瓶(けびょう)と呼ばれる花立てに入れて飾ります。仏花を挿れる花立てとは別に用意しましょう。
ほかにも、仏壇に造花で作った常花(じょうか)を飾ることもあります。地域や宗派それぞれの風習があるため、分からない時は仏具店や檀家に確認してみるといいかもしれません。
仏壇のお花を綺麗に飾るポイント

次は、仏壇のお花の綺麗な飾り方を紹介します。
いざお花を買って花立てに生けてみると、意外と難しいものです。「お花がバラバラに見える」「うまくバランスが取れない」と難しく感じる人もいるかもしれません。
次の3つのポイントを意識してみると、生けやすくなります。
- お花の長さ|花立ての3倍を目安にする
- お花の形|全体がひし形になるように整える
- 葉の量|適度に減らしてすっきり見せる
仏壇のお花を生ける手順は、仏花の生け方の記事でも詳しく解説しています。用意する道具や細かな手順を知りたい人は、参考にしてみてください。
では、ひとつずつ見ていきましょう。
お花の長さ|花立ての3倍を目安にする
お花の長さは、花立ての高さの約3倍程度にするとバランスよく見えます。
お花が長すぎると間延びして見え、花立てごと倒れてしまうこともあります。また、まとまりにくく、ばらついた印象になってしまうでしょう。
逆に短くしすぎても、バランスが悪くなってしまいます。また、茎が短いとお花がすぐに開いてしまい、長持ちしにくくなるデメリットもあります。
高さ10cmの花立ての場合、お花は全体の長さが30cm程度になるように切るといいでしょう。
お花の形|全体がひし形になるように整える
仏壇のお花は、花立てから出ている部分がひし型になるように整えましょう。
仏花をひし型に整えるのは、神棚に供えるサカキの形を模していると言われています。また、ひし型はバランスのよい形で、見た目も美しく仕上がります。
まず、一番後ろのお花を一番高くしてみましょう。真ん中あたりのお花は左右に広がるように整え、足元に向かって締まるように組みます。
最後に茎を輪ゴムで留めると、バラバラにならず、まとまって見えます。
葉の量|適度に減らしてすっきり見せる

余分な葉を取り除くことで、見た目が引き締まってまとまりやすくなります。
特にキクは葉が多いので、葉を適量に整理することですっきりした印象になります。「なんだかモサモサして見える」と思った時は、葉の量を調節してみましょう。
葉を減らす際は、次の3つのポイントを意識してみてください。
- 他の葉よりも大きい葉
- 重なり合う葉
- 水に浸かる高さの葉
葉を減らすことは、見た目だけでなくお花の持ちにもつながります。
大きい葉は水分の蒸散量が多く、花瓶の水がすぐに減ったり、早くお花が開いてしまう原因になります。適量に減らしてあげることで、ゆっくり開花して長持ちしてくれるでしょう。
重なり合っている葉は、蒸れて腐りやすくなります。また、葉が水に浸かると腐ってしまい、水が汚れてしまいます。異臭や早く枯れてしまう原因にもなるので、取り除いてください。
仏壇のお花を長持ちさせる4つの管理方法

仏壇を綺麗に見せるには、お花の美しさを保つことが大切です。しかし、頻繁にお花を替えるのはコストがかかることもあるでしょう。
そこで、長持ちさせる4つの管理方法をご紹介します。
- 花立てを綺麗に洗う
- 毎日水替えをする
- お花の水揚げをする
- 延命剤や漂白剤を水に入れる
順番に見ていきましょう。
①花立てを綺麗に洗う
まずは、お花を生ける前に、花立てを綺麗に洗いましょう。
花立てが汚れていると雑菌が繁殖しやすくなり、水が汚れてしまいます。水の中に雑菌が繁殖すると、お花がうまく水を吸い上げられず、早く枯れる原因になります。
できれば、水を替える度に花立てを洗いましょう。基本は、台所用の中性洗剤で優しく洗います。
汚れがひどいときは、漂白剤につけ置きします。
ただし真鍮や鉄、銅などの金属製の花立ては、塩素系・酸素系いずれの漂白剤も使用は避けてください。酸で金属が溶けて、錆びたり穴が開いたりする可能性があります。
金属製の花立ては、中性洗剤でこまめに洗うのがおすすめです。
②毎日水替えをする
お花の持ちには、新鮮な水を保つことが重要です。毎日水を替えるだけで、お花の持ちが格段によくなります。
水を替えることで茎のぬめりが抑えられ、お花が効率的に吸水できるでしょう。
また、雑菌の繁殖が抑えられるためで、花立てを綺麗に保つこともできます。
特に18℃以上が続く暖かい時期は、毎日の水替えがおすすめです。冬は2日〜3日に1回でもよいでしょう。
毎日手を合わせる際に水替えをする習慣がつくといいかもしれません。
③お花の水揚げをする
水揚げとは、お花の切り口を切ることで断面を新しくして、水分の吸収をよくする方法です。
水揚げにはさまざまな方法があり、お花の種類によって適した方法が異なります。仏花によく使われるお花の水揚げをまとめてみました。
| お花の種類 | 適した水揚げの方法 |
| キク | 手で折る |
| カーネーション ユリ |
ハサミで斜めに切る |
| ガーベラ カラー |
ハサミで横にまっすぐ切る |
キクは、茎の繊維質が剥き出しになるように手で折ると、水をよく吸い上げます。
カーネーションやユリのように茎の中が詰まっているお花は、斜めに切りましょう。斜めに切ることで表面積が増え、吸水しやすくなる効果があります。
ガーベラやカラーのように茎の中が空洞になっている種類は、茎が潰れないようにまっすぐ横に切るのが基本です。
ハサミは切れ味のよいものを使い、切った後はすぐに新鮮な水に漬けてください。水の中で切る水切りを行うとより効果的です。
④延命剤や漂白剤を水に入れる
切り花延命剤や漂白剤を使う方法もおすすめです。
漂白剤は雑菌の繁殖を抑え、新鮮な水を保ちます。10cmの花立てに対して、1滴が目安です。入れすぎるとお花が枯れてしまうことがあるので、少量を心掛けましょう。
また、延命剤は雑菌を抑えるほかに、切り花に不足しがちな栄養成分も含まれています。綺麗なお花が長く楽しめておすすめです。
注意点として、漂白剤は金属の花立てには使用できません。延命剤の中にも漂白剤と同様に、金属を変質させる成分が含まれていることがあります。
延命剤や漂白剤を使う際は、製品の使用方法をよく読んでから試してみてください。
仏壇にふさわしいお花

仏壇に飾るお花の種類は、基本的には決まりはありません。
しかし、一般的にふさわしいとされるお花がいくつかあります。仏壇のお花にふさわしいと言われるお花は、主に次の種類です。
- キク
- カーネーション
- ユリ
- スターチス
- トルコキキョウ
- 季節のお花
- 故人が好きだったお花
上記のお花は、長持ちして花びらが散りにくいことから、仏壇のお供えによく使われます。
ユリは上品な印象と長持ちする性質から好まれますが、花粉が落ちると仏壇が汚れてしまいます。お供えする際には、花粉が開く前に取り除いておきましょう。
旬のお花で季節感を取り入れたり、故人を偲んで生前好きだったお花を入れたりするのもよいと言われています。
「お供えの花はキクじゃないとだめ」といったルールはありません。仏様やご先祖様への気持ちに合った、美しいと感じるお花をお供えしてみてください。
仏壇に避けるべきお花

仏壇のお花に厳密な決まりはありませんが、できれば避けた方がよいと言われるお花もあります。
一般的にタブーとされるお花は、次の種類です。
- 香りが強いお花(カサブランカ・ジンチョウゲなど)
- トゲのあるお花(バラ・アザミなど)
- 毒のあるお花(スイセン・スズランなど)
- つる性のお花(クレマチス・スイートピーなど)
- 食べられるお花(アワ・イネなど)
- 花びらが散りやすいお花(サクラ・コデマリなど)
お線香の香りをかき消すほどの強い香りを持つお花は、なるべく避けましょう。
トゲのあるお花・毒のあるお花は、殺生をイメージすることからお供えにはふさわしくないとされます。また、つる性のお花は、「絡みついて成仏の妨げになる」と連想されるそうです。
食べられるお花は虫が寄ってくるおそれがあります。花びらが散りやすいお花は仏壇が汚れる可能性もあるため、飾る際にはこまめに掃除しましょう。
しかし、仏壇にはふさわしくないと言われるバラやクレマチスなどは、好きな人が多いお花です。故人が好きだった場合、故人を偲ぶ気持ちがあればお供えしてかまわないでしょう。
気になる場合は、法要のように人が集まる時のみ避けるといいかもしれません。
仏壇のお花の飾り方についてよくある質問

基本の飾り方以外にも、「生花じゃないとだめ?」「お供えを続けるのは大変」などの悩みを持つ人もいるかもしれません。
そこでここからは、仏壇のお花の飾り方についてよくある質問をまとめてみました。
- 造花やプリザーブドフラワーを飾ってもいい?
- 仏花は常に飾らないとだめ?
参考にしてみてくださいね。
造花やプリザーブドフラワーを飾ってもいい?
仏花には「生きとし生けるものはすべて死ぬ」といった諸行無常の教えが込められているため、仏壇には生花をお供えするのが基本です。また、「仏様はお花の香りを召し上がる」とも言われ、生花の香りは大切な供物のひとつです。
しかし、生活様式が変化し、物価も高騰している現代では、生花でお供えし続けることが難しいこともあります。
そのため近年は、プリザーブドフラワーや造花をお供えしてもよいと言われています。
仏壇がいつも華やかになり、「お花の管理をしなければいけない」といった心の負担も軽減するでしょう。法要や命日など特別な日には生花をお供えし、日々のお供えには造花やプリザーブドフラワーを飾る方法もおすすめです。
ただし、造花やプリザーブドフラワーが推奨されていない宗派や地域もあります。家族や檀家と相談しながら、家庭に合った方法を見つけてみてください。
仏花は常に飾らないとだめ?
仏壇には、常にお花をお供えすることが基本です。
美しい季節の生花を飾ることは、仏様やご先祖様に敬意や日々の感謝を示し、故人の供養をする意味があります。また、仏壇を普段から綺麗に整えておくことで、身を清め、仏教の修行を積む意味もあると言われます。
しかし、大切なのは手を合わせる気持ちです。お花を飾ることで負担を感じてしまうのであれば、無理にお花を飾り続けなくてもいいかもしれません。
日々のお供えは、管理しやすい造花やプリザーブドフラワーや、枯れにくいシキミのみを飾る方法もあります。
普段は簡素に済ませ、月命日や法要などの大切な日には仏壇を綺麗に整える習慣をつけるといいでしょう。
仏様やご先祖様、故人への感謝を忘れず、できる範囲でお供えをしてみてください。
まとめ
仏壇のお花の飾り方は、地域や宗派によっても異なります。
おばあちゃんやおじいちゃんがしていた方法を受け継いだり、今のライフスタイルに合った方法を見つけたり、家庭ごとにふさわしい方法があるかもしれません。
仏壇はもともと、仏教の信仰のために家に本尊を祀る目的で広まった風習で、家の中の小さなお寺のようなものです。
家の中に手を合わせる場所があることで、ご先祖様や故人との繋がりを感じ、心の拠り所になります。また、仏教の教えに触れ、自分自身を見つめ直す機会を与えてくれるものでもあります。
仏壇を綺麗にする本来の意味を考えながら、自分に合った飾り方で仏壇のお花をお供えしてみてくださいね。
AND PLANTSでは、お供えのお花を取り揃えています。
そのまま花立てに入れられるブーケはもちろん、飾りやすいアレンジメントもおすすめです。即日発送の商品もご用意していますので、お急ぎの際にも安心してご注文いただけます。
気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
[https://andplants.jp/collections/offering-flower]