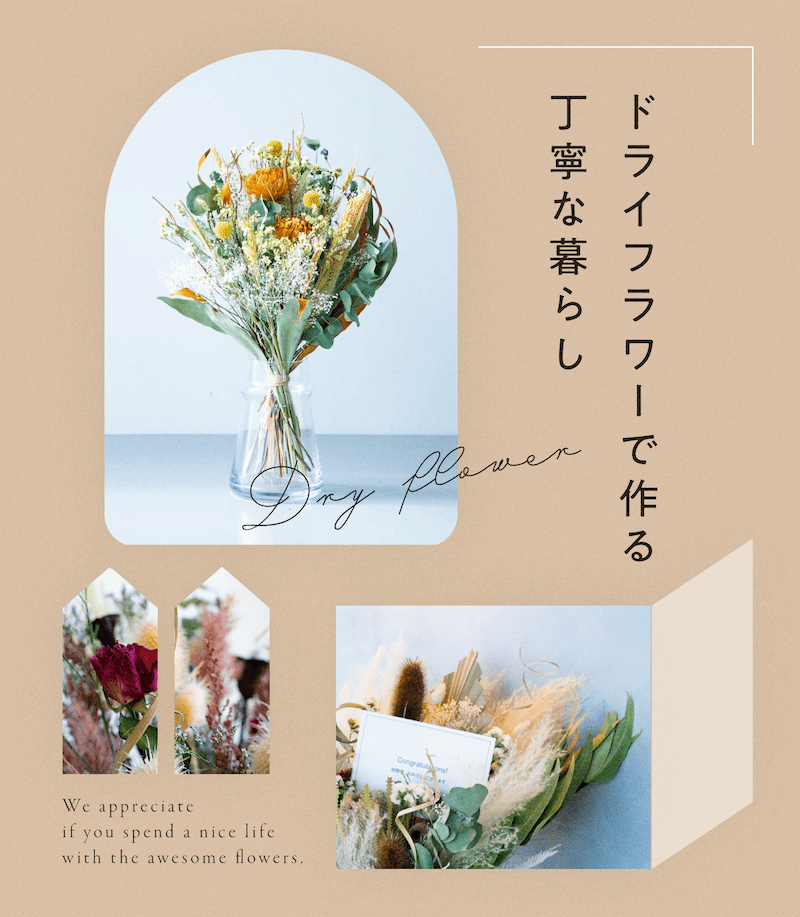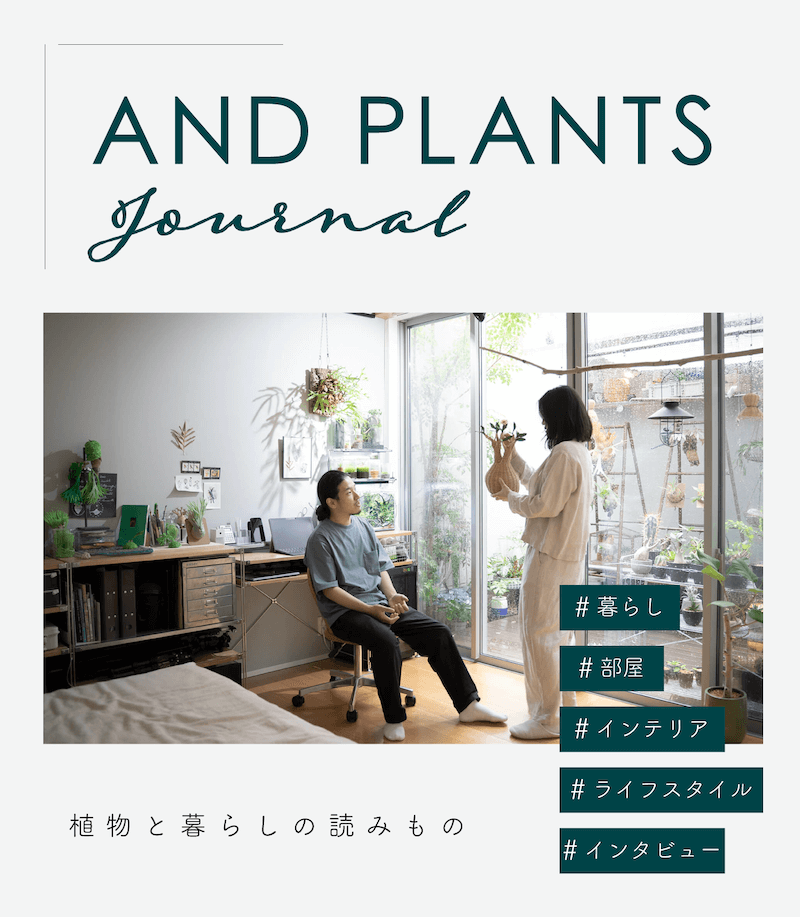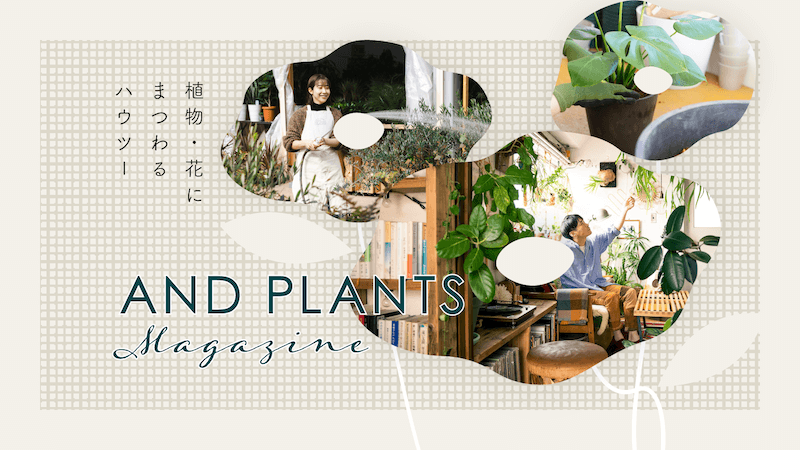夏場、観葉植物に水やりをした翌日、白いふわふわとしたカビが生えているということがあると思います。ほかにも肥料をまいたあとなどにも、見られる場合も。
白や黄色の綿毛のようなカビが、土の表面を覆い尽くすので不快に感じますよね。そのまま放置しておくと、次第にきのこが生えることもあります。
まず、どうしてカビが生えてしまったのか、またどのように除去すればいいのか。焦って悩むこともあると思いますが、カビが生えたからといって観葉植物が枯れることはないです。
今回は観葉植物に生えるカビの原因と予防対策について詳しく紹介します。除去方法についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
土の上に生えるカビを今すぐ改善したい方は、新しい土に植え替えを行うのがおすすめ。殺菌効果のある原料で、虫が住みにくく、カビも生えにくい環境が作れるでしょう。
[https://andplants.jp/products/andplantssoil-25l]観葉植物に生えたら危険・OKなカビ
実は、観葉植物に生えるカビには、すぐに対処が必要な「病気」のサインと、土壌の性質上ある程度は仕方がないものがあります。
見た目の特徴から、その危険度を正しく判断することが、大切な植物を守る第一歩になるでしょう。
ここでは、それぞれのカビの特徴と見分け方を詳しく解説します。
- 危険|葉・幹に生えたカビ
- OK|土・肥料の表面に生えるカビ
危険|葉・幹に生えたカビ
葉や茎、幹に直接カビが生えている場合、それは植物が病気にかかっている危険なサインです。
うどん粉をまぶしたような「うどんこ病」や、黒いススが広がったような「すす病」などが代表的でしょう。

これらは土に生えるカビとは異なり、植物の組織に侵入して養分を奪い、光合成を妨げてしまいます。植物の病気のサインであり、放置すると株全体が弱り、最悪の場合枯れてしまうため、早期の発見と対処が不可欠です。
見つけ次第、病気の部分を特定し、取り除くなどの対策をすぐに行う必要があります。
代表的な危険なカビ(病気)の種類と特徴を以下にまとめました。
| カビ(病気)の種類 | 見た目の特徴 | 危険度 |
| うどんこ病 | 葉や茎に白い粉をまぶしたようなカビが付着する | 高 |
| すす病 | 葉や枝が黒いススで覆われたように見える | 中〜高 |
| 灰色カビ病 | 花や葉が褐色に腐り、灰色のカビで覆われる | 高 |
| 白絹病(しらきぬびょう) | 株元に白い絹糸のような菌糸が広がる | 極高 |
OK|土・肥料の表面に生えるカビ

土の表面に現れる、白いふわふわとした綿のようなカビ。これは多くの場合、植物の生育に直接的な害を及ぼすものではありません。
有機質の腐葉土や肥料に含まれる成分を、微生物が分解する過程で自然に発生する「腐生菌(ふせいきん)」と呼ばれる菌類の一種です。
そのため、過度に心配する必要はありませんが、注意点もあります。
カビ自体はアレルギーの原因になる可能性があり、何よりカビが発生しているということは、土が常に湿っている「多湿」状態である証拠。
植物の生育に直接的な害は少ないものの、カビが生えやすい環境(多湿・風通しの悪さ)であるサインと捉え、管理方法を見直すきっかけにしましょう。
見た目が気になる場合は、表面の土ごとスプーンなどで取り除き、風通しの良い場所に置くことで改善が期待できます。
観葉植物にカビが生える5つの原因

どうして観葉植物の土や肥料、さらに葉の表面などにカビが生えるのか。何となく湿気が原因というのはわかると思います。
しかし、それ以外にもカビが発生してしまう原因がいくつかあります。
ここでは、観葉植物にカビが生える主な原因を以下5つ解説します。
- 有機物の土や肥料を使っている
- 湿度が高く土壌環境が悪化している
- 日当たりと風通しが悪い
- 土が乾きにくい
- すでに鉢の中に菌が紛れている
いくつかの条件が重なることで、カビは生えます。
またカビは植物や動物でもなく、小さな菌です。菌単体は肉眼で確認することができないので、気が付かないうちに室内に侵入していることもあります。
①有機物の土や肥料を使っている
土や肥料の表面に発生するカビは、有機物の素材や成分を使っているため繁殖しやすいです。
そもそもカビは、「糸状菌(しじょうきん)」と呼ばれる糸状の菌で、胞子を飛ばして繁殖する生物です。糸状菌の他に担子菌類とよばれる種類のカビは、生長するときのこを出して胞子を飛ばし、水を含むと植物のように発芽し、根を地面に張り巡らします。
栄養は植物や動物などの有機物から得るため、発芽できる場所は有機質の素材だけです。観葉植物の土に腐葉土・ウッドチップ・バーク・ココナッツファイバーなどが含まれていると、菌がそれらの有機物に付き、大きくなって繁殖します。
アンドプランツの「INLIVING 観葉植物の土」なら、有機物無配合なため虫・カビが付きにくいです。カビの発生に悩んでいる方は、下記の土に植え替えてみるのをおすすめします。
[https://andplants.jp/products/inliving-soil-2l]②湿度が高く土壌環境が悪化している
観葉植物にカビが生える最大の原因、水のやりすぎや風通しの悪さによって、土が常にジメジメと湿った「過湿」状態が続くこと。
植物を元気にしたい一心で水やりをしても、土が乾く暇がないと、カビにとって最高の繁殖環境を提供してしまいます。
特に、空気がこもりがちな室内では土の表面が乾きにくく、カビの温床になりがちです。また、受け皿に溜まった水をそのままにしておくのも、鉢底から常に湿気を供給し続けることになり、根腐れを引き起こす原因にもなるでしょう。
カビは、植物そのものだけでなく、その住処である「土壌環境」が悪化していることを知らせる重要なサインなのです。
ご自身の管理方法が、知らず知らずのうちに過湿を招いていないか、以下のチェックリストで確認してみましょう。
- 土の表面がまだ湿っているのに、次の水やりをしてしまう
- 水やり後、受け皿に溜まった水を捨てずに放置している
- 部屋を閉め切っていることが多く、風通しが良くない
- 梅雨の時期など、湿度が高い季節でも水やりの頻度を変えていない
③日当たりと風通しが悪い
日当たりと風通しが悪くなることで、空気が全く流れず停滞します。そのため、梅雨の時期になると気温と湿度がすぐに高くなりやすく、条件がそろう数値まで上昇するとカビが生えます。
また、日当たりや風通しが悪い場所では、葉についた菌の温床となりそのまま病気にかかることもあります。
④土が乾きにくい
カビ胞子は、水を含むことで発芽します。土が乾きにくく、いつまでも湿ったままでいると、土の上に落ちたカビ胞子は発芽をし続けるため、さらに範囲が広がる場合も。
土の表面に、ウッドチップを敷き詰めることもあると思います。しかし土が乾きにくいと、チップの裏側には白いカビ菌が無数に繁殖することもあります。
⑤すでに鉢の中に菌が紛れている
肉眼で確認しにくいカビ菌や胞子は、購入した鉢植えの土や庭・畑の土にすでに混入していることがあります。消毒されていないものは、カビがよく生えやすいです。
また、風に乗って胞子が飛ばされるため、気付かないうちに窓から侵入したり、人間の衣類に付着して室内に持ち込んだりする場合も。換気扇や換気口などほかにも侵入経路はあるので、完全に防ぐのは難しそうですね。
観葉植物に生えるカビを安全に除去方法

ふわふわとしたカビの見た目は、少し気持ちが悪く、衛生的に不快と感じる方も多いと思います。観葉植物の土にカビが生えていたら、除去後に環境を変えることが大切です。
カビの除去は、以下の5つの方法でやってみましょう。
- 表面の土を削り取る
- 新しい土に植え替える
- 木酢液や酢を吹きかける
- 濡れたティッシュで直接拭き取る
- 日当たりと風通しの良い場所へ移動させる
表面の土を削り取る
土の表面に広がってしまったカビは、その部分を物理的に取り除いてしまうのが最も手軽で効果的な方法です。カビは土の浅い部分で繁殖していることが多いため、根本からごっそり除去することができます。
スプーンや園芸用のミニスコップを使い、土の表面を2〜3cmほどの深さまで削り取りましょう。削り取った土にはカビの胞子がたくさん含まれているため、すぐにビニール袋などに入れて口を縛り、処分してください。
土を削った後は、新しい観葉植物用の土を足しておけば完了です。カビの温床となっている部分を物理的に取り除くことで、胞子がさらに広がるのを防ぎ、再発のリスクをぐっと下げることができます。
新しい土に植え替える
取り除いたカビ胞子が再度生える場合は、観葉植物の土を新しいものに植え替えるといいです。カビの菌糸は土の奥深くまで伸びています。根本的にカビを生やさないようにするのであれば、消毒された培養土を使うのがおすすめです。
また、カビ菌は植物の根に共生している場合もあるので、きっちりと行なうのであれば根鉢を崩してやさしく洗って掃除をするといいかもしれません。
ただし、植え替えは4〜7月の時期にしましょう。時期を間違えてしまうと、観葉植物がストレスを受けて枯れてしまう場合もあります。
具体的な植え替え方法と手順は「観葉植物の植え替え」を参考にしてください。
木酢液や酢を吹きかける
化学薬品を使いたくない方には、木酢液(もくさくえき)や家庭用の食酢を使った殺菌スプレーがおすすめです。これらに含まれる有機酸にはカビの増殖を抑える効果が期待でき、人やペット、植物にも比較的安全に使えます。
使用する際は、必ず規定の倍率に水で薄めてから使用してください。原液のまま使うと、植物を傷めてしまう原因になります。
目安として、木酢液は200〜500倍、お酢は20〜50倍程度に薄め、スプレーボトルに入れてカビが気になる土の表面や葉に吹きかけましょう。独特の匂いがありますが、カビ予防の心強い味方になってくれるはずです。
濡れたティッシュで直接拭き取る
葉の表面に、うっすらと白や黒のカビを見つけたばかりの初期段階であれば、濡らしたティッシュや柔らかい布で優しく拭き取るだけでも効果があります。薬剤を使わずに、今すぐできる応急処置です。
作業のコツは、胞子を周りに広げないように、そっと拭うこと。ゴシゴシ擦ると葉を傷つけたり、目に見えないカビの胞子をかえって塗り広げてしまったりする原因になるため、注意が必要です。
一度拭いた面は使わず、こまめにティッシュを交換しながら作業するのがポイント。拭き取った後に、薄めた木酢液などを軽くスプレーしておくと、より再発防止に繋がるでしょう。
日当たりと風通しの良い場所へ移動させる
カビを除去する作業とあわせて、必ず行いたいのが植物の置き場所の見直しです。カビは湿気と空気の滞留が大好きなので、日当たりと風通しの良い場所に移動させることが、何よりの再発防止策となります。
直射日光が葉にダメージを与えないよう、レースのカーテン越しの明るい窓辺などが理想的です。日光には消毒効果が、そして風通しは土の表面を適度に乾かし、カビが繁殖しにくい環境を作ってくれます。
カビの除去は一時的な対処ですが、環境改善はカビの発生源を断つ根本的な解決策となります。サーキュレーターで空気を優しく循環させるのも良いでしょう。
観葉植物に生えるカビの予防方法

一度カビを除去したら、もう二度と生やしたくないですよね。カビの予防は、実は植物を元気に育てるための基本的なお世話そのものです。
難しいことは何もありません。日々のちょっとした習慣を見直すだけで、カビの心配が少ない快適なグリーンライフを送ることができます。ここでは、そのための3つの重要なポイントをご紹介しましょう。
- 正しいお水やりをマスターする
- カビが生えにくい土を選ぶ
- 日当たりと風通しの良い場所で育てる
正しいお水やりをマスターする
カビを防ぐお世話の中で、最も大切なのが水やりです。
ポイントは「土の表面が完全に乾いてから、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」こと。この乾湿のメリハリが、カビを寄せ付けない健康な土壌環境を作ります。
土が湿っているうちに水を追加すると、常に土がジメジメした状態になり、カビの温床となってしまいます。水やりの前には必ず指で土を触ってみて、乾いているかを確認する習慣をつけましょう。
そして、「毎日少しずつ」ではなく、「乾いたら、たっぷり」と覚えておいてください。受け皿に溜まった水は、根腐れの原因にもなるため、その都度必ず捨てることが大切です。
カビが生えにくい土を選ぶ

植物にとっての「家」である土は、カビの発生を左右する重要な要素です。カビを防ぐには、水はけが良く、空気が通りやすい土を選びましょう。
園芸店などで販売されている「観葉植物用の土」は、水はけが良くなるようにあらかじめ配合されているため、初心者の方でも安心して使えます。
もしご自身で土を配合する場合は、赤玉土やパーライトといった無機質の用土を多めに混ぜ込むのがおすすめです。水やり後に余分な水分がスッと抜け、土の中に空気が通りやすい環境を作ることが、カビにくい土選びのゴールだと考えましょう。
カビが生えにくい、虫が住みにくい土をお探しの方は、アンドプランツのオリジナル観葉土がおすすめです。
[https://andplants.jp/products/andplantssoil-25l]日当たりと風通しの良い場所で育てる
適切な水やりと土選び。この2つの効果を最大限に高めてくれるのが、植物を育てる「環境」です。カビは「湿気」と「空気のよどみ」がある場所を好みます。この2つを日々の管理で取り除いてあげましょう。
具体的には、レースのカーテン越しに柔らかな日差しが当たる、風通しの良い窓辺などが最高の置き場所です。
日光には植物を元気にし、殺菌する効果も期待できます。また、定期的に窓を開けて換気をし、室内の空気を入れ替えるだけでも効果は絶大です。
カビの発生を防ぐことは、植物にとっても人にとっても心地よい空間づくりに直結します。ぜひ意識してみてください。
観葉植物のカビに関するよくある質問

さて、ここまでカビの対策や予防法について解説してきましたが、まだ「こんな場合はどうなの?」と気になる点があるかもしれません。
ここでは、観葉植物のカビに関して特によく寄せられる質問をピックアップしました。一つひとつの疑問に的確にお答えしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。
- アルコールスプレーで除去するのはあり?
- カビが生えた植物はもうダメになる?
- 人体やペットには悪影響はあるの?
- カビが生えた土は再利用できる?
アルコールスプレーで除去するのはあり?
条件付きで有効ですが、使用には注意が必要です。
消毒用のアルコールはカビの殺菌に効果があるため、カビが生えた鉢の縁を拭き掃除したり、土の表面に軽くスプレーしたりする分には有効でしょう。
ただし、植物の葉や茎に直接吹きかけるのは、株を傷めるリスクがあるためおすすめできません。アルコールが気化する際に葉の水分を奪い、葉焼けや変色の原因になってしまうからです。
もし使用する場合は、換気を十分に行い、植物自体にはかからないよう注意してください。植物に直接使える安全なスプレーをお探しなら、木酢液や植物専用の殺菌剤を選ぶのが賢明です。
カビが生えた植物はもうダメになる?
多くの場合、適切な対処で回復可能です。土の表面に生えた白いカビであれば、植物自体へのダメージは少なく、土の入れ替えや環境改善で十分に元気を取り戻します。
葉や茎にカビが生える病気の場合も、初期段階で発見し、病気の箇所を取り除いて殺菌すれば、助かる可能性は非常に高いでしょう。
カビの発生は、植物が出している「助けて!」のサインです。そのサインを見逃さず、すぐに行動を起こしてあげることが何よりも大切。手遅れだと決めつけずに、まずはできることから試してみてください。
人体やペットには悪影響はあるの?
一般社団法人 微生物対策協会によると、カビの胞子を吸い込むことで、アレルギー性鼻炎や喘息、皮膚のかゆみなどを引き起こすことがあるそうです。
特に、免疫力が低い小さなお子様やご高齢の方、アレルギー体質の方は注意が必要でしょう。また、ペットも同様に健康を害する可能性があり、好奇心でカビに触れたり舐めたりしないよう見守りも大切です。
植物のためだけでなく、ご自身と大切なご家族、ペットの健康を守るためにも、カビの早期発見と対策は非常に重要です。カビの除去作業をするときは、マスクの着用や換気を忘れないようにしてください。
カビが生えた土は再利用できる?
再利用はおすすめできません。新しい土との交換が最も安全です。
目に見えるカビを取り除いたとしても、土の中には無数の胞子や菌糸が残っている可能性が非常に高いです。その土を再利用すると、新しい植物や植え替えた植物にカビが再発する原因となりかねません。
熱消毒などの方法も存在しますが、手間がかかる上に完全に殺菌できる保証はありません。
大切な植物をカビのリスクから守るためには、一度カビが生えた土は思い切って処分し、清潔で新しい土を使いましょう。それが結果的に、植物を健康に育てる一番の近道となります。
まとめ
観葉植物の土に付着するカビは、特に悪さをしているわけではなく、植物の生長を助け育ちやすい環境をつくる役割を担っています。
しかし、そのまま放置しているのも気になる方が多いと思います。個人的には、表面だけでもいいので、新しい土に交換をするのがおすすめです。
特に、下記の用土であれば有機物無配合なため、虫やカビが発生しにくいでしょう。普段の植え替えの際にも使えるので、1つ持っておくと安心ですよ。
[https://andplants.jp/products/andplantssoil-25l]