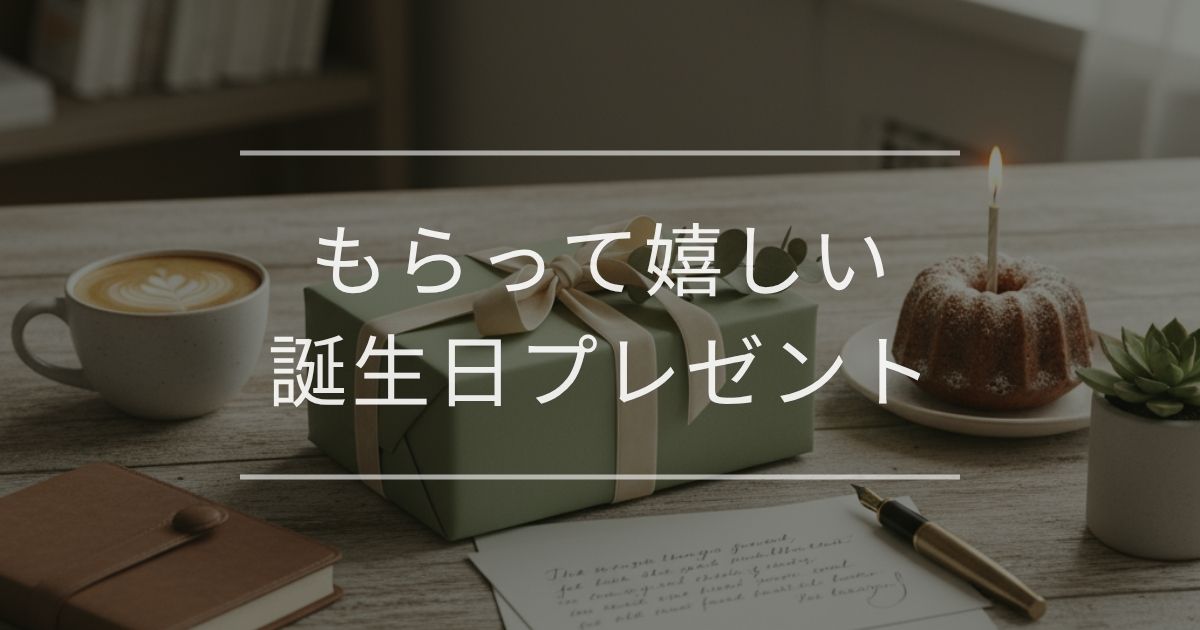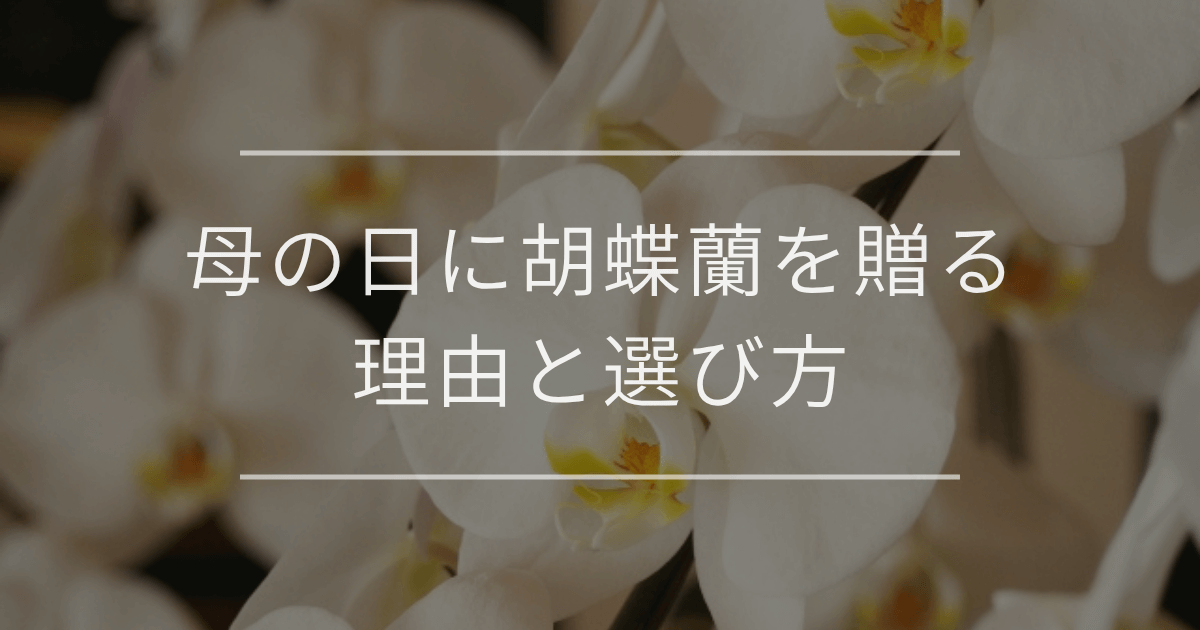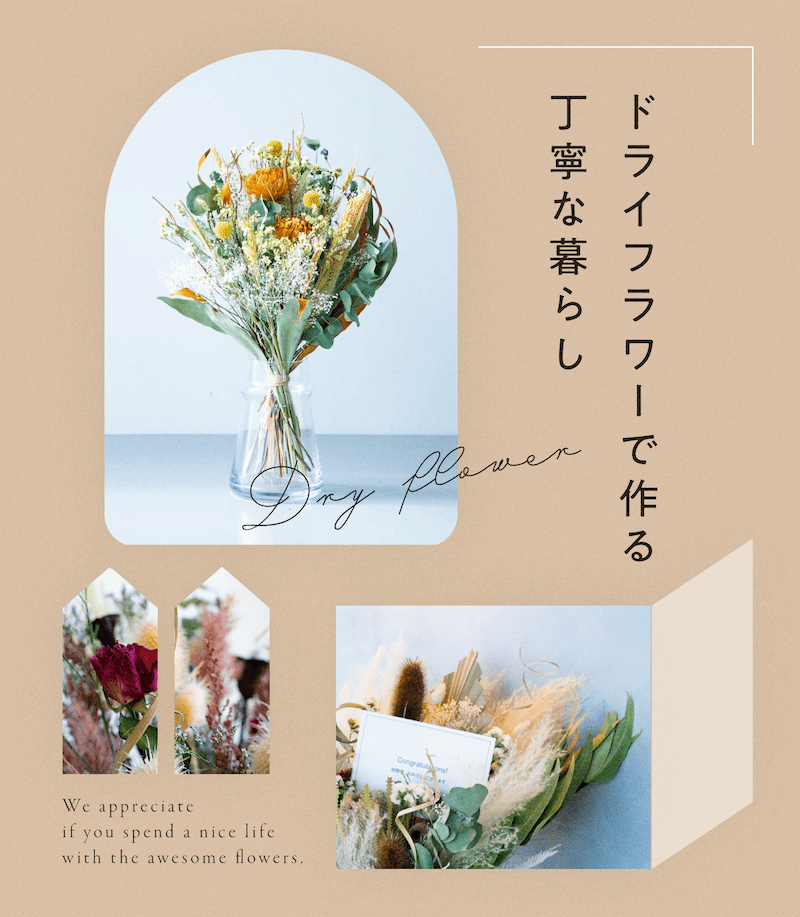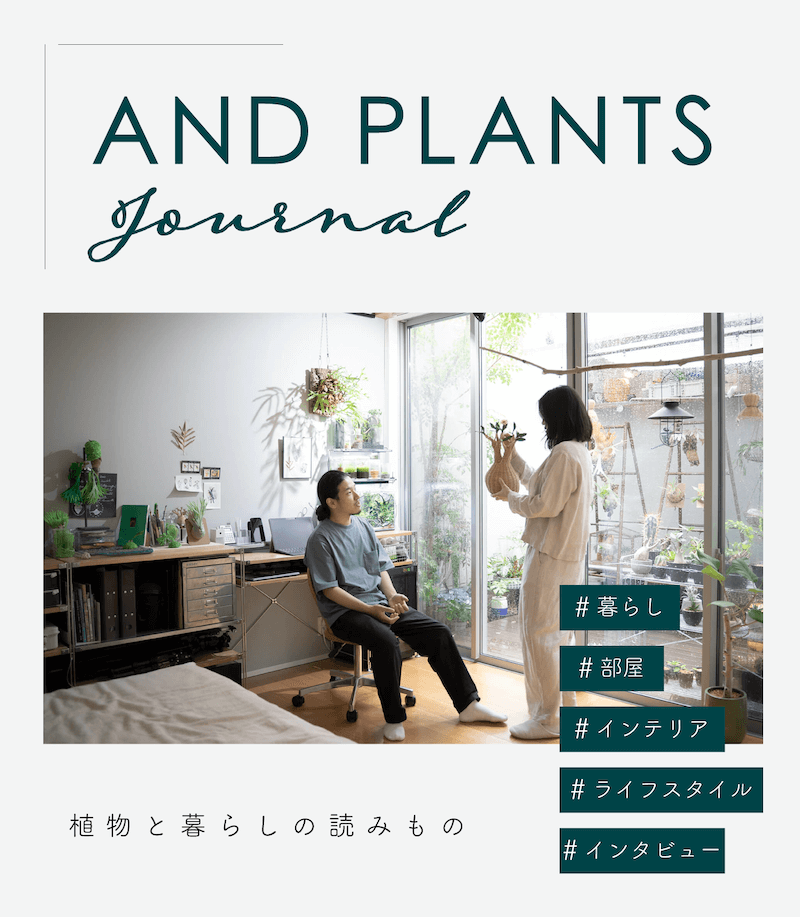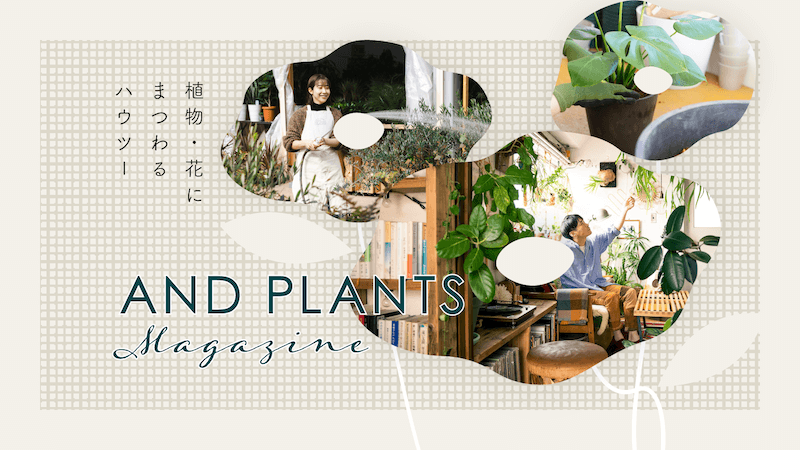土に植えずに楽しめるエアプランツ。個性的な姿をしている種類も多く、ユニークなインテリアグリーンとして人気があります。
しかし、エアプランツを育てていて枯らしてしまった方は意外と多いのではないでしょうか。「急に元気がなくなったけれど、対処法や復活方法がわからない」と悩んだ経験もあると思います。
今回は、エアプランツが枯れる原因について詳しく解説します。対処法や復活方法にも触れているので、ぜひ参考にしてください。
育てているエアプランツの元気が急になくなったら、枯れる予兆かもしれません。原因や対処法を知っておくことで、きっと枯らすことなく育てられます。
エアプランツが枯れる原因と対処法
エアプランツが枯れる原因は以下の5つが考えられます。
- 日当たり
- 風通し
- 水やり
- 温度
- 着生方法
対処法も含めて、それぞれ見ていきましょう。
①日当たり
エアプランツは、直射日光が当たらない明るい日陰を好みます。日陰と言っても、真っ暗な環境では生育できません。
室内であれば明るい窓際で、屋外であれば木漏れ日が差し込むような明るい日陰で管理します。また、西日や夏の直射日光に当たると葉焼けする可能性が高いので、注意が必要です。
葉焼けした葉は元には戻らず、そのまま枯れてしまうため剪定してください。強い直射日光が当たる場合は、遮光シートやレースカーテンをして日差しを和らげましょう。
筆者は、エアプランツを夏の直射日光に当てて葉焼けして枯らした経験があります。季節によっても日差しの当たり方は変わるので、注意してください。
②風通し
エアプランツは風通しが良い環境を好みます。水やり後に風通しが悪いと、蒸れて葉がバラバラになったり根元が腐ったりして枯れてしまう原因です。
屋外であれば自然と風が通るため、あまり心配はいりませんが、室内での管理では風通しに注意してください。水やり後は窓を開けて風通しを確保したり、サーキュレーターを利用したりして乾燥させましょう。
葉の隙間に水が溜まりやすいキセログラフィカやクルコフィラなどの種類は、水やり後は逆さまにして水が溜まらない工夫が必要です。
関連記事:観葉植物とサーキュレーター|必要性や使い方について
③水やり
エアプランツには水やりが必要です。「エアプランツ」の名前から、生育に水は必要ないと勘違いしてしまう方も多いかもしれません。
水やりを行わなければ、乾燥して枯れてしまうので注意してください。また、水やりは夕方から夜にかけて行いましょう。
エアプランツは、酸素や水分を吸収する「気孔(きこう)」が夜に開くためです。明るい日中に水やりしても、気孔は十分に開いていないため、効率的に吸水できずに根腐れする可能性があります。
④温度
エアプランツは寒さに弱い植物です。最低温度が10℃を下回ると生育が悪くなり、5℃以下では枯れる恐れがあります。
屋外で管理している場合は、気温が下がり始める秋には室内に移動させてください。冬の窓際は、屋外と変わらないくらいに冷え込むので、窓際から離して管理するとよいでしょう。
暖房の風が直接当たると、急激な乾燥によって枯れる原因になります。そのため、暖房の風が直接当たらない場所に置いてください。
⑤着生方法
エアプランツの多くは、木の幹に着生して生育します。着生せずとも生育はしますが、ヘゴやコルクなどに着生させると、より元気に育てることが可能です。
着生方法はさまざまですが、グルーガンやボンドは使わないでください。グルーガンは樹脂を高温で溶かして素材を接着させる道具です。
エアプランツの基部が高温の樹脂に触れることで、根元が傷んでしまいます。傷んだ根元は枯れる恐れがあるので、注意してください。
ボンドは高温で傷むことはありませんが、接着部分からの発根は期待できず、呼吸もできないため部分的に枯れる恐れがあります。
エアプランツの着生は細い針金で固定して、自然と伸びた根がヘゴやコルクなどにくっつくのを待った方が安心です。
症状別|エアプランツの復活方法

ここでは、エアプランツに起きる症状別の復活方法について紹介します。エアプランツを育てていて、起きる症状は下記の5つです。
- 葉が丸まる
- 葉に黒い斑点がある
- 葉が茶色い
- 乾かない
- 虫が付く
それぞれの復活方法を解説します。
①葉が丸まる|水やりする
エアプランツの葉が丸まるのは、「水不足」「空気の乾燥」が原因です。普段の水やりが少なかったり、冷暖房によって極端に空気が乾燥したりするときに葉が丸くなります。
エアプランツの葉が丸まったら、バケツやガラスなどの容器に水を溜めて一晩吸水させてください。翌朝には、溜めた水をしっかりと吸水して、張りでなく葉先もシャキッとした姿になります。
溜めた水にエアプランツを浸して吸水させる方法を「ソーキング」と呼びます。ソーキングは、月に1回程度、4~6時間ほどすると健康的な姿の維持に効果的です。
②葉に黒い斑点がある|ふき取る
葉に暗い斑点があるのは、カビやカイガラムシが付着している可能性があります。育てている環境の風通しが悪いかもしれないので、置き場所を変えたりサーキュレーターを設置したりして対策しましょう。
黒い斑点がカビであれば、柔らかいブラシや布で簡単に取り除けます。綺麗にふき取って、風通しの良い場所で管理してください。
カイガラムシが発生すると、葉の養分を吸汁した部分が黒くなります。カイガラムシは殺虫剤が効きにくいので、カビ同様に柔らかいブラシや布で取り除いてください。
エアプランツは黒いまだら模様が入る品種もあるため、黒い斑点が病害虫が原因であるとも限りません。育てているエアプランツがどんな品種であるか確認することも重要です。
③葉が茶色い|遮光する
エアプランツの葉が茶色い場合は、葉焼けしている可能性があります。屋外で直射日光に当たっているのであれば、遮光シートを張って光を和らげたり、明るい日陰に移動させたりしてください。
室内の窓際では、時間帯によって直射日光が差し込んでいるかもしれません。レースカーテンをして光を和らげるとよいでしょう。
葉焼けした部分は元には戻らないので、剪定はさみで切って形を整えてあげてください。
[https://andplants.jp/products/sakagen-flower-shears]④乾かない|風通しを良くする
水やり後に、エアプランツが乾かない場合は、風通しが悪い可能性が高いです。長時間、湿っている状態が続くと、カビが生えたり腐ったりするので注意してください。
水やり後は、風通しが良い場所に置くことが重要です。風通しが良い場所がなければ、サーキュレーターを使用しましょう。
また、水が溜まらない工夫も重要です。霧吹きやソーキングをした後に、お皿に置くと流れ落ちた水が溜まってしまいます。
溜まった水はエアプランツが乾燥しない原因の一つです。水やり後は、空中に逆さまに吊るしたりお皿にキッチンペーパーを敷いたりすると乾燥しやすくなります。
筆者は、キセログラフィカの筒状になった中心部分に水を溜めてしまって、腐らせた経験があります。水が溜まりやすいタイプは、逆さまにして水気をしっかり切ってください。
⑤虫が付く|殺虫剤を使う
虫が付く場合は、殺虫剤を使ってください。ハダニやカイガラムシなどが付くと、エアプランツの生育が悪くなり枯れる恐れがあるためです。
ハダニが付くと、黄色い斑点が葉に現れます。増殖すると、クモの巣のような糸をエアプランツ全体に巻き付けるので注意してください。カイガラムシが付くと、赤褐色~黒い斑点ができます。
日頃の観察で見つけ次第、市販の殺虫剤(ベニカXファインスプレー・オルトランなど)で対処しましょう。害虫によっては、一度の殺虫剤では対処できない場合もあるため、見つけ次第、何度も殺虫剤を使用します。
カイガラムシは殺虫剤が効きにくいので、柔らかいブラシや布で取り除く対処法がおすすめです。
虫がいなくなれば、新芽も自然と出てきてエアプランツも元気に復活します。虫が付く前から防虫として、除虫菊を配合した防虫スプレーをしておくことも効果的です。
[https://andplants.jp/products/evo_anti_insect_spray]エアプランツの育て方

エアプランツを枯らさずに楽しむためには、育て方が重要です。エアプランツの育て方について以下の5つのポイントに絞って解説します。
- 置き場所と日当たり
- 温度
- 水やりの頻度
- 肥料
- 剪定
関連記事:エアプランツ(チランジア)の育て方
置き場所と日当たり
エアプランツは風通しの良い日陰を好みます。ただし、日陰と言っても暗い日陰ではなく、木漏れ日が差し込むような明るい日陰です。
室内ではレースカーテン越しくらいの明るさがある場所で育ててください。屋外では、直射日光が当たらない明るい日陰で育てましょう。
強い直射日光は枯れる原因になるので注意が必要です。また、置き場所の風通しに特に気を付けてください。
エアプランツの水やり後に風がなく蒸れが続いてしまうと、根元の葉が黒くなり枯れてしまうことも。窓を開けることが難しい場合は、サーキュレーターを設置して使用するのも一つの手です。
関連記事:観葉植物とサーキュレーター|必要性や使い方について
温度
エアプランツは中南米原産の植物ですが、暑さにはそれほど強くなく寒さにも弱い植物です。生育適温は20~30℃で、10℃以下になると生育が止まり5℃以下になると枯れる恐れがあります。
そのため夏は風通しの良い涼しい日陰、冬は室内で管理することが重要です。屋外で育てている場合は、気温が下がり始める秋には室内に移動させてください。
冬の窓際は外気と変わらないくらいに冷え込むので、窓から離して温度変化の少ない部屋の中央に置くと管理しやすいです。
水やり
- 霧吹き:1週間に1~2回(夕方から夜)
- ソーキング:月に1回程度
エアプランツの水やりは霧吹きで夕方から夜にかけて行うことが重要になります。日が沈んで暗くなることで、水分を吸収する気孔が開くためです。
明るい日中に水やりをしても気孔が十分に開いていないので、吸水が十分にできず根腐れの原因になるので気を付けましょう。
梅雨時期と冬を除いて、月に一回程度バケツなどに溜めた水に4~6時間ほど浸すソーキングを行うと、効率よく吸水して葉が元気になります。
肥料
エアプランツは基本的に肥料は必要なく、水だけで育ちます。
ただし生育期の春(3~5月)と秋(10~11月)に限り、液体肥料を与えると葉に艶のある大きな株になりやすいです。規定の2倍以上薄めた液肥を霧吹きやソーキングで吸収させると良いでしょう。
通常の薄め方ではエアプランツにとって液肥が濃いので、液肥を与える場合はさらに薄く作ることが大事なポイントです。
AND PLANTSでは園芸用品ブランド「evo/ エボ」による、豊かな自然が育んだ腐植で作られた有機100%の植物活性剤の取り扱いがあります。ぜひ、こちらを利用してエアプランツを育ててみてください。
剪定
生育期である春と秋のエアプランツは、ゆっくりと新芽を出して大きくなっていきます。それに伴って外側の葉は古くなり枯れていきます。
その枯れた葉は、株元から優しく取り除きましょう。そのままにしておくと、風通しが悪くなったり、その隙間に水が溜まり根腐れの原因になったりします。
上手に取り除けない場合は、ピンセットで優しく取り除いてください。
エアプランツを育てている人からよくある質問

最後にエアプランツを育てている人からよくある質問とその答えを以下にまとめました。
- エアプランツは枯れるとどうなる?
- エアプランツが枯れてる時の見分け方は?
- エアプランツがふにゃふにゃなのはどうして?
- エアプランツの根元が枯れる原因は?
- エアプランツの根っこは切ったら枯れる?
- 茶色いエアプランツは復活する?
それでは具体的に見ていきましょう。
エアプランツは枯れるとどうなる?
エアプランツは枯れると、全体的に茶色になり根元を触ると葉がボロボロと落ちる状態に変化します。また、風通しが悪く蒸れや腐れで枯れた場合は、株元が黒くなることも。
根元が柔らかかったり、葉がボロボロ落ちたりした場合は、残念ながら復活できません。正しく管理して、美しいエアプランツを維持できるように育てましょう。
エアプランツが枯れてる時の見分け方は?
エアプランツが枯れている時の見分け方は、根元を触って葉がボロボロと落ちるかを確認してください。葉色でも確認できますが、品種によっては葉色は様々であるため見分けるのが難しいかもしれません。
葉色が白っぽい品種は、枯れているようにも見えるため、根元を触って確認するとよいです。また、枯れているエアプランツは葉が茶色っぽくなり、張りや艶がありません。
葉の状態と根元の硬さを確認して、枯れているかどうかを見分けましょう。
エアプランツがふにゃふにゃなのはどうして?
エアプランツがふにゃふにゃなのは、「日当たり不足」「水不足」が考えられます。暗すぎる場所では、うまく生育ができずに葉が間延びしたり柔らかくなったりするので注意してください。
また、水やりが少ないと葉の張りがなくなるため、ふにゃふにゃになりやすいです。水不足の場合は、ソーキングでしっかりと吸水させると、元の張りと艶のある状態に戻ります。
葉が茶色く、根元もふにゃふにゃの場合は枯れている可能性が高いです。ソーキングして、元に戻らなければ、回復は難しいでしょう。
エアプランツの根元が枯れる原因は?
エアプランツの根元が枯れる原因は、「水のやりすぎ(やらなすぎ)」「葉の隙間に水が溜まっている」が考えられます。
エアプランツを元気に育てるためには、水やりは非常に重要なポイントです。適切な水やりを心がけて育ててください。
水やりが適切でも、その後の管理によって根元が枯れることがあります。風通しの悪い場所に置いたり、葉の隙間に水が溜まりやすいタイプを上向きに置いていたりする場合です。
霧吹きやソーキングをした後は、しっかり水が乾くように、空中に吊るしたり、逆さまにしたりして水が溜まらない工夫をしてください。
エアプランツの根っこは切ったら枯れる?
エアプランツの根っこは、切っても枯れません。エアプランツは葉にある細毛「トリコーム」から水分や栄養分を吸収します。
根っこは着生するために伸びているので、根っこを切らせても生育には影響を及ぼしません。ただし、根の伸び具合でエアプランツの状態を確認できるため、切らずに伸ばして管理した方がよいでしょう。
いざ、コルクやヘゴ、バークなどに着生させるときに根が伸びていた方が、より着生しやすくなります。
茶色のエアプランツは復活する?
葉がすべて茶色のエアプランツの復活は難しいと考えられます。多くの場合、根元まで茶色で、触ると葉がボロボロと落ちるためです。
葉先だけが茶色いのであれば、剪定して形を整えましょう。外側の葉だけが茶色になっているのであれば、ピンセットで優しく茶色の葉を取り除いてください。
一部分が茶色になったエアプランツは、茶色の部分を取り除いた後に適切に管理すれば、自然と葉の枚数も増えて元気になるので安心してください。
まとめ
エアプランツはおしゃれなインテリアグリーンです。土を使わずに育てることができるため、お部屋やカフェ、サロンなどさまざまな場所で活躍しています。
しかし、日当たりや風通し、水やり、温度などによって枯れることもあるでしょう。いざ、調子が悪くなった時に、その対処法や復活方法を知っていると安心です。
原因がわからなくても、葉の症状によって対処することもできます。紹介した対処法や復活方法を試して、ぜひ元気なエアプランツを育ててください。