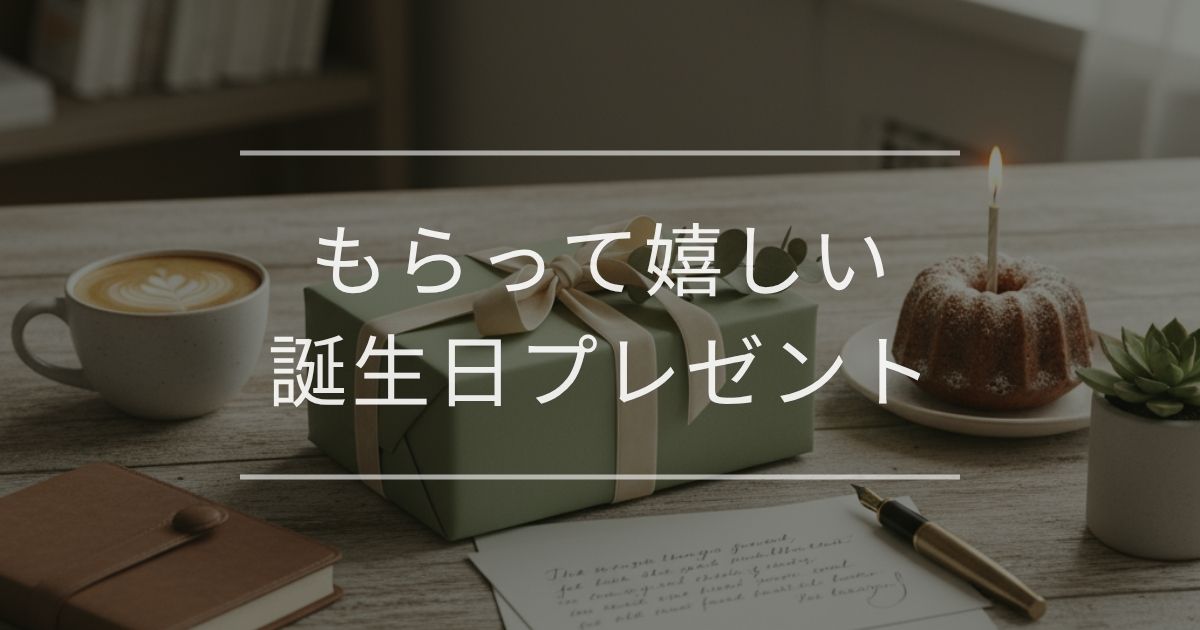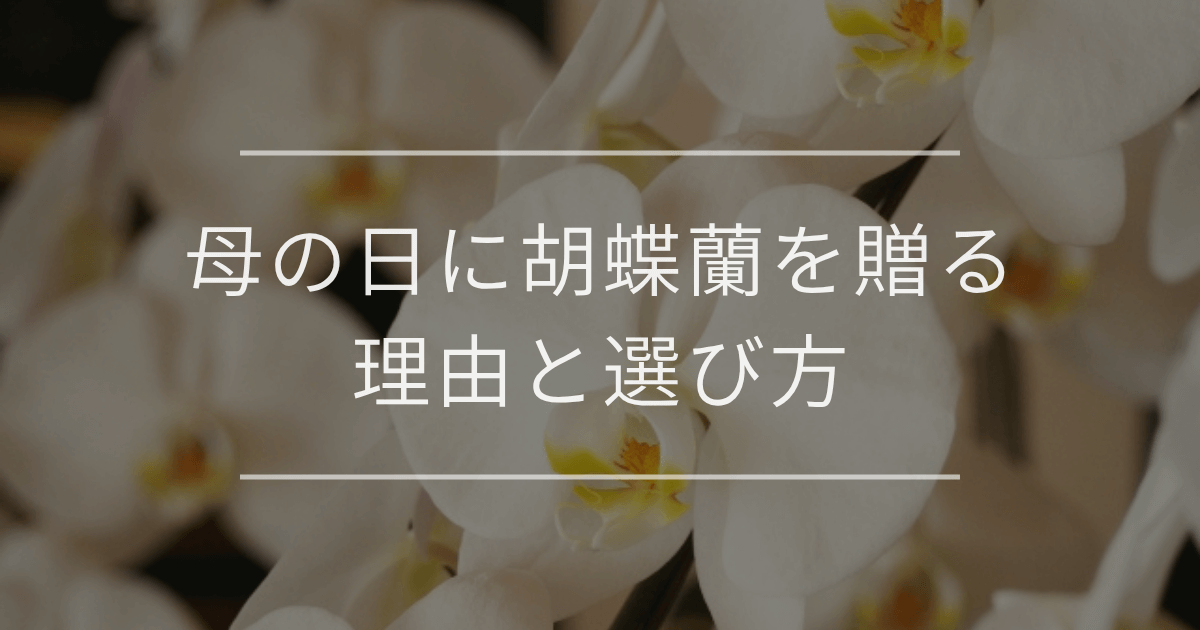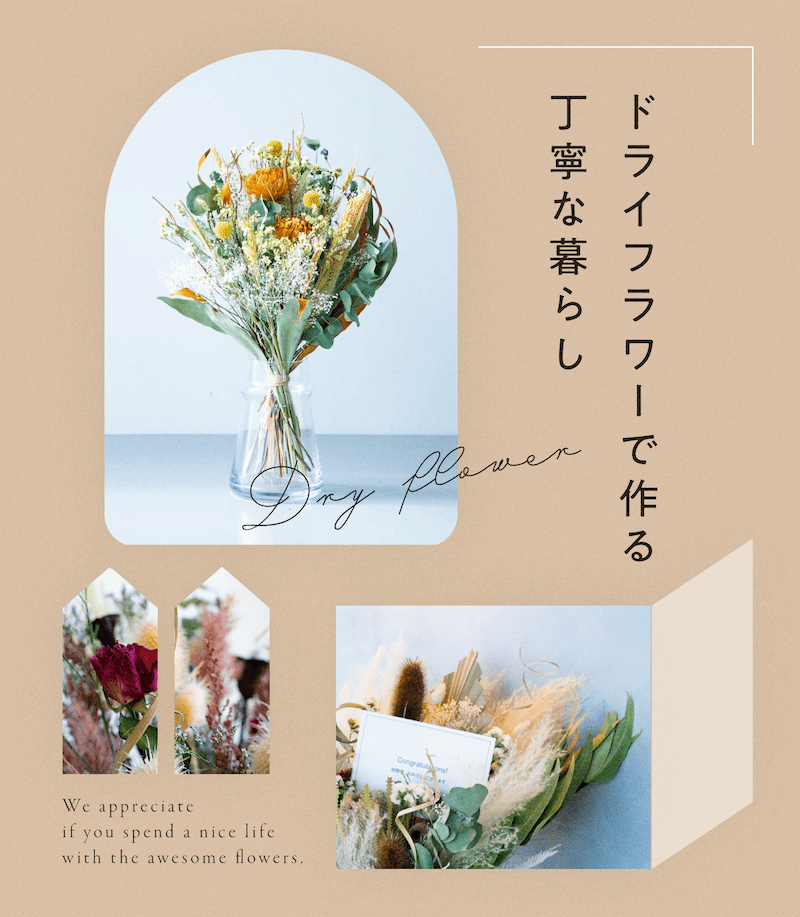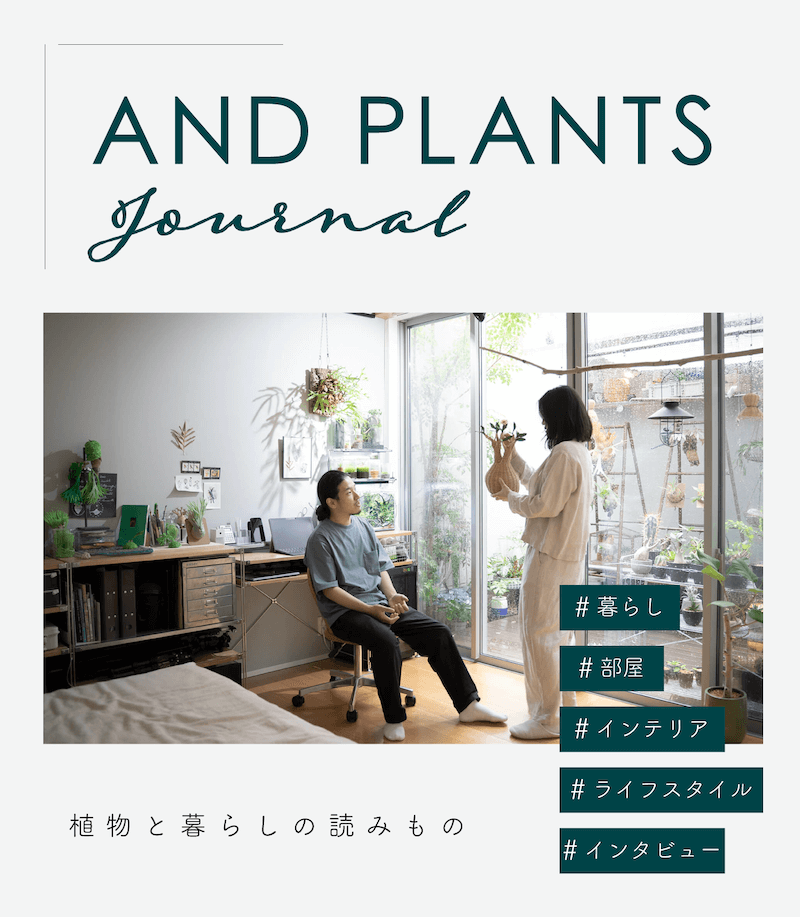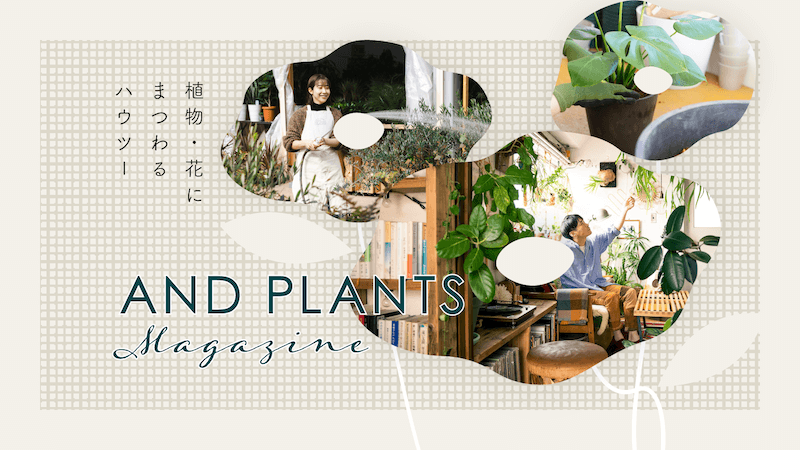| 項目 | 詳細 |
| 植物名 | ルディシア トリカラー |
| 学名 | Ludisia discolor 'Tricolor' |
| 英名 | Ludisia discolor 'Tricolor' |
| 科目/属性 | ラン科ルディシア属 |
| 原産地 | 東南アジア |
| 日当たり | 屋内のレースカーテン越しの光 |
| 温度 | 最低10℃以上をキープ |
| 耐寒性 | 弱い |
| 耐暑性 | 強い |
| 水やり | 手で土または水苔を触って水分が少なくなってきたら |
| 肥料 | 緩効性肥料、液体肥料 |
| 剪定時期 | 5月~10月 |
ジュエルオーキッド(ルディシア トリカラー)をすぐにチェックしたい方は、下記をクリックすると商品一覧に移ります。
[https://andplants.jp/collections/jewelorchidludishiatricolar]ルディシア トリカラーの特徴
ルディシア トリカラーは、深緑色の葉に、きめ細かい白い葉脈入るジュエルオーキッドです。生育が進むにつれて、葉にはピンク色が混じることから、3色を意味するトリカラーの名前が付いています。

ルディシア ディスカラーの変種です。ルディシア ディスカラーは1属1種の植物ですが、葉の色や模様の変異が非常に多いため、緑葉や黒葉、白い葉脈、赤い葉脈などさまざまな種類があります。
ディスカラー同様に、トリカラーも暑さ・蒸れに強い傾向があるので、初めてジュエルオーキッドを育てる方におすすめです。葉色にピンクの差し色が入り始めると、優しい雰囲気が増します。
自生地ではジャングルの奥地で育つ植物です。夏の直射日光や冬の寒さに当てると枯れやすい点には注意してください。
ルディシア トリカラーの育て方

ここでは、ルディシア トリカラーの基本的な育て方を6つのポイントに分けて紹介します。
- 置き場所と日当たり
- 温度
- 水やりの頻度
- 肥料
- 剪定方法
- 植え替え方法
ルディシア トリカラーの育て方の確認前に、美しい葉脈や葉色、株姿などの見た目の美しさが気になる方は以下をクリックしてみてください。
置き場所と日当たり

ルディシア トリカラーは屋内のレースカーテン越しの光を好む植物です。直射日光に当たると、葉焼けの原因になるので窓際で管理する際は注意してください。
レースカーテンやシェードなどで、直射日光を和らげて管理します。ただし、暗すぎる環境では茎が徒長したり葉色が薄くなったりするため、光が全く入らない暗いお部屋には置かないでください。
お部屋に日差しが入らず暗すぎる場合は、植物育成用LEDライトを利用して光を補うと安心です。AND PLANTSでは、太陽光に近い波長を使用した「バレル 植物ライト(TSUKUYOMI 10W ホワイト)」を取り扱っています。
徒長させずに美しい葉を維持させたい方は、ライトスタンドで照射距離を調整しつつ光に当てて管理してください。
[https://andplants.jp/products/tsukuyomi-10w]温度

ルディシア トリカラーは寒さに弱いため、最低10℃以上をキープして育ててください。生育温度は15~25℃なので、冬でも15℃以上あれば、ゆっくりと生育します。
基本的に一年を通して室内で育てますが、冬や真夏は窓際の近くに置かないようにしてください。レースカーテンをしていても、屋外の気温の影響を受けやすいためです。
暑さには比較的強いですが、30~35℃以上の夏の高温に当たり続けると枯れる可能性があります。特に、密閉した容器の中で育てている場合は注意しましょう。
密閉した容器内の温度が上がりすぎないように、定期的に風を通して温湿度を調整してください。もし可能であれば、真夏だけでもクーラーを常時稼働させて室温を一定にしておくと、安心して夏越しさせられます。
水やりの頻度

ルディシア トリカラーの水やりは、1年を通して以下の水やりを徹底してください。
- 手で土または水苔を触って水分が少なくなってきたら
生育が緩慢な真夏や冬であっても、基本的に湿った状態を保ってください。ただし、受け皿に常に水を溜めた状態だと、根が空気に触れることができずに根腐れします。
指で少し水分を感じる程度を一年中維持しましょう。土や水苔に霧吹きを近づけて、噴霧して水分を染み込ませる水やりがおすすめです。
ガラス容器や水槽内では、湿度計を入れて湿度70~90%を維持しながら霧吹きで管理します。密閉容器内では、水が溜まりやすいので与え過ぎに注意してください。
底に水分が溜まった場合は、丸めたティッシュをピンセットで挟んで吸水すると、効率よく余分な水分を取り除けます。
土や水苔の乾き具合が分からない場合は、水やりチェッカーの利用がおすすめです。以下の水やりチェッカーは水苔にも使用できるので、ぜひ水苔管理の際に使ってみてください。
[https://andplants.jp/products/watering_checker_sustee_large_single]肥料

ルディシア ディスカラーには、生育期の5月~7月、9月~11月それぞれに1度置き肥を置くか、水に薄めた液肥を水やり代わりに与えると生育が良くなります。
ただし、観葉植物に与える規定量よりもずっと薄い濃度で与えてください。通常の観葉植物に与える液肥の希釈倍率が1,000倍であれば、3,000倍といった形です。
肥料成分を多く必要とする植物でないため、与えすぎると根傷みの原因になります。キラキラと光る美しい葉脈を楽しむために、葉を増やしたり大きくしたりしたい方は薄めの液肥を与えてください。
AND PLANTSでは、オリジナル肥料「アンドプランツ 植物を元気にする固形肥料」を取り扱っています。土や水苔の上に置くだけ、混ぜるだけで効果のある肥料です。
ルディシア トリカラーに与える際には、土や水苔の上に5粒程度の量を置いておくと良いでしょう。真夏や冬前には、固形の肥料は取り除いてください。
[https://andplants.jp/products/andplants_fertilizer]剪定方法

ルディシア トリカラーの剪定は、枯れた下葉や伸びすぎた茎を切る程度です。
ジュエルオーキッドは花が咲く植物です。順調に生育した場合、直径5㎜程度の小さな白い花を咲かせる花茎が伸びます。
ルディシア トリカラーをはじめジュエルオーキッドは花が咲くと、開花後に一時的に葉がボロボロになりやすいので注意してください。栄養が花に集中してしまい、株の体力が落ちてしまうためです。
花茎が伸び始めたら、花を咲かせずに早めに茎の付け根部分からの剪定をおすすめします。筆者はルディシア ディスカラーを育てていますが、開花後に株が元気をなくしたので、それ以降は花を咲かせないように花茎は剪定するようにしています。
葉の美しさを常に楽しみたい方は、伸び始めた花茎は早めに剪定してください。
AND PLANTSでは皇室献上品でもある、新潟県三条市の100年企業・株式会社坂源のハサミ「Sakagen Flower Shears」を取り扱っています。剪定に失敗しないためには、切れ味の良いハサミが欠かせません。
観葉植物専用の剪定ハサミを持っていない方は、ぜひ使ってみてください。
[https://andplants.jp/products/sakagen-flower-shears]植え替え方法
ルディシア トリカラーの植え替え時期は、5月~7月の春から夏前にかけて行います。水苔または水はけのよい土に植え替えしましょう。
手順は以下の通りです。
- 鉢を逆さまにして優しく根鉢を取り出す
- 根を切らないように水苔や土をほぐす
- 新しい水苔や土で植えなおす
- 植え替え後は発根剤や活力剤を薄めて水やりする
ルディシア属に限らず、ジュエルオーキッドの根は繊細で折れやすいです。さらに、根の生育も遅いので、植え替えは慎重に行ってください。
根の生育が遅い植物です。あまり根が伸びていない場合は、同じサイズの鉢に植え替えましょう。
大きすぎる鉢に植え替えると、根腐れや蒸れを引き起こす危険があります。また、土で育てている株は、土に植え替えてください。
水苔で育てている場合も同様です。今まで育ってきた環境と異なる用土を使用した場合、根が傷む要因になります。
「土→水苔」「水苔→土」といった植え替えはしないようにしましょう。植え替え後は発根剤や活力剤を与えながら管理すると、植え傷みからの回復が早くなります。
AND PLANTSでは、「微生物の力で植物を元気にする水」といった活力剤を取り扱っています。光合成細菌の力で、土壌環境を良くして発根を促します。
土栽培をする方は、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。
[https://andplants.jp/products/microorganismswater]ルディシア トリカラーの増やし方

ルディシア トリカラーは、5月~7月に挿し木や茎伏せ(くきふせ)で増やします。簡単な手順は以下の通りです。
- 節が残るようにカットする
- 容器に溜めた水に浸けて1時間ほど吸水させる
- 葉を半分ほど剪定する
- 肥料の入っていない土または水苔に挿す
- 乾燥しないように明るい室内で管理する
- 発根して新芽が出てきたら植え替える
茎伏せとは、茎を土や水苔に挿すのではなく、横に寝かせる方法です。1節残るように茎をぶつ切りにして、土や水苔の上に横に置くだけです。
湿度が70~90%の高湿度環境下で育てている株であれば、剪定前の株の節から気根が伸びていることがあります。気根が出ていれば、より簡単に増やすことが可能です。
筆者は、ルディシア トリカラーを密閉できる透明な容器内で茎伏せして増やしました。しかし、高湿度条件では、切断面が乾かず病原菌が侵入しやすい状態です。
茎伏せや挿し木をする際は、切断面にトップジンMペーストのような殺菌癒合剤を塗っておくと、より安心して増やせます。また、太い茎であるほど発根発芽率が良いので、増やす際はルディシア トリカラーをしっかりと育てておきましょう。
ルディシア トリカラーのよくあるトラブルと対処法

初心者向きのルディシア トリカラーですが、トラブルが発生する場合もあります。ここではよくあるトラブルと対処法を解説していきます。
ルディシア トリカラーによくあるトラブルは以下の6つです。
- 根腐れ
- 根詰まり
- 葉焼け
- 伸びすぎ(徒長)
- 葉が赤くなる
- 葉が下を向いて枯れる
対処法を知っておくと、いざトラブルが起きても安心して対処できます。それぞれ見ていきましょう。
根腐れ
ルディシア トリカラーの根腐れでは、以下の症状が見られます。
- 株がグラグラする
- 葉が茶色・黄色に変色している
- 葉がポロポロ落ちる
- 株元が柔らかく黒ずんでいる
- 土や水苔から腐敗臭がする
- 土や水苔の表面にカビが生えている
- 根が黒く変色している
根腐れは、土の酸素濃度が低下して土壌環境が悪くなることで発症します。また、土が常に湿っていると、根は呼吸できずに枯れてしまい、根自らが腐る症状でもあります。
水苔は多く空気を含むことができ、通気性も良いため、土よりも根腐れしにくい素材です。しかし、管理によっては土同様に根腐れを発生させる点には注意しましょう。
根腐れの対処法は以下の通りです。
- 土や水苔の乾湿サイクルが早くなるように、1回り小さな鉢に植え替える
- 古い土や水苔を落として新しいものに交換する
- 根の傷んでいる部分、腐っている部分をカットする
- 風通しがよく明るい日陰で管理する
※1週間を目安に水が乾くコンディションで管理する - 発根剤を与える
- 傷んだ葉・ポロポロと落ちる葉はすべてを取り除く
- 殺菌剤に浸す
根腐れが起こった場合は、植え替えをして土や水苔の環境を変えることが大切です。傷んでしまった根は取り除き、健康な根が伸びる状態にしてください。
ケイ酸塩白土・ゼオライトなどの根腐れ予防効果のある土壌改良材も新しい用土や水苔に混ぜ込むと、より根腐れしにくくなります。
根詰まり
根詰まりとは、鉢の中が根でいっぱいになることで起きる症状のことです。
ルディシア トリカラーは根詰まりすると、以下のような症状が見られます。
- 新芽が出てこなくなる
- 葉色が全体的に薄くなる
- 下葉からポロポロと落ち始める
ルディシア トリカラーの根は繊細で小さく、さらに1~2本程度しか伸びません。根の生育も非常にゆっくりです。
そのため、2~3号(直径6~9㎝)程度の小さな鉢で育てられていることがほとんど。最初の数年間はそのままでも問題ありませんが、あまりにも小さな鉢に長期間植えっぱなしにしていると根詰まりする場合があります。
対処法は、植え替えです。
5月~7月、または9月~11月に、土や水苔を優しくほぐして根を傷めないように植え替えます。根の伸び具合にもよりますが、ほとんどの場合は同じ鉢サイズまたは0.5号アップの鉢に植え替えてください。
大きな鉢に植え替えると、根腐れする原因になるので気を付けましょう。植え替えするだけで、上記の症状は解決します。
葉焼け
ルディシア トリカラーが葉焼けすると、以下の症状が出てきます。
- 葉先が赤色~茶色くなる
- 葉が黒く焦げたようになる
強い日差しを浴びすぎると、葉が傷んで「葉焼け」のトラブルが発生します。葉焼けの症状に気がついたら、直射日光を避けるように対策してください。
対処法は以下の通りです。
- 置き場所を変える
- レースカーテンやシェードなどで遮光する
- 葉焼けした葉は取り除く
葉焼けのトラブルが起きる場合、強い直射日光が当たりすぎている可能性が高いです。直射日光を弱めたり、置き場所を移動したりしてください。
株全体が強い直射日光で枯れていなければ、日差しの対処をすれば自然と新芽が出てきます。葉焼けした葉は元には戻らないので、株全体のバランスを見ながら切り取ってください。
株元が葉焼けで傷んでいる場合は、元気な茎を節を残すように切って挿し木や茎伏せで復活させるようにしましょう。
ジュエルオーキッドをテラリウムやパルダリウムとして育てている方の中には、植物育成用LEDライトで明るさを管理している方もいると思います。
植物育成用LEDライトは、種類によって光の強さが異なります。そのため、近距離で光を当てていると葉焼けすることも。植物育成用LEDライトを使って育てる場合は、照射距離を調整しながら育ててください。
伸びすぎ(徒長)
ルディシア トリカラーには、茎が伸びすぎる徒長トラブルが起きることがあります。考えられる原因は、主に以下の2つです。
- 日当たり不足
- 水のやりすぎ
徒長すると、株全体が伸びて見栄えが悪くなります。また、葉や茎の組織が軟弱になるため、病害虫の被害も発生しやすいです。
徒長の対処法は、以下の通りです。
- 日当たりの良い環境で育てる
- 風通しを良くする
- すでに徒長した茎は切り戻す
徒長したルディシア トリカラーを、日当たりの良い場所に置いても元に戻ることはありません。徒長して見栄えが悪い株は、茎を切り戻してください。
切り戻した株の節から新芽が出てきますので、出てきた新芽が伸びすぎないように育てましょう。日頃から暗すぎる場所で管理しないように、植物用LEDライトを利用して管理しておくと安心です。
葉が黄色くなる
ルディシア トリカラーは、以下の原因で葉が黄色くなるトラブルが発生します。
- 日当たり不足
- 寒さ
- 高温(蒸れ)
- 新陳代謝
ルディシア トリカラーを、本も読めないほど暗すぎる場所に置くと、十分に光合成ができません。光合成が出来なければ、葉色を維持できず薄くなり、黄色っぽくなることがあります。
また、寒さに弱い植物なので、10℃以下の寒さに当たり続けると葉が黄色く枯れることがあります。真夏の直射日光に当たった場合でも同様の症状が出ます。
特にテラリウムのような形で密閉して育てている場合、直射日光に当たると高温による蒸れも重なり、葉が黄色く枯れることも。
対処法が以下の通りです。
- 直射日光の当たらない明るい環境で管理する
- 冬は暖かい室内で管理する(最低10℃以上)
- 風通しを良くする
- 黄色くなってしおれた葉は切り取る
適切な温度や日当たりの場所に移動しても、黄色くなった葉は元には戻りません。黄色くなった葉は早めに切り取りましょう。
生育が順調であっても、新芽が出たタイミングで古い下葉は黄色くなりやすいです。これは、新陳代謝によって新芽へ栄養が移動している現象なので、そのまま安心して育ててください。
ルディシア トリカラーの害虫トラブルと対処法

ルディシア トリカラーに発生しやすい害虫は以下の4つです。
- ハダニ
- カイガラムシ
- アブラムシ
- コバエ
それぞれ見ていきましょう。
ハダニ
ハダニの症状は以下の通りです。
- 葉にクモの巣のような糸がついている
- 葉の裏に小さな虫がついている
- 葉に斑点やカスリのような傷がある
- 葉の色が薄くなり枯れている
ハダニは繁殖力の強さと、薬剤耐性を持つ厄介な害虫です。
放っておくと糸を張って大量発生する危険性もあるので、早めに対処を行いましょう。
対処法は以下の通りです。
- 傷んだ葉は取り除く
- 葉の表裏、付け根や葉柄も水で洗浄する
- ハダニに効果のある液体を噴霧する(殺虫剤のほか、2倍に薄めた牛乳、重曹と水を混ぜたもの、濃いコーヒー、10倍に薄めた酢でも一定の効果あり)
ハダニが湧いてしまったら、市販の殺虫剤(ベニカXファインスプレー・オルトランなど)の使用が効果的です。ハダニは一度では駆除しきれないことがほとんどなので、状態を見ながら、定期的に噴霧してください。
2倍に薄めた牛乳などの液体を噴霧する対処法もありますが、匂いが気になる方は水で洗い流す方法がおすすめです。
ガラス容器内やテラリウムで高湿度環境を維持して育てていれば、ルディシア トリカラーにハダニが付くことは稀です。ただし、高湿度条件下でなければ、ハダニが発生することはよくあります。
ハダニが現れたら、こまめに殺虫剤を吹きかけたり、ホースシャワーで株全体を水で洗い流したりしてください。
ハダニは非常に小さいため、姿を確認しにくい害虫です。葉を触ってザラザラした感触がある場合はハダニがいるかもしれません。
大発生してクモの糸のようなものが目立ち始めたら注意です。そうなる前に「観葉植物に発生するハダニ」の記事で初期症状や対処法を確認しておきましょう。
カイガラムシ
カイガラムシの症状は以下の通りです。
- 貝殻のような殻を被ったり、粉状の物質で覆われたりしている虫がついている
- 黒いカビ(すす病)が発生している
- 葉や鉢、床がベタベタしている
カイガラムシは繁殖力の強さと薬剤耐性のある厄介な害虫です。
風通しの悪い環境で育てていると、葉と葉の隙間や株元の付け根にカイガラムシが発生しやすいです。そのままにしていると、大発生してすす病を併発させたり株が弱々しくなったりするので注意してください。
見つけ次第、早めに対処しましょう。対処法は以下の通りです。
- 柔らかい布やブラシで擦り取り除く
- 茂り過ぎている葉は取り除き、風通しを良くする
- カイガラムシに効果のある液体を噴霧する(殺虫剤のほか、2倍に薄めた牛乳、重曹と水を混ぜたもの、濃いコーヒー、10倍に薄めた酢でも一定の効果あり)
カイガラムシが発生したら、市販の殺虫剤(ベニカXファインスプレー・オルトラン・スミチオンなど)の使用が効果的です。
しかし、カイガラムシは殺虫剤が効きにくい害虫です。そのため、殺虫剤使用と布・ブラシでの拭き取りを合わせて行うと効率的に駆除できます。
ルディシア トリカラーの茎は柔らかいので、傷つけないように優しくブラシで取り除いてください。数が少なければ、ピンセットで取り除いた方が早い場合もあります。
ジェルオーキッドに付くカイガラムシ対策も、観葉植物に付くカイガラムシ対策と一緒です。「観葉植物の白い虫はコナカイガラムシ」の記事の内容を参考にしてみてください。
アブラムシ
徒長させると、アブラムシが増えやすくなります。徒長した株や生育不良の新芽は柔らかく、アブラムシが集まりやすいためです。
アブラムシが発生した際の症状は、以下の通りです。
- 新芽にアブラムシが密集している
- 新芽の葉の形がゆがんでいる
- 白~茶色い脱皮殻が目立つ
- 葉や鉢、床がベタベタしている
アブラムシは繁殖力が強いため短期間で増え、ウイルスを媒介する厄介な害虫です。
脱皮を繰り返して短期間で成虫になるので、アブラムシが増えると、葉に白~茶色の小さなチリのようなものが目立ち始めます。このチリのようなものは、脱皮殻です。
脱皮殻を見つけた際は、近くにアブラムシがいますので、注意深く観察して見つけてください。放っておくと生育が弱まり綺麗な新芽が出てこなくなるので、早めに対処を行いましょう。
対処法は以下の通りです。
- ゆがんだ新芽は取り除く
- アブラムシを取り除く
- 枯葉は取り除いて風通しをよくする
- 日当たりと風通しの良い場所に移動させる
- アミノ酸を多く含む有機系の肥料は与えない
- アブラムシに効果のある液体を噴霧する(殺虫剤のほか、2倍に薄めた牛乳、重曹と水を混ぜたもの、濃いコーヒー、10倍に薄めた酢でも一定の効果あり)
アブラムシを見つけたら、市販の殺虫剤(ベニカXファインスプレー・オルトランなど)の使用がおすすめです。殺虫剤が効きやすい害虫なので、すぐに対処すれば被害は大きくなりません。
コバエ
コバエの症状は以下の通りです。
- 土や水苔に虫が湧く
- コバエが植物の周囲を飛んでいる
コバエ自体は植物に無害ですが、ルディシア トリカラーを育てるうえでは不快害虫です。放っておくとコバエはどんどん増えていくので、早めに対処を行いましょう。
対処法は以下の通りです。
- 発酵不十分な堆肥や有機質肥料を与えることをやめる
- 新しい土や水苔に植え替える
- 土の表面に無機質な素材(赤玉土・鹿沼土・砂利など)を敷く
- トラップを仕掛ける
- コバエに効果のある殺虫剤を噴霧する
土や水苔が常に湿っている環境になりやすいルディシア トリカラーに、堆肥や有機質肥料を使うとコバエが発生する原因になります。そのため、水苔で育てて有機質肥料を使わない育て方がおすすめです。
もしコバエが発生したら、市販の殺虫剤(ベニカXファインスプレー・オルトラン・スミチオンなど)を使って退治しましょう。スプレーでうまく対処できない場合は、トラップを仕掛けて数を減らすのも一つの手です。
コバエのトラップは食器用洗剤やお酢、めんつゆなどで簡単に作ることができます。植物の近くに置いておくと、簡単にコバエを捕殺できるはずです。
土の中の卵や幼虫が気になる場合は、溜めた水に殺虫剤を溶かして、一時的に鉢ごと沈めてください。土の中にいる幼虫や卵は、殺虫成分と窒息の効果で退治できます。
土栽培にこだわりたい方は、「観葉植物に発生するコバエ」の記事を確認して、コバエ対策をしっかりしておきましょう。
ルディシア トリカラーの育て方に関するよくある質問

最後にルディシア トリカラーの育て方に関するよくある質問とその答えを以下にまとめました。
- ガラス瓶や水槽での育て方は?
- テラリウムとして別の植物と植えても大丈夫?
それでは具体的に見ていきましょう。
ガラス瓶や水槽での育て方は?
ガラス瓶やガラスケース、水槽などの密閉した容器では、お部屋の中で年中15~25℃を維持しながら、容器内を多湿環境にして育ててください。湿度は70~90%を目安とします。
ガラス瓶や水槽で育てる場合、以下2通りの管理方法があります。
- 2~3号のプラ鉢を容器に入れる
- 容器内に直接植え付ける
容器に鉢ごと入れる場合は、容器の底にベラボンやソイルを敷き詰めておくことをおすすめします。余分な水分を吸水してくれて、空気中に効率よく水分を放出してくれて湿度管理がしやすくなるためです。
直接植え付ける場合は、鉢底に根腐れ防止効果のある「ケイ酸塩白土」「ゼオライト」などを敷いてください。直接植え付ける場合、根が水に浸ってしまい根腐れする危険があるので、水やり管理には注意が必要です。
テラリウムとして別の植物と植えても大丈夫?
同じ多湿環境を好む植物であれば大丈夫です。例えば、コケやセラギネラ、根茎性ベゴニアなどは、テラリウム内で一緒に寄せ植えができます。
湿度70~90%を維持しながら、明るい環境で育てましょう。ただし、成長するスピードは異なるため、伸びすぎて形が崩れてきたら定期的に剪定してください。
伸ばしっぱなしにすると、成長が遅い株は光が当たらなかったり蒸れの影響を受けたりします。全体のバランスを見ながら、定期的に剪定しながら管理しましょう。
まとめ
ルディシア トリカラーは、緑葉に入るピンクの差し色と繊細な白い葉脈が特徴のジュエルオーキッドです。トリカラーの名前通りに、成長に伴って3色の色合いを楽しめます。
ルディシア ディスカラーの変種なので初めての方も育てやすく、最初のジュエルオーキッドとしておすすめです。美しい葉姿はプレゼントとしても喜ばれます。
湿度を維持しながら管理すれば、比較的育てやすい植物です。大きめのガラス容器がお家にある方は、容器内に入れるだけで簡単に育てられるでしょう。
インテリアとしてもおしゃれなので、気になる方はぜひチャレンジしてみてはいかがですか。
[https://andplants.jp/collections/jewelorchidludishiatricolar]