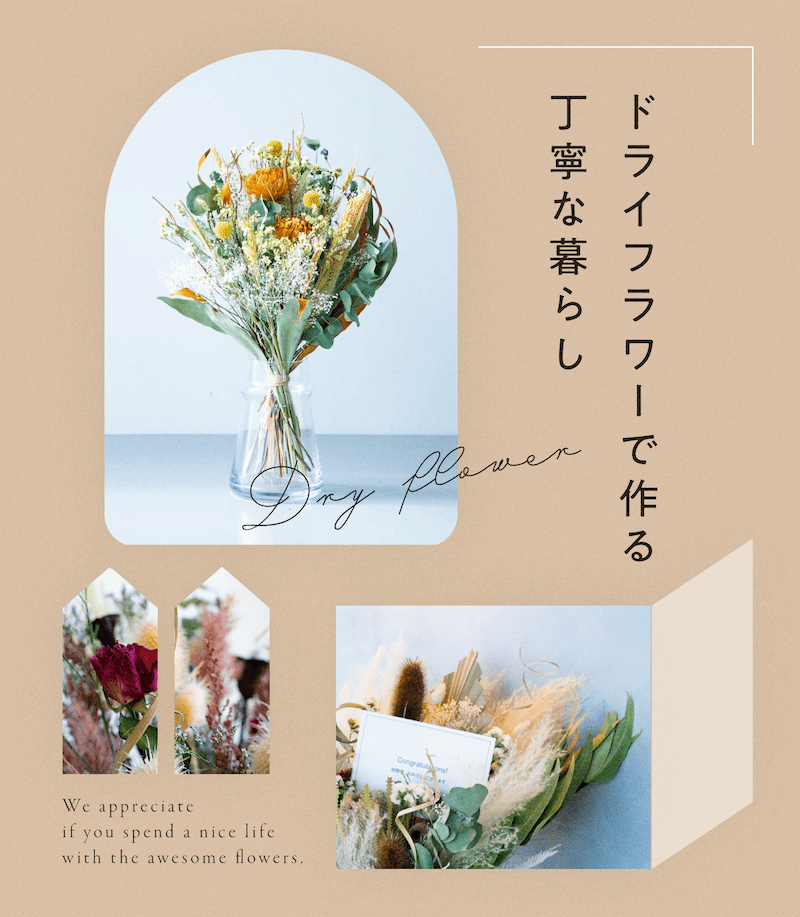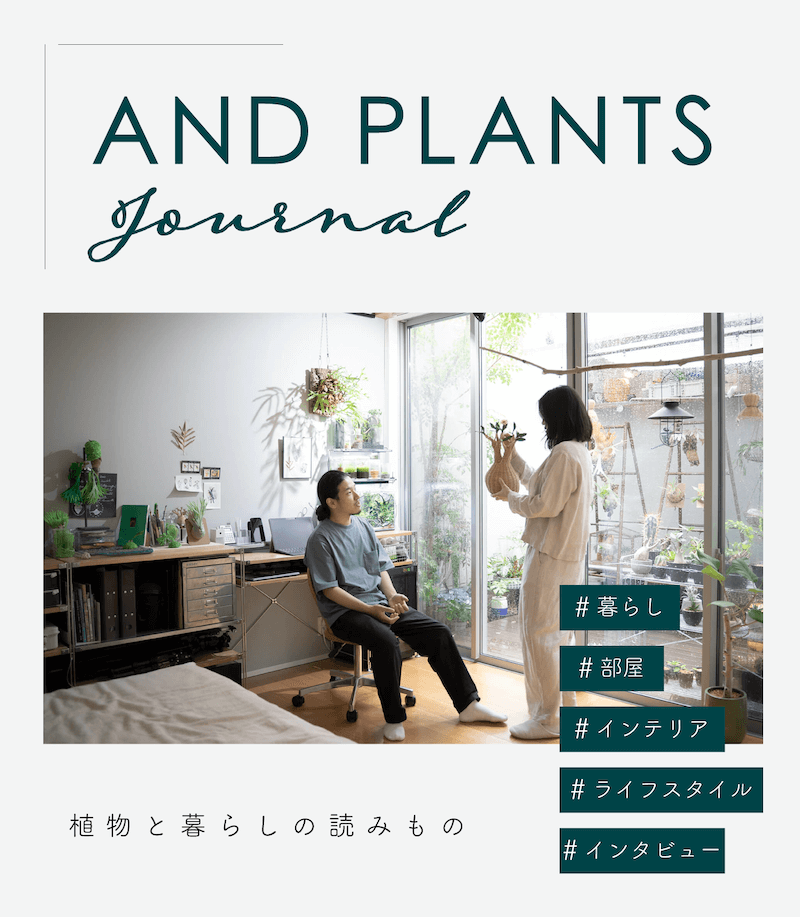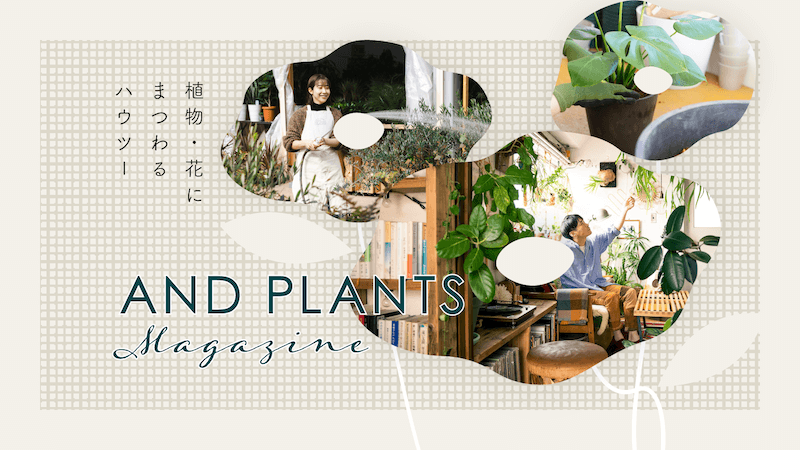故人の冥福を祈り遺族を慰めるため、葬儀に合わせて贈る供花。しかし、突然の訃報に、供花の贈り方や相場などを迷う方も少なくありません。
最近では、家族葬で香典を辞退するケースも多く、供花を贈っていいのか悩ましい場面もあるでしょう。
また、供花を贈る際は、タイミングや名札の書き方などに決まりがあるため、マナーを知っておくことも大切です。
筆者は遺族側で供花の取りまとめをしたことがありますが、葬儀社の担当の方に聞いたり自分で調べたりと大変でした。
そこで今回は、供花を贈るときの相場やマナーを解説します。宗教による違いや注意点も紹介しているので、供花について疑問や不安がある方は、ぜひ参考にしてください。
[https://andplants.jp/collections/offering-flower]供花とは
供花は、お通夜やお葬式のときに供えるフラワーアレンジメントです。故人や喪主と関わりのある方や会社などの団体が、故人の冥福を祈り遺族を慰めるために贈ります。
遠方に住んでいる方や、事情により葬儀に参列できない方が、お悔やみの気持ちを伝えるために贈ることもあります。
読み方と数え方
供花は「きょうか」「くげ」と読みます。数え方は、次のとおりです。
- 単位は「基」
- 1基、2基と数える
- 2基で1対(1セットのこと)となる
かつては1対で贈ることが一般的でしたが、規模の小さな葬儀や家族葬も増え、1基で贈ることも珍しくなくなりました。
数え方を知っていないと、「1」という数字だけを見て、「1基」のつもりが「1対」で注文してしまう方もいるので注意しましょう。
お通夜と告別式で祭壇横に飾るもの
供花は、お通夜と告別式のときに祭壇の横に飾られます。アレンジメントの上か下に、送り主の立札(芳名札)がついているのが一般的です。
故人や喪主との関係性や付き合いの深さによって、1対や2対で贈る場合もあれば、1基のみのケースもあります。
ユリや菊、トルコキキョウなど、お供えに適したお花が使われますが、故人や喪主の希望によっては、故人の好きだったお花を入れることも可能です。
色は白だけとは限らず、優しいピンクや紫、黄色などが入ることもありますが、宗教によっても異なります。
故人や遺族との関係性で並ぶ順番が決まる
供花は飾る順番が決められているため、贈るときに故人や遺族との関係性を伝えることが必要です。祭壇が中央にあり、一番近いところから家族、親族、関係者へと続きます。
左右対称に並べていきますが、贈るのが1基でも問題ありません。祭壇の右側上段が一番目になり、二番目が左側の上段、次に右といったように左右交互で並べていくため、1基でも1対でも差し支えないからです。
供花の種類

供花は、金額や選ぶスタイルによって、基本的には次の4パターンになります。
- スタンドフラワー
- アレンジメント
- 盛籠
- 花祭壇に加えることもある
葬儀会社や花屋によって、それぞれにさらにランクがあり、デザインや金額、使うお花などが異なります。
スタンドフラワー
供花の中で、一番サイズが大きいものがスタンドフラワーです。背の高いスタンド台の上に、アレンジメントを設置します。
立札は供花の上、もしくはスタンド台に下げるスタイルです。後ろからも見やすく、豪華な葬儀ではスタンドフラワーが両側にびっしり並ぶこともあります。
アレンジメント
アレンジメントは、スタンド台に載せずに、そのまま祭壇の並びに置くスタイルです。立札は供花の上に立てます。
スタンドフラワーより、一般的には金額が安いです。しかし、小さな葬儀場や自宅での葬儀の場合、スペースの都合からスタンドフラワーではなく、アレンジメントを飾ることもあります。
盛籠
盛籠は、フルーツやジュースなどを盛った籠を、造花で装飾したものです。盛籠を贈るのは血縁者が一般的ですが、ほかの関係者が贈ってはいけないわけではありません。
一般的には、故人の子ども一同でスタンドフラワーを、孫一同で盛籠をといったように、身内の間でバランスを考えて決めることが多いです。
生花祭壇に加えることもある
故人や遺族の希望によっては、両側に供花を置かず、生花祭壇の一部としてお花を加えるケースもあります。
生花祭壇とは、全体を生花でデザインしたオリジナルの祭壇のことです。一般的な祭壇は木で作ったもので、こちらにも花を飾れますが、デザインの自由度は低くなります。
供花を生花祭壇に加える場合は立札がないため、斎場内に送り主の名前を列記した「芳名版」を設置するのが一般的です。
また、供花の費用は不祝儀袋に入れて、「御花代」として渡します。キリスト教で使う「御花料」とは異なるので、間違えないように注意しましょう。
供花の手配の方法

次に、供花の手配について解説します。手配の方法は、次の3つです。
- 葬儀社に依頼する
- 花屋に依頼する
- インターネットで依頼する
それぞれ、手配するときの流れも含めて解説します。
葬儀社に依頼する
供花は、葬儀社に依頼すれば用意してもらえます。葬儀を行う葬儀社であれば、祭壇や宗教、宗派に合った供花を設置してくれるので安心です。
基本的にはプランが決まっているため、故人や遺族との関係性から適切なものを選んで注文します。
葬儀社であれば、故人や遺族の希望も理解しているので、手配もスムーズです。また、お通夜が始まる数時間前というぎりぎりのタイミングでも、対応してくれる可能性が高いでしょう。
葬儀社に依頼するときの流れ
葬儀社に供花を依頼するときは、次のような流れになります。
- 喪家に葬儀の日程や葬儀社、斎場を確認する
- 葬儀社に連絡し、供花を注文したいと伝える
- 葬儀の日時、喪家の名前、斎場名を伝える
- 供花のプランを決める
- 故人や喪主との関係性、立札に記入する名前などを伝える
喪家が供花を取りまとめている場合は、喪家に注文内容を伝えます。葬儀社へは、喪家からまとめて注文してもらう流れです。
花屋に依頼する
一般の花屋に、供花を依頼することも可能です。花の種類が豊富なので、故人の好きなお花や雰囲気を取り入れて作ってもらうことができます。
ただし、どの花屋でも大丈夫というわけではありません。事前に、次の3点を確認してから注文することが重要です。
- 斎場が外部の花屋の供花を受け付けてくれるか
- 供花の制作に対応しているか
- 配達を行ってくれるか
斎場が外部の花屋の納品を受けてくれるか
葬儀社によっては、提携の花屋以外からの供花を受け付けていないところもあります。
そのため、花屋に注文する前に、外部からの供花を受け付けてくれるか、葬儀社への確認が必要です。
供花の制作に対応しているか
一般の花屋に依頼するときは、供花の注文に対応してくれるかを確認しましょう。
葬儀のマナーに精通していて、適切な供花を制作してくれる花屋でないと、遺族や斎場に迷惑をかけてしまうかもしれません。
配達を行ってくれるか
斎場に配達してくれるかどうかも確認しましょう。指定の日時に、間違いなく届けてもらえるかどうかが重要です。
花屋に供花を依頼するときの流れ
花屋に供花を依頼するときは、次のような流れになります。
- 喪家に葬儀の日程や葬儀社、斎場を確認する
- 葬儀社に連絡をし、花屋から供花を届けてもいいか確認する
- 良ければ、供花のスタイルや宗教など必要事項を聞く
- 花屋に供花の注文をする
- 日時や喪家の名前、斎場、立札の名前など必要事項を伝える
インターネットで依頼する
最近では、インターネットで供花を手配することも可能です。配達可能時間や設置方法、お花の種類や宗教の確認など、葬儀社とのやりとりを代行してくれるところもあります。
インターネット注文のメリットは、掲載された商品から選べること。ほかにも、弔電と一緒に注文できるなど利便性も高いです。
また、インターネットで注文する際も、指定の斎場が外部からの納品を受け付けてくれるかを確認する必要があります。
インターネットで依頼するときの流れ
- 喪家に葬儀の日程や葬儀社、斎場を確認する
- 葬儀社に連絡をし、花屋から供花を届けてもいいか確認する
- 良ければ、供花のスタイルや宗教など必要事項を聞く
- インターネットで商品を選び、必要事項を入力し注文する
- 注文確定の連絡があれば手配完了
供花を手配するときのマナー

供花を贈るときは、マナーもよく確認しておきましょう。注意点は、次の3つです。
- 先方に供花を贈ってもよいか確認する
- お通夜に間に合うように贈る
- 喪家や周囲と連携を取る
マナーから外れたことをしてしまうと、贈り先の遺族や周囲にも迷惑をかけてしまいかねません。
喪家に供花を贈ってもよいか確認する
供花の手配を進める前に、喪家に供花を贈ってもよいか確認しましょう。
連絡をせずに一方的に贈るのはマナー違反です。家族葬などの葬儀スタイルによっては、供花を辞退されるケースもあります。
供花はもともと1対で贈るのがマナーでしたが、最近では小規模な斎場や家族葬も増え、1基で贈ることも珍しくありません。斎場の広さによっては、各自1基のみの受付となっていることもあります。
お通夜に間に合うように贈る
一般的な葬儀は、お通夜と告別式を2日に渡って行います。そのため、お通夜が始まるときには、すでに供花が飾ってあるのが望ましいです。
できればお通夜当日の午前中、遅くともお通夜が始まる3時間前には届くように手配しましょう。
お通夜に間に合わなかった場合は、お通夜が終わってから、もしくは告別式当日の1~2時間前までに届けば飾ってもらえます。
喪家や周囲と連携を取る
供花を贈るときは、喪家や葬儀社、関係者と連携を取りましょう。
喪家によっては、親族が取りまとめをすることもあります。また、友人一同や会社から贈る場合などは、確認不足による手配ミスや、連絡の行き違いによる二重手配なども。
筆者も家族の葬儀で供花を取りまとめたことがありますが、葬儀社の担当の方とやり取りをして、順番を決めたり立札をチェックしたりとバタバタしました。
葬儀は短い期間で手配しなければならないため、どうしても慌ただしくなります。間違いや失礼があると迷惑をかけてしまうので気を付けましょう。
供花の相場と贈る立場ごとの芳名札の書き方

葬儀は、しめやかに執り行われるもの。祭壇や供花も、統一感を持たせて作られていることが一般的です。
そのため、供花の値段は、葬儀によっては一律で決められていることもあります。また、誰から贈られたか分かるように、立札をつけるのがマナーです。
ここでは、供花の相場と贈る立場ごとの芳名札の書き方を、次の項目に分けて解説していきます。
- 一基の値段は7,000円~15,000円が相場
- 親族(兄弟、子ども、孫など)が贈る場合
- 親戚が贈る場合
- 個人で贈る場合
- 友人同士で贈る場合
- 会社や団体から贈る場合
- 家族葬の場合
一基の値段は7,000円~15,000円が相場
供花の相場は、一基が7,000円~15,000円です。一対で出す場合は、倍の値段になります。
金額は、故人や喪主との関係性、一基か一対のどちらで贈るかにもよるでしょう。一般的には、提示されたプランから選ぶケースが多いです。
強い思いがあって、相場より高い金額で供花を贈りたいと考える方もいるでしょう。しかし、相場を超える金額の供花は、かえって遺族に気を遣わせてしまいます。
迷惑をかけないように、相場に合わせた供花を贈るのもマナーです。
親族(兄弟、子ども、孫など)が贈る場合
供花につける立札は、故人との関係性ごとに書き方のマナーがあります。親族の場合、故人の兄弟や子ども、孫が世帯で贈る場合は
- 〇〇家一同
同じ立場の方たちが合同で贈る場合は
- 兄弟一同
- 子供一同
- 孫一同
となります。また、夫婦で贈る場合は夫(世帯主)の名前のみを記載するのが一般的です。
親族の代表者が取りまとめることが多いため、一律で同じ値段の供花を選ぶことがほとんどです。一基ずつか一対にするかは、斎場の広さや他から贈られてくる供花の数にもよります。
親戚が贈る場合
近しい身内以外の親戚が供花を贈る場合も、世帯で贈る場合は「〇〇家一同」となります。夫婦で贈る場合は、夫(世帯主)の名前のみです。
訃報を受け取ったら喪家に連絡を取り、取りまとめをしている方がいれば、その方と相談して決めるとよいでしょう。
供花の値段も、親族と合わせることで統一感が保たれるだけでなく、金額に対して遺族が気を遣いすぎずにすみます。
個人で贈る場合
個人で供花を贈る場合は、フルネームで記載します。故人や遺族と仕事上のかかわりがある場合は、次のような記載が一般的です。
- 会社名
- 会社名、役職、氏名
- 会社名、氏名
友人同士など複数人で贈る場合
友人同士など複数人で贈る場合、3名くらいまでなら連名で記載しても差し支えありません。それ以上だと文字が見にくくなってしまうので、注意が必要です。
連名は、書く順番にもマナーがあります。年齢や役職が上の方から、右から左への順に記載してもらいましょう。
友人同士などで上下関係がないときは、どの順番でも問題ありません。通常は、五十音順で右から記載することが多いです。
大勢で贈る場合は
- 友人一同
- (グループやサークル名)一同
と記載します。
会社や団体から贈る場合
故人や遺族が勤めている会社や、所属している団体から供花を贈る場合は
- 会社または団体名
- 会社または団体名、代表者の役職、代表者の氏名
- 会社または団体名、(部署やグループ名)一同
と記載します。
会社名や団体名は略さずに、正式名称を記載するのが基本です。しかし、あまり長くなる場合は、(株)や(有)など略しても差し支えありません。
また、葬儀の芳名札は縦書きのみなので、英語表記の場合はカタカナで書くのが一般的です。
家族葬の場合
家族葬は、家族や親族のみ、もしくはごく親しい人を含めた少人数で行う、小規模な葬儀のこと。最近では、家族葬専門の葬儀社や斎場も増えています。
家族葬でも、供花の相場は変わりません。しかし、スペースに限りがあるため、一対ではなく一基でと決められている場合もあります。
また、基本的に供花を贈るのは参列者のみです。葬儀に招待されていない方は、供花を贈るのを遠慮しましょう。かえって、お返しなどで遺族に気を遣わせてしまいます。
お花を贈りたいのであれば、後日お供えのお花を自宅に贈るとよいでしょう。
宗教ごとの供花の違い

葬儀のスタイルは仏式が多いですが、ほかにも神式やキリスト式などがあります。供花に使うお花の種類や色などは、宗教や地域によっても異なるので注意が必要です。
ここでは、次の4つの項目に分けて解説します。
- 仏式
- 神式
- キリスト式
- その他
仏式
日本の葬儀は、仏式が8割と言われています。筆者自身も、遺族や参列者として出席した葬儀はすべて仏式でした。
お花の色は白が基調ですが、白ばかりだと寂しく見えてしまうので、淡いピンクや紫、黄色など複数の色が入っていることが多いです。
| 供花のスタイル |
|
| 色 |
|
| 主に使うお花 | ユリ、菊、コチョウラン、デンファレ、トルコキキョウ、カーネーション、カスミ草など |
| 注意点 |
|
神式
神式の際の供花は、仏式とほぼ同じでかまいません。かつては榊を飾る風習がありましたが、現在は生花が一般的です。
| 供花のスタイル |
|
| 色 |
|
| 主に使うお花 | ユリ、菊、カーネーション、トルコキキョウ、カスミ草など |
| 注意点 |
|
キリスト式
キリスト教では、葬儀を行う教会ではなく、故人や喪主の自宅に供花を贈るのが一般的です。枕元に供えた後、葬儀に合わせて教会に運び、祭壇に飾ります。
そのため、運びやすい籠盛りのアレンジメントが主流です。
| 供花のスタイル |
|
| 色 |
|
| 主に使うお花 | ユリ、カーネーション、トルコキキョウ、カスミ草など |
| 注意点 |
|
その他
京都や大阪、名古屋などの一部地域では、お花の代わりにしきみ(樒)を飾るところもあります。
しきみは、香りが強く毒性を持った植物です。本来、仏式では香りや毒のあるお花はタブーですが、特定の地域や宗派では、しきみを飾るのが一番丁重だとされています。
しきみは、仏教と深いかかわりがあり、強い香りと毒性によって邪気を払い、故人を守ってくれると考えられているからです。
筆者自身はしきみを飾る葬儀に参列した経験はありませんが、名古屋の花屋にいたときは、しきみの問合せをいただくこともありました。
しきみを使った供花は、扱っているところが限られます。贈りたいときは、喪家や葬儀社に確認するとよいでしょう。
供花を贈るときの注意点

供花は、マナーどおりに贈れば問題ないとは限りません。ほかにも贈る際に気を付けることがあるので、次の4つの注意点をチェックしておきましょう。
- 贈るタイミングが早すぎるのはNG
- 間に合わない場合は後日自宅に贈る
- お花の種類や色は故人や遺族の意向に合わせる
- 香典や供花を辞退している場合は無理に贈らない
これらの気遣いをすることで、故人を悼み遺族に寄り添う気持ちや、意思を尊重したい思いが伝わりますよ。
贈るタイミングが早すぎるのはNG
供花を贈るときは、届くタイミングに注意しましょう。お通夜の当日に届くよう手配するのがマナーです。
訃報を受け取ってすぐに贈るのは「事前に準備していた」と受け取られるので、故人や遺族に失礼にあたります。
また、早く贈りすぎると祭壇の設置がまだだったり、季節によっては花が傷んできてしまったりもするからです。
間に合わない場合は後日自宅に贈る
供花の手配が葬儀に間に合わなかった場合は、後日自宅にお供え花を贈りましょう。無理に供花を贈って、葬儀中や葬儀後に届いてしまったら、遺族に迷惑をかけてしまいます。
贈るお花は、自宅に飾りやすいアレンジメントや胡蝶蘭がおすすめです。最近では、手間のかからないプリザーブドフラワーを贈る方も増えています。
相場は5,000円~10,000円くらいです。あまり高額だと、遺族を困惑させてしまうので注意しましょう。
お花の種類や色は故人や遺族の意向に合わせる
葬儀に故人の好きだったお花を贈りたいと考える方もいるでしょう。しかし、供花は、受け取る遺族の気持ちを考えて贈るのが大切です。
葬儀に飾るお花は、宗教や宗派によって種類や色が限られています。一方で、最近では家族葬が増えたことから自由度が上がり、故人の好きなお花で祭壇を彩るケースも少なくありません。
あくまで故人や遺族の意向次第なので、喪家や葬儀社に確認して判断しましょう。
香典や供花を辞退している場合は無理に贈らない
家族葬では、香典や供花を辞退するケースも少なくありません。知り合いの訃報を知って供花を贈りたいと思っても、辞退を伝えられたら素直に受け入れて遠慮しましょう。
お花だけでもと思ったとしても、故人や遺族の気持ちを尊重することが優先です。差し支えなければ、自宅にお供えのお花を贈ってもいいか確認し、後日手配するとよいでしょう。
供花以外に贈るお花の種類

故人の逝去に伴い贈るお花は、供花だけではありません。ここでは、次の3つの供花以外のお花について解説します。
- 花輪(花環)
- 枕花
- 献花
ほかの種類も知っておくことで、間違いを防いだり、状況によって選んだりできますよ。
花輪(花環)
花輪は、生花や造花を使い丸くアレンジしたもので、斎場の入り口に飾られることが多いです。専用の土台の上に置き、花輪の下には芳名札を付けます。
供花と同じく、故人の関係者が贈るものです。色は、白や黒、紫、緑などの落ち着いた色が中心になります。
家族葬や小規模な斎場が増えたことで、花輪を飾ることも少なくなりました。
枕花
枕花は、故人が亡くなってすぐに枕元に飾る花のことです。贈るのは、故人や遺族と縁の深かった方のみになります。
お通夜が始まるまで枕元に置き、ご遺体と一緒に祭壇へ移動させるため、小ぶりな籠のアレンジメントで用意します。
献花
献花は、主にキリスト教の葬儀で行われる風習です。仏式の焼香と同じように、一人ずつ棺や祭壇にお花を供えていきます。
供花はお悔やみを伝える意味があるのに対し、献花は故人との別れを伝える意味を持ちます。献花は喪主が用意するので、参列者が用意する必要はありません。
お別れ会や偲ぶ会に供花を贈りたいとき

葬儀は家族葬で済ませ、後日お別れ会や偲ぶ会を行うこともあります。特に、著名な方や 会社の代表の方などに多いです。
お別れ会や偲ぶ会に供花を贈る場合、要点は次の3つになります。
- 手配の方法は葬儀と同じ
- 主催者の意向に沿ったものを選ぶ
- 規模やスタイルによってはお花代徴収形式もあり
手配の方法は葬儀と同じ
お別れ会や偲ぶ会への供花の手配方法は、基本的には一般的な葬儀と同じです。まずは、主催者や会場に連絡を取り、供花を贈ってもいいか確認しましょう。
遺族の希望によっては、テーマや雰囲気を決めていることもあります。統一感を出すために、サイズやお花の種類、色などの指定をされるケースもあるので、確認せずに贈るのはNGです。
主催者の意向に沿ったものを選ぶ
お別れ会や偲ぶ会は、スタイルに決まりがありません。宗教や宗派の決まりどおりに進める葬儀と異なり、進行や演出も自由に組み立てられることが特徴です。
場所も斎場とは限らず、ホテルの宴会場で行うケースもあります。お別れ会や偲ぶ会にテーマとなる趣向があるなら、それに合わせた供花を選びましょう。
規模やスタイルによってはお花代徴収形式もあり
お別れ会や偲ぶ会では、全体を花で埋め尽くす花祭壇や特別なデザインを取り入れているケースもあります。デザイン重視の場合は、お花代徴収形式もありです。
贈られた供花を飾るのではなく、祭壇に使うお花の費用としてお花代を徴収します。確認せずに供花を贈ってしまうと、飾ってもらえないこともあるので注意しましょう。
供花についてのよくある質問

最後に、供花についてのよくある質問について紹介していきます。
- 参列する場合に供花と香典を両方贈ってもいいの?
- 供花を贈るときの親族はどこまでを含むの?
- 葬儀が終わったら供花はどうなるの?
参列する場合に供花と香典を両方贈ってもいいの?
供花と香典を両方贈っても問題ありません。
供花は、より深いお悔やみの気持ちを伝えるもの。故人や遺族と浅からぬ関係であれば、供花と香典の両方を贈ることで、遺族の気持ちも慰められるでしょう。
供花を贈るときの親族はどこまでを含むの?
一般的に、供花を贈る親族は次の関係性の方になります。
- 故人の配偶者や子ども、孫などの直系の親族
- 故人の兄弟姉妹
- 故人の祖父母
- 故人の叔父叔母やいとこ
それ以外にも、故人が親戚づきあいをしていた方は、親族として供花を贈っても差し支えありません。
しかし、ごく身内での家族葬で、葬儀に招かれていない場合は遠慮しましょう。
葬儀が終わったら供花はどうなるの?
供花は、出棺前に棺に入れることが多いです。斎場のスタッフが花を抜き参列者に渡してくれるので、棺の中にお別れの気持ちを込めて入れていきます。
残った分は花束にまとめ、参列者にお礼として配られるのが一般的です。
まとめ

供花は、葬儀に際し、故人の冥福を祈り遺族にお悔やみの気持ちを伝えるために贈るお花です。立札をつけ、祭壇の両側に故人や喪主と関係の深い方から並べていきます。
冠婚葬祭はマナーが多く、マナー違反は相手を不快にさせてしまうこともあるので、供花を贈るときも注意が必要です。
この記事では、供花の相場や贈るときのマナー、注意点などについて詳しく解説してきました。
突然の訃報を受け取ったときも、慌てずに記事の内容を参考にして、心からのお悔やみと共に適切な供花を贈りましょう。
[https://andplants.jp/collections/offering-flower]