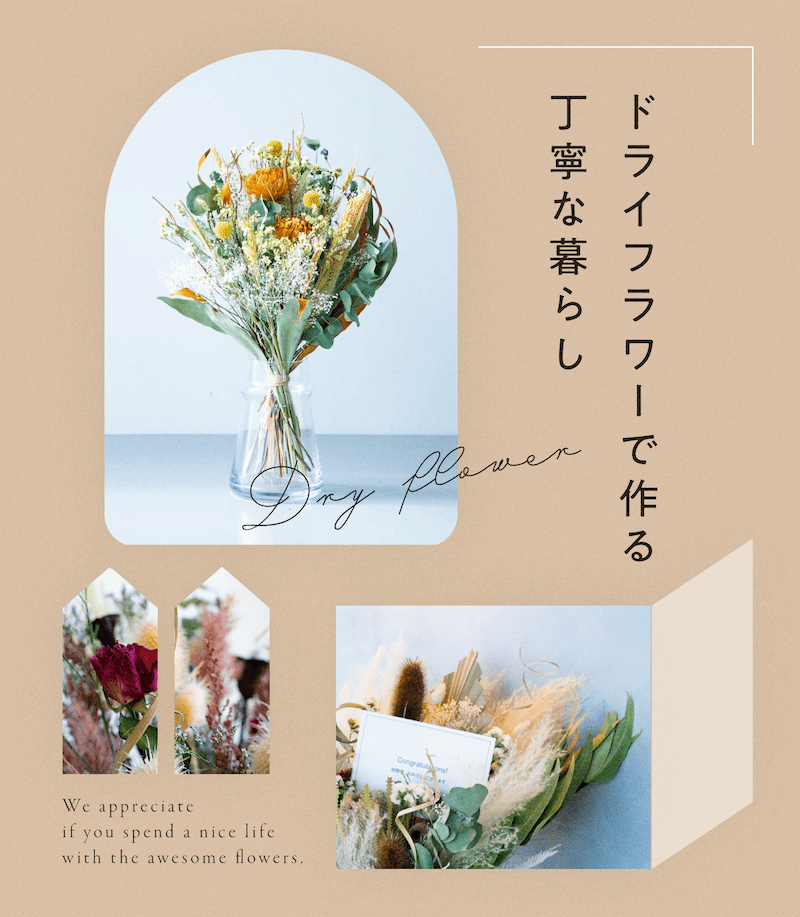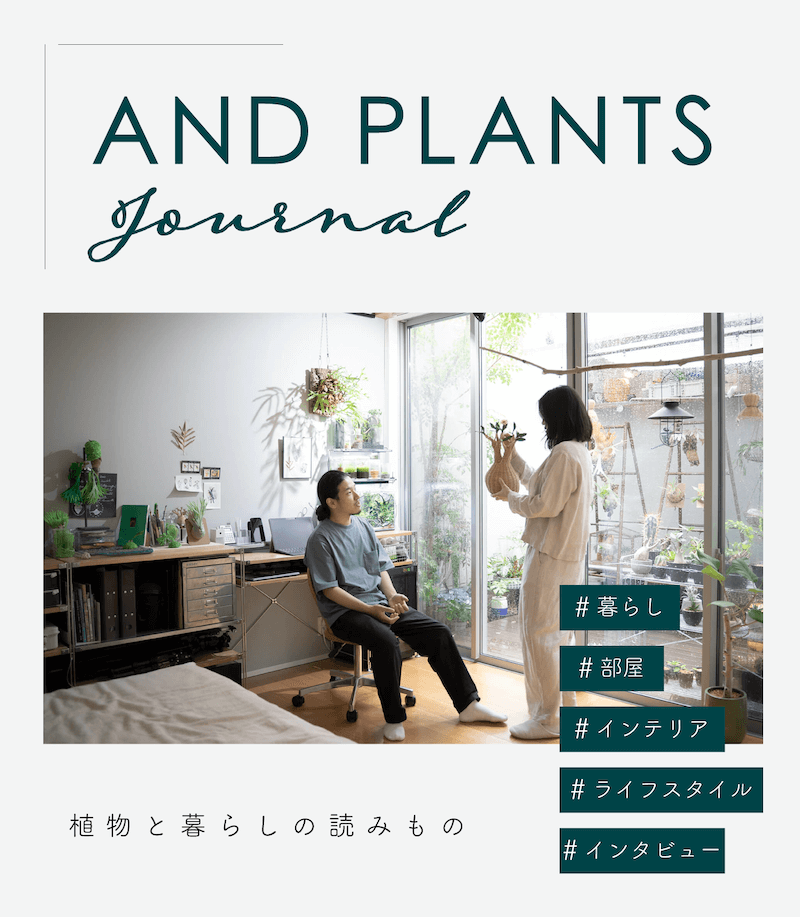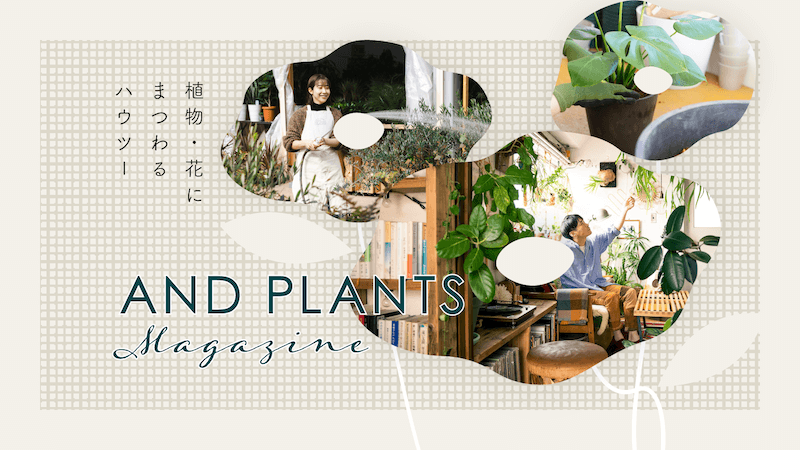| 植物名 | カランコエ |
| 学名 | Kalanchoe |
| 英名 | Kalanchoe |
| 科目/属性 | ベンケイソウ科カランコエ属 |
| 原産地 | アフリカ、マダガスカル |
| 日当たり | 日当たりの良い置き場所 |
| 温度 | 最低10℃以上をキープ |
| 耐寒性 | 弱い |
| 耐暑性 | 強い |
| 水やり | 春秋:手で土を触って水分を感じなくなったら(鉢の中央部分までしっかり乾いてから) 夏冬:手で土を触って水分を感じなくなって(鉢の中央部分までしっかり乾いてから)一週間後 |
| 肥料 | 緩効性肥料、液体肥料 |
| 剪定時期 | 5月~9月 |
カランコエの特徴
カランコエは、ベンケイソウ科カランコエ属の種類豊富な多肉植物です。大まかに花を楽しむタイプと多肉質な葉を楽しむタイプに分かれます。
花を楽しむタイプには、花の形や色が異なる品種が豊富です。主に鉢花として人気があります。
多肉質な葉を楽しむタイプは、葉の形や色、大きさに違いがあります。強健な性質で、他の多肉植物と寄せ植えしても丈夫に育つ点からも人気です。
葉を楽しむタイプであっても花は楽しめますが、葉や茎が乱れやすい点には気を付けましょう。どちらのタイプのカランコエも、湿気に弱い性質があります。
梅雨~夏の時期は、水管理や風通しに注意して育ててください。湿度や水のやりすぎにさえ気を付ければ、初めてお部屋に迎える方にもおすすめです。
カランコエの種類
カランコエは、改良品種も含めると、世界中に200種類以上あるとされています。ここでは、特徴的な多肉質な葉が人気のカランコエを紹介します。
福兎耳やファング、仙人の舞の多肉質な葉は、細かな毛で覆われており、フェルト生地のような質感が人気です。

デザートローズは秋~冬にかけて赤く紅葉します。子宝ベンケイソウは、葉の縁に無数の子株が生える品種です。子株が付くと、フリルがかって見える可愛らしい姿になります。

花を楽しむタイプのカランコエであれば、ブロスフィルディアナやクィーンローズなどが人気です。園芸店や花屋さん、雑貨屋さんでも、可愛い鉢とセットで花が咲いている状態で販売されています。
カランコエの花言葉
カランコエの花言葉は「幸福を告げる」「あなたを守る」「たくさんの小さな思い出」などです。カランコエ属に共通する花言葉になります。
花言葉「幸福を告げる」は、ベル型の花を咲かせる品種から付けられたとされています。「あなたを守る」は、厳しい環境でも強く育つ性質や開花期が長い特徴が由来です。
花言葉「たくさんの小さな思い出」は、小さな花が集まって咲く姿が由来とされています。
「幸福を告げる」の花言葉は、新築祝いや開店祝い、結婚祝い、出産祝いなどに贈るプレゼントにぴったり。「あなたを守る」の花言葉はパートナーへ告白や記念日に贈るプレゼントにおすすめです。
「たくさんの小さな思い出」の花言葉は、友人の誕生日祝いや母の日、父の日、敬老の日などに贈ると、これまでの思い出を感じさせてくれます。
感動的なプレゼントにしたい場合は、ぜひカランコエの花言葉を伝えてください。
カランコエの風水
カランコエの風水効果は、「金運」を高めるとされています。風水では葉が丸い植物は「金」の気を循環させるとされ、金運に効果的と考えられているためです。
金運を高めたい方は、西側に置くと商売繁盛をもたらすとされています。開店祝いや開業祝い、移転祝いなどでプレゼントする場合は、西側に置いてもらうように伝えると喜ばれるでしょう。
ただし、風水効果を十分に得るためには、置く場所を整理整頓して、カランコエを元気に育てることが重要です。
また、多肉植物は種類ごとに風水効果が異なると言われています。「多肉植物の風水」の記事では、特徴別の風水効果や置き場所について紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
カランコエの育て方
 カランコエは、初めて植物をお部屋に迎える方にも育てやすい多肉植物です。しかし、上手に育てるためには、押さえておきたいポイントがあります。
カランコエは、初めて植物をお部屋に迎える方にも育てやすい多肉植物です。しかし、上手に育てるためには、押さえておきたいポイントがあります。ポイントは、以下の5つです。
- 置き場所と日当たり
- 温度
- 水やりの頻度
- 肥料
- 剪定方法
関連記事:多肉植物の育て方
置き場所と日当たり
カランコエは日当たりと風通しのよい環境を好みます。ただし、真夏の直射日光に当たると葉焼けする可能性がある点には注意してください。
ほとんど日光の光が入らないような暗すぎる場所では生育できません。葉色が悪くなったり葉が薄くなったり、徒長してひょろひょろになったりします。
「日光があまり当たらない場所に置いていたら、ひょろひょろになった」と言われることが多い多肉植物です。そのため、基本的にカランコエは屋内よりも屋外で育てましょう。
しかし、原産地に比べ日本の冬は寒すぎるため、冬は屋内管理がおすすめです。屋内で管理する場合は、冷え込む窓から距離をとって、明るい場所で育ててください。
温度
カランコエは寒さに弱い植物です。最低10℃以上をキープして育ててください。
水やりを控えることで5℃程度まで耐えられますが、0℃以下の寒さに当たり続けると凍結によって枯れる恐れがあります。気温が下がり始める晩秋には室内に移動させてください。
カランコエは夏型の多肉植物ですが、春秋型に近い性質も持ち合わせています。そのため、春~秋に生育して冬に休眠する性質です。
日本の夏は湿度が高いため、なるべく涼しく風通しがよい場所で管理してください。屋内で管理する場合は、冷暖房の当たらない明るい場所に置きます。
冷暖房の風が直接当たると、急な乾燥によって葉がポロポロと落ちやすいので、注意してください。
水やりの頻度
カランコエの水やりを季節別に大まかに紹介します。
- 春秋:手で土を触って水分を感じなくなったら(鉢の中央部分までしっかり乾いてから)
- 夏:手で土を触って水分を感じなくなって1週間後
- 冬:月に1回程度で十分
春と秋の生育期は、手で土を触って水分を感じなくなったら(鉢の中央部分までしっかり乾いてから)、鉢底から水が流れるくらいにしっかり行ってください。
カランコエは夏も生育期ですが、梅雨に入るタイミングで徐々に水やりを控えましょう。高温多湿環境で水やりしすぎると、腐る恐れがあります。
カランコエを育てていて、夏に溶けるように枯れる方は、水やりする頻度が多すぎるかもしてません。乾燥気味に管理しましょう。
手で土を触って水分を感じなくなって1週間後に水やりする程度です。気温の低い冬は、常に暖房で暖かい部屋に置いていない限りは、休眠しています。
基本的に、月に1回の水やりで十分です。冬の水やりは、気温の高い時間帯に常温または35℃程度の温いお湯で与えると、根に負担がかかりません。
もし、生育期の水やりタイミングが掴めない場合は、水やりチェッカーを使うとパッと一目でわかります。水やりで失敗する方は、ぜひ使ってみてください。
[https://andplants.jp/products/watering_checker_sustee_large_single]肥料
生育期に2か月に1度置き肥を置くか、水に薄めた液肥を2週間に1度のペースで水やり代わりに与えてください。夏の生育が緩慢な時期や冬の休眠期には、肥料は与えません。
カランコエは、肥料が少なくても十分に育ちますが、葉を大きくしたり群生させたりしたい場合は土に混ぜ込んだ元肥以外にも追肥もしましょう。ただし、肥料の与えすぎは根を傷めるため、与えるペースや時期はしっかり守ってください。
[https://andplants.jp/products/evo_solid_fertilizer_for_green]剪定方法
カランコエの剪定時期は5月~9月です。枯れた葉を取り除いたり伸びた茎や花茎を切り戻したりします。
葉が茂っていて、枯葉が取り除きにくい場合は、ピンセットで丁寧に取り除くとよいでしょう。日当たり不足によって株が徒長した場合は、葉の隙間から茎を切ります。
切り取ったカランコエは葉挿しや挿し木で増やすことも可能です。葉を楽しむタイプの多くは、株姿を崩しながら花茎をまっすぐ伸ばします。
姿形を崩したくない方は、花茎が伸び始めたら、すぐに剪定した方が良いでしょう。花を楽しみたい方は花が咲き終わったら、花茎の根元付近で剪定してください。
[https://andplants.jp/products/sakagen-flower-shears]カランコエの増やし方

カランコエの増やし方には、以下の3つの方法があります。
- 挿し木
- 葉挿し
- 種
カランコエは、剪定した茎を土に挿して増やす「挿し木」で増やすことが可能です。剪定した茎の断面を乾かした後に、土に挿すと数日後に発根します。
また、茎ではなく葉を土に挿す「葉挿し」でも増やせます。葉挿しで増やす場合は、葉の付け根が傷ついていると発根しにくいので、葉を茎からとる時には注意してください。
カランコエは花が咲くため、開花後は種子が収穫できます。収穫した種子は、暖かい春に種まきすると、芽を出します。
種から育てた株を「実生株(みしょうかぶ)」と言いますが、実生株は親株とは違う性質が現れることが特徴です。
カランコエの増やし方の手順や注意点については、「多肉植物の増やし方」の記事でも、詳しく紹介しています。
カランコエのよくあるトラブルと対処法

種類が豊富で人気のあるカランコエですが、トラブルも存在します。
ここではトラブルが起きたときの対処法を解説していきます。あらかじめ対処法を知っておけば、いざ何かあっても安心です。
主なトラブルは以下の3つです。
- 根腐れ
- 根詰まり
- 葉焼け
それぞれ詳しく見ていきましょう。
根腐れ
根腐れでは、以下の症状が見られます。
- 水をあげても元気にならない
- 土がなかなか乾かない
- 葉が落ちやすい
- 葉が茶色・黄色に変色している
- 幹や幹の根元が柔らかい
- 土から腐敗臭がする
- 土の表面にカビが生えている
- 根が黒く変色している
根腐れは、土の中の酸素濃度が低下して土中の細菌叢が変化し、有機物の腐敗が進むことで有害なアンモニアが発生し、土壌環境が悪くなることで発症します。
また、常に土が湿っている状況では根が呼吸することができず、細胞が死んでしまいます。
これが原因で、根から水を吸い上げることができなくなり、植物体に水を供給することができなくなることで死んでしまう現象です。
根腐れの対処法は以下の通りです。
- 鉢から植物を抜き、悪い土を落として水はけのよい土に交換する
- 根の傷んでいる部分、腐っている部分をカットする
- 少量の水を与え、風通しがよく明るい日陰で管理する
※1週間を目安に水が乾くコンディションで管理する - 発根剤を与えてみる
- 傷んだ葉を取り除く
- 枯れた枝を切り取る
根腐れが起こった場合は、鉢を入れ替えて土の環境を変えることが大切です。傷んでしまった根は取り除き、健康な状態が取り戻せるような環境を与えてあげましょう。
赤玉土・ゼオライトなどを用土に混ぜ込むことで、水はけと根腐れを防止することができます。
葉先がダメになっている場合は、生きている部分までカットし、新しい葉を出すことで回復させます。根元から腐っている場合は、無事な部分で切り取り、挿し木にして発根させて回復させましょう。
根腐れが起こると枝が垂れ、新芽を残すために古い葉を落とす現象が見られます。重度の根腐れの場合は、新芽や枝の先から枯れることがあるので注意が必要です。
カランコエは土の多湿状態が長く続くと、根腐れしやすい特徴があります。小さな株ほど根腐れが生じると、あっという間に枯れやすいです。
日頃から風通しと水やりに注意して育ててください。
根詰まり
根詰まりとは、鉢の中で根がいっぱいになることで起きる症状。根詰まりの症状は以下の通りです。
- 水が浸透しづらくなる
- 底から根が出てくる
- 葉が黄色くなる
特に春夏の成長期で一気に伸びてしまうと上記のような症状が起きてしまいます。すぐに枯れる要因にはなりませんが、放置してしまうとカランコエに悪影響です。
対処法はカランコエの植え替えをすること。
カランコエを現在の鉢より1つ上の大きい鉢に植え替えることで、上記の症状はほとんど解消されるでしょう。植え替えを行う時期も春夏の成長期が最も適しています。
葉焼け
葉焼けでは、以下の症状が起きます。
- 葉の色素が抜けて白くなっている
- 葉の一部が茶色く枯れている
真夏の強い日差しを浴びすぎると葉が傷んで「葉焼け」というトラブルが発生します。
葉焼けの症状に気がついたら、早めに置き場所を移動させてください。
対処法は以下の通りです。
- 直射日光が当たっている場合はカーテンや寒冷紗などで遮光する
- 葉焼けした部分はカットする
葉焼けが起こるということは、日光が当たりすぎている可能性が高いため、直射日光に当てないような措置を取りましょう。
また、一度焼けてしまった葉は二度と元に戻りません。傷んだ葉はカットし、新しい健康な葉が生えてくるのを待ちましょう。
葉焼けは、暗い場所から急に直射日光が当たる場所へ移動させた際にも起こるトラブルです。「暗いお部屋で徒長したから、屋外の直射日光に当てたら葉焼けした」といった例はよくあります。
日頃から直射日光や明るさには注意しておくと安心です。
カランコエの害虫トラブルと対処法

花が咲くタイプや多肉質な葉を楽しむタイプ、どちらにも害虫トラブルは存在します。
カランコエに発生しやすい害虫トラブルは、以下の4つです。
- ハダニ
- アブラムシ
- カイガラムシ
- コバエ
害虫によるトラブルが発生したときの対処法を解説していきます。あらかじめ対処法を知っておけば、いざ何かあっても安心です。
ハダニ
ハダニの症状は以下の通りです。
- 葉にクモの巣のような糸がついている
- 葉の裏に小さな虫がついている
- 葉に斑点や傷がある
- 葉の色がかすれたように薄くなり枯れている
ハダニは繁殖力の強さと、薬剤耐性を持つ非常に厄介な害虫です。
放っておくと糸を張って大量発生する危険性もあるので、早めに対処を行いましょう。
対処法は以下の通りです。
- 傷んだ葉はカットする
- 葉の表裏、付け根や茎も水で洗浄する
- ハダニに効果のある液体を噴霧する(殺虫剤のほか、2倍に薄めた牛乳、重曹と水を混ぜたもの、濃いコーヒー、10倍に薄めた酢でも一定の効果あり)
ハダニが湧いてしまったら、市販の殺虫剤(ベニカXファインスプレー・オルトラン)の使用が効果的です。ただし、薬剤散布は使用回数を守らないと、美しい葉に黒点が付いたり株が弱ったりするため、注意してください。
2倍に薄めた牛乳などの液体を噴霧する対処法もありますが、匂いが気になる方には水で洗い流す方法もおすすめです。
そもそもハダニは、こまめな霧吹き・葉をふき取りきれいにすることを怠らなければ発生しません。
常にきれいな状態を保つために、霧吹きの購入は必須といえます。月に一度はシャワーで洗い流すなどの管理も必要です。
冬の水やり頻度が少ないカランコエは、乾燥した冬にハダニが発生しやすいです。冬は暖かい時間帯に霧吹きをしたり、湿った布やテッシュで葉を拭いたりする予防もしておきましょう。
アブラムシ
アブラムシの症状は以下の通りです。
- 新芽が萎縮している
- 葉が縮れている
- 新芽に虫が付いている
- 葉や幹がベタベタしている
アブラムシは繁殖力が強いため短期間で増え、ウイルスを媒介する厄介な害虫です。
放っておくとカランコエの生育が弱まり枯れる恐れもあるので、早めに対処を行いましょう。
対処法は以下の通りです。
- 縮れた葉はカットする
- アブラムシを取り除く
- 茂り過ぎている枝葉は剪定して風通しをよくする
- アブラムシに効果のある液体を噴霧する(殺虫剤のほか、2倍に薄めた牛乳、重曹と水を混ぜたもの、濃いコーヒー、10倍に薄めた酢でも一定の効果あり)
アブラムシが湧いてしまったら、市販の殺虫剤(ベニカXファインスプレー・オルトラン)を使用すると効果があります。ただし、薬剤散布は使用回数を守らないと、美しい葉に黒点が付いたり株が弱ったりするため、注意してください。
2倍に薄めた牛乳などの液体を噴霧する対処法もありますが、匂いが気になる方には水で洗い流す方法もおすすめです。
カイガラムシ
カイガラムシの症状は以下の通りです。
- 貝殻のような殻を被ったり、粉状の物質で覆われたりしている虫が枝葉についている
- 黒いカビ(すす病)が発生している
- 葉や幹がベタベタしている
カイガラムシは繁殖力の強さと薬剤耐性のある厄介な害虫です。
放っておくとカランコエの生育が弱まり枯れる恐れもあるので、早めに対処を行いましょう。
対処法は以下の通りです。
- 柔らかい布やブラシで擦り取り除く
- 茂り過ぎている枝葉は剪定して風通しをよくする
- カイガラムシに効果のある液体を噴霧する(殺虫剤のほか、2倍に薄めた牛乳、重曹と水を混ぜたもの、濃いコーヒー、10倍に薄めた酢でも一定の効果あり)
カイガラムシが発生したら、市販の殺虫剤(ベニカXファインスプレー・オルトラン・スミチオンなど)を使用するのが効果的。ただし、薬剤散布は使用回数を守らないと、美しい葉に黒点が付いたり株が弱ったりするため、注意してください。
カイガラムシの成虫には殺虫剤が効きにくいので、幼虫の時期である5~7月に使用するとよいでしょう。
既に貝殻をかぶっている成虫は、柔らかいブラシや布で擦り取ってください。
葉が細かなカランコエにカイガラムシが増えると、対処が非常に難しいです。日頃のお手入れの際に、カイガラムシが付いていないかどうか確認して、見つけ次第すぐに駆除するようにしてください。
コバエ
コバエの症状は以下の通りです。
- 土に虫が湧く
- コバエが植物の周囲を飛んでいる
コバエ自体は植物に無害ですが、観葉植物を育てるうえでは不快害虫です。
放っておくとコバエは増えていくので、早めに対処を行いましょう。
対処法は以下の通りです。
- 発酵不十分な堆肥や有機質肥料を与えることをやめる
- 土上2~3㎝を取り除き、新しい土に植え替える
- 土の表面に無機質な素材(赤玉土・鹿沼土・砂利など)を敷く
- トラップを仕掛ける
- コバエに効果のある殺虫剤を噴霧する
コバエが発生したら、市販の殺虫剤(ベニカXファインスプレー・オルトラン・スミチオンなど)を使用するのが効果的です。ただし、薬剤散布は使用回数を守らないと、美しい葉に黒点が付いたり株が弱ったりするため、注意してください。
コバエのトラップは食器用洗剤やお酢、めんつゆなどで作ることができます。植物の近くに置いておくと、簡単にコバエを捕殺できるでしょう。
コバエは、発酵不十分な腐葉土やバーク堆肥、有機質肥料の匂いに引き寄せられます。
そのため、有機質肥料を取り除いたり土の表面に赤玉土や鹿沼土など3~5㎝程度敷き詰めたりするとコバエ発生を防ぐことが可能です。
そもそもコバエは、完熟たい肥を使用した質のよい土であれば発生しません。また、土が常に湿っている状況を避ければ、発生する可能性は低いです。
コバエを発生させないためには、適切な土と水やり管理で育ててください。
カランコエの育て方に関してよくある質問

最後にカランコエの育て方に関してよくある質問とその答えを以下にまとめました。
- カランコエは室内・屋外どちらを好む?
- カランコエがひょろひょろになる原因は?
- カランコエの花が終わった後の育て方は?
- カランコエの葉が落ちるのはどうして?
- カランコエは地植えできる?
それでは具体的に見ていきましょう。
カランコエは室内・屋外どちらを好む?
カランコエは、屋外を好む多肉植物です。日当たりと風通しの良い環境ほど、よく育ちます。
ただし、真夏の直射日光は葉焼けの原因になるので、夏の時期は室内でレースカーテン越しの光に当てたり明るい日陰で管理したりしてください。また、温度は10℃以上をキープして育てる必要があるため、冬は室内に移動させましょう。
暗い室内に置くと徒長しやすいため、もし春~秋の生育期も室内で管理する場合は、なるべく窓際の明るい場所に置いてください。
カランコエがひょろひょろになる原因は?
カランコエがひょろひょろになる原因は、「日当たり不足」「水のやりすぎ」が考えられます。
日当たりを好む多肉植物なので、暗い場所では徒長してひょろひょろになりやすいです。室内であれば、窓際の明るい場所で管理してください。生育期であれば、屋外に置いても問題ありません。
また、カランコエは土が常に湿っているほど、水をやりすぎている場合は徒長しやすいです。さらに、株元が腐る根腐れにもなりやすいので、土の状態を見て水やりしましょう。
カランコエの花が終わった後の育て方は?
カランコエの花が終わった後は、花茎を剪定して通常通りに育てます。
花が咲き終わったからと言って、特別に育て方は変わりません。特に花を楽しむタイプは、花茎を切り取るだけでよいでしょう。
多肉質の葉を楽しむタイプは、花を咲かせると株姿が乱れやすいため、花茎を剪定しても元の姿にならないかもしれません。花が咲く前の姿を再び楽しみたい方は、挿し木や葉挿しをして小さな株から育てなおした方がよいかもしれません。
カランコエの葉が落ちるのはどうして?
カランコエの葉が落ちるのは、「水切れ」「日当たり不足」「冷暖房の直風」などが考えられます。
乾燥に強いカランコエですが、春~秋の生育期に水切れを何度も経験させると、葉がポロポロと落ちます。季節に合った水やりを心がけてください。
カランコエは、日当たり不足でも葉が落ちます。暗い場所では光合成が十分にできないため、古い葉から順番に落ちていきます。
夏や冬に室内に置くと、場所によっては冷暖房の直風が当たる場合もあるかもしれません。冷暖房の直風が当たると、葉から水分が奪われて乾燥して落ちます。
室内で管理する場合はエアコンの乾いた風が直接当たらないようにしてください。
カランコエは地植えできる?
カランコエの地植えはおすすめしません。多湿を嫌い、寒さにも弱い多肉植物なので、四季のある日本では地植えは難しいでしょう。
長雨が続く梅雨の時期に地植えしていると、根腐れをして枯れやすいです。また、10℃以下の気温になる冬では、寒さで枯れます。
花を楽しむタイプであっても多肉質な葉を楽しむタイプであっても、鉢植えで管理してください。
カランコエのまとめ
カランコエは日当たりと風通しのよい環境であれば、春秋は屋外でも簡単に育てることができます。夏は明るい日陰やレースカーテン越しの窓際、冬は暖かい室内の明るい場所で育ててください。
花言葉「幸福を告げる」は開店祝いとして、「あなたを守る」の花言葉はパートナーに贈るプレゼントとして最適です。金運を高めるとされている風水効果は、多くの方に喜んでもらえます。
さまざまな葉の形や色、質感を持つカランコエを、ぜひ育ててみてはいかがでしょうか。
[https://andplants.jp/collections/kalanchoe]