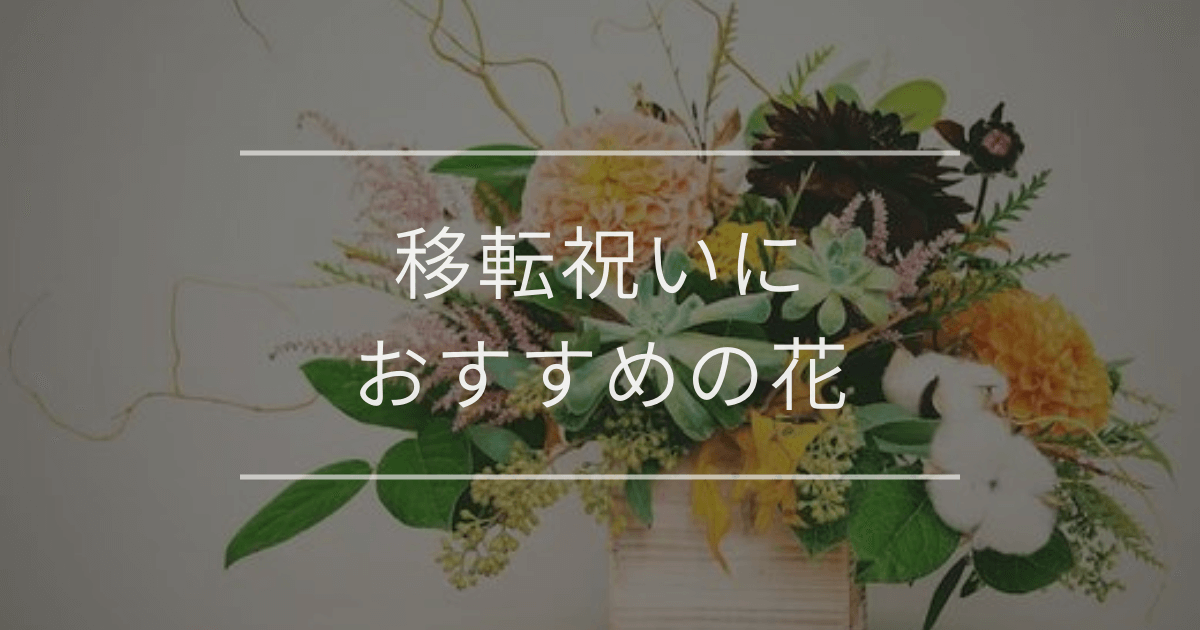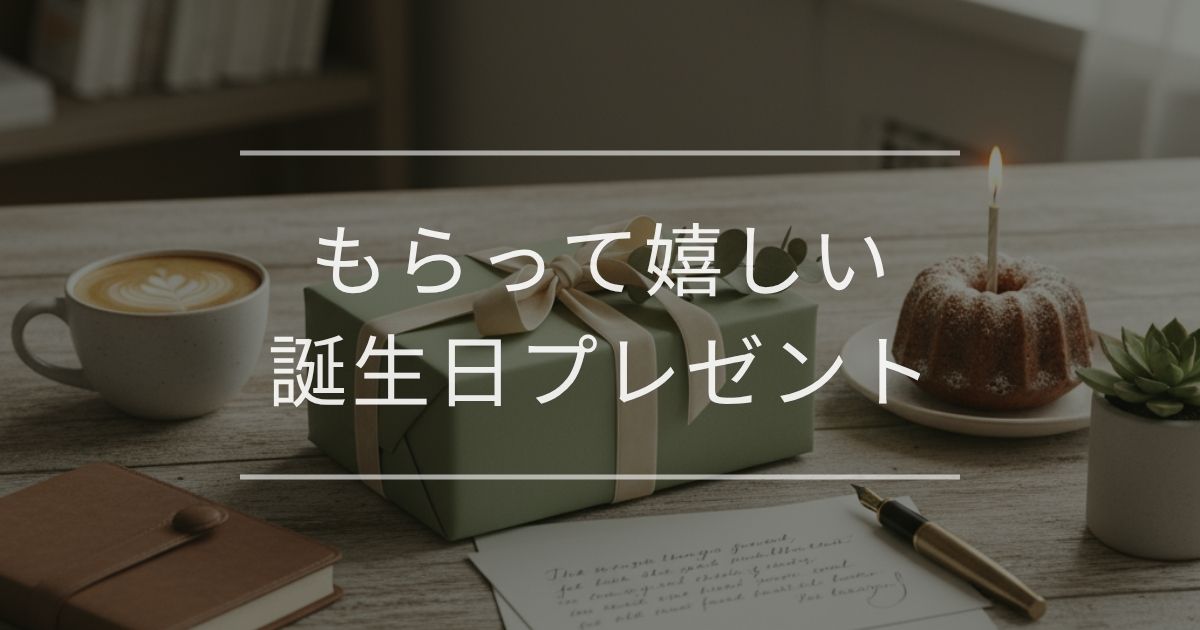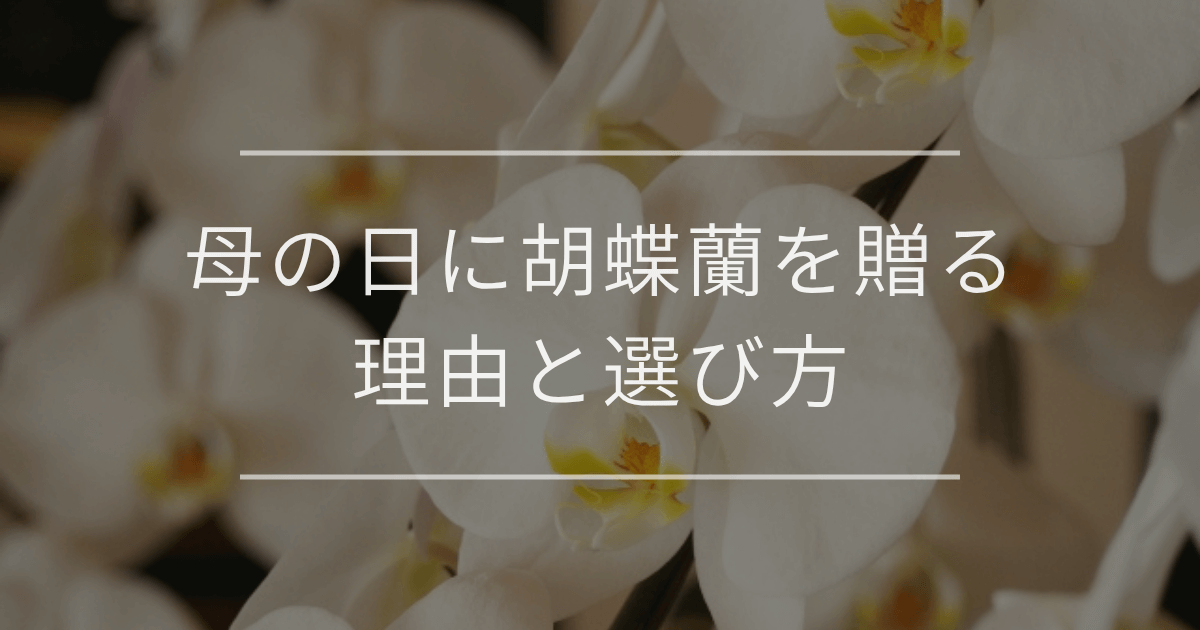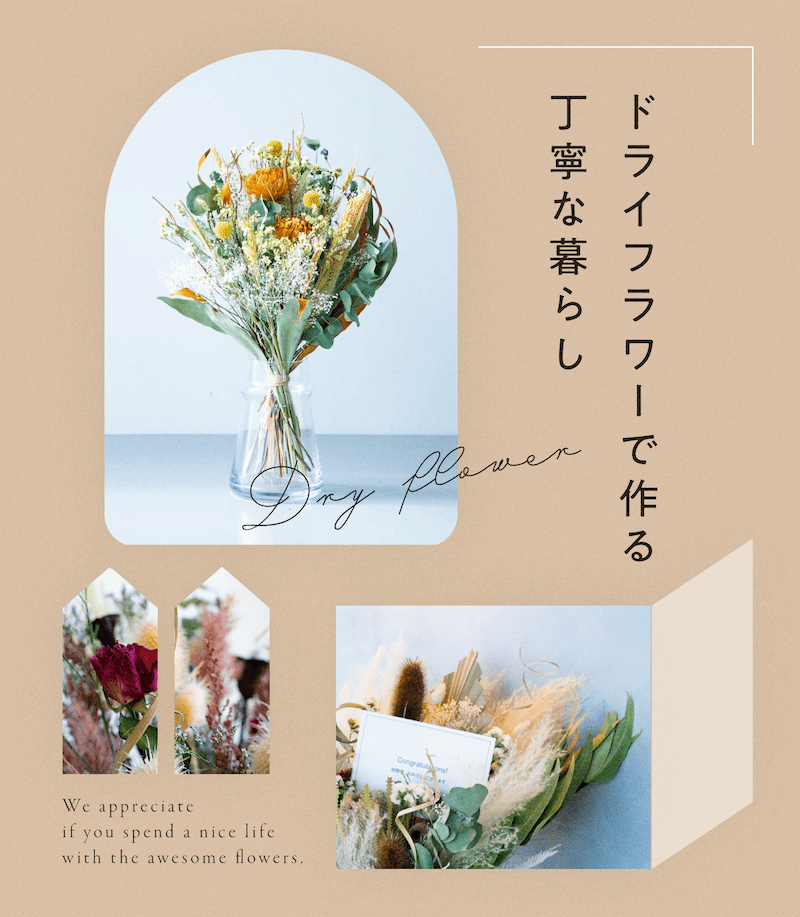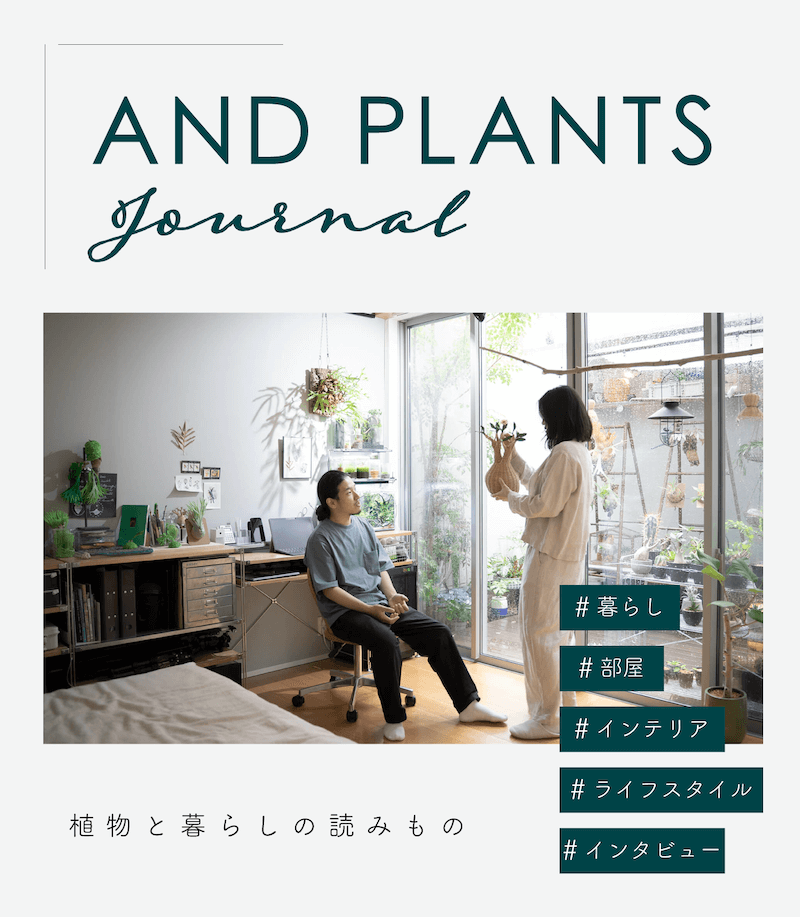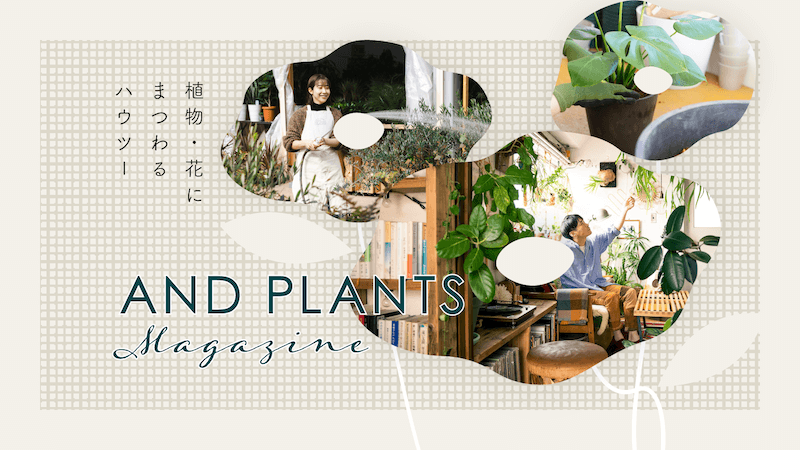| 項目 | 詳細 |
| 植物名 | タコノキ |
| 学名 | Pandanus boninensis |
| 英名 | screwpine |
| 科目/属性 | タコノキ科タコノキ属 |
| 原産地 | アフリカ、オーストラリア、太平洋諸島 |
| 日当たり | 日当たりの良い場所 |
| 温度 | 最低10℃以上をキープ |
| 耐寒性 | 弱い |
| 耐暑性 | 強い |
| 水やり | 春夏:手で土を触って水分を感じなくなったら(鉢の中央部分までしっかり乾いてから) 秋冬:土が乾いて1週間程度あけてから |
| 肥料 | 緩効性肥料、液体肥料 |
| 剪定時期 | 5月~10月 |
タコノキをすぐにチェックしたい方は、下記をクリックすると商品一覧に移ります。
[https://andplants.jp/collections/screwpine]タコノキの特徴
タコノキは、成長に伴い幹からタコの足のように気根を四方八方に伸ばす植物です。その他に、らせん状に付く葉やとげとげしいボール状の果実などの特徴もあります。

雌雄異株(しゆういかぶ)であるため、果実を収穫するには雄木と雌木が必要です。熟した果実は食用としても利用されます。
タコの足のように広がる気根が大きな特徴ですが、細長い葉が広がる姿はスタイリッシュな印象を与えます。おしゃれな南国の雰囲気を演出したい時におすすめです。
日当たりの良い環境を好むため、室内で管理する場合は日当たりの良い窓際で育ててください。高温多湿にも強いので、暑い夏でも育てやすいです。
ただし、寒さには弱いため、冬は暖かい室内で管理しましょう。
タコノキの育て方

ここでは、タコノキの基本的な育て方を5つのポイントに分けて紹介します。
- 置き場所と日当たり
- 温度
- 水やりの頻度
- 肥料
- 剪定方法
タコノキの育て方の確認前に、幹から気根が伸びている姿が気になる方は以下をクリックしてみてください。
置き場所と日当たり

タコノキは日当たりの良い環境を好む植物です。ただし、真夏の直射日光に当たり続けると葉焼けする可能性があります。
室内の窓際で直射日光が当たる場合は、レースカーテンやシェードなどで光を和らげて育ててください。冬以外を屋外で管理する場合は、真夏の時期は明るい日陰に移動させておくと安心です。
暗すぎる環境に置くと、葉はシャキッとせずに枝垂れてしまいます。また、葉色が薄くなり、見た目も悪くなるので注意してください。
日光を非常に好む性質から冬は日当たり不足になりやすい傾向があります。冬時期の室内が暗くなりやすい方は、植物育成用LEDライトを利用して光を補うと安心です。
AND PLANTSでは、太陽光に近い波長を使用した「バレル 植物ライト(TSUKUYOMI 10W ホワイト)」を取り扱っています。ライトスタンドを併せて使うと、インテリアとしてもおしゃれに育てられるでしょう。
[https://andplants.jp/products/tsukuyomi-10w]温度

タコノキは寒さに弱いため、最低10℃以上をキープして育ててください。生育温度は15~25℃です。
屋外で管理している方は、気温が下がり始める晩秋には室内へ移動させましょう。暖かい室内であっても、窓際の場合は屋外の寒さの影響を受けやすいです。
窓から30~40㎝ほど距離を取っておくと安心して冬越しできます。暑さには比較的強い植物ですが、30~35℃以上の夏の高温に当たり続けると枯れる可能性があります。
サーキュレーターやエアコンなどの空調で、高温になりすぎないように気を付けましょう。屋外で管理している方は、夏だけは風通しの良い涼しい日陰に移動させておくと安心して夏越しさせられます。
水やりの頻度

タコノキの季節ごとの大まかな水やり頻度は以下の通りです。
- 春夏:手で土を触って水分を感じなくなったら(鉢の中央部分までしっかり乾いてから)
- 秋冬:土が乾いて1週間程度あけてから
春夏の生育期は、手で土を触って水分を感じなくなったら(鉢の中央部分までしっかり乾いたら)水やりしてください。ただし、受け皿に水を溜めたままにしておくと根腐れの原因になるため、溜まった水はこまめに捨てましょう。
気温が下がり始める秋は、土の乾き具合を確認しながら徐々に水やり間隔を調整します。冬の水やり頻度は、土が乾いて1週間程度あけてから与える程度です。
ただし、室温が常に15℃以上の場合は、緩やかに成長し続けます。冬の室温を一定に保っている場合は、土の乾き方には注意してください。
基本的に、寒い冬に水やりしすぎると凍結や根ぐされのトラブルが発生しやすいです。季節に応じた水やりが苦手な方は、水やりチェッカーの利用をおすすめします。
パッと一目で土の乾燥具合を確認できるため、気温や成長具合、鉢の大きさによる水やり間隔による悩みが少なくなるでしょう。
[https://andplants.jp/products/watering_checker_sustee_large_single]肥料

タコノキには、生育期の5月~7月、9月~11月それぞれに1度置き肥を置くか、水に薄めた液肥を2週間に1度のペースで水やり代わりに与えてください。真夏と冬は生育が緩慢なので、肥料は与えません。
葉の緑色や艶をより良くしたい方は、元肥とは別に上記タイミングでの追肥をおすすめします。生育期に葉をぐんぐん出す植物です。
肥料が少なくなりすぎると、葉色が薄くなりやすいため、ぜひ生育期に肥料を与えてください。
AND PLANTSでは、オリジナル肥料「アンドプランツ 植物を元気にする固形肥料」を取り扱っています。土の上に置くだけでも使えて、混ぜれば元肥としても活用できるので、肥料に困っている方はぜひ使ってみてください。
[https://andplants.jp/products/andplants_fertilizer]剪定方法

タコノキの剪定は、枯れた下葉を切る程度です。新陳代謝で黄色くなったり、病害虫で枯れたりした葉などを幹の付け根部分で切り取ります。
幹に残った葉は、自然と枯れ落ちるので、無理して取り除く必要はありません。無理に引っ張って枯葉を取り除こうとすると、株が傷むので気を付けましょう。
AND PLANTSでは皇室献上品でもある、新潟県三条市の100年企業・株式会社坂源のハサミ「Sakagen Flower Shears」を取り扱っています。剪定で綺麗な樹形を作るには、切れ味の良いハサミが欠かせません。
軽くて切れ味抜群の使いやすい剪定ハサミを使って、タコノキの姿形をぜひ整えてみてください。
[https://andplants.jp/products/sakagen-flower-shears]タコノキの増やし方

タコノキは、5月~7月に挿し木や株分けで増やします。簡単な手順は以下の通りです。
挿し木
- 支柱根より上の伸びすぎた幹を切る
- 容器に溜めた水に浸けて1時間ほど吸水させる
- 葉を半分ほど剪定する
- 肥料の入っていない土に挿す
- 乾燥しないように明るい室内で管理する
- 発根して新芽が出てきたら植え替える
タコノキは、10号鉢以上の大きな鉢に植えるほどの大株になると、株元から子株が出てくることがあります。子株が出てきたら、気根が伸びるまで待ってください。
気根が付いた状態で切り分けると、植え替え後の生育が良いです。
タコノキは幹が太いため、大株であるほど剪定ハサミでは切り取れないことがほとんどです。ノコギリを使って剪定すると、作業がやりやすいでしょう。
また、株分け以外に種まきでも増やせます。もしインターネットや自生地の1つである沖縄または小笠原諸島などで手に入れることができれば、ぜひ種まきからも育ててみてください。
タコノキのよくあるトラブルと対処法

暑さに強く育てやすいタコノキですが、順調に育っていてもトラブルが発生する場合があります。ここではよくあるトラブルと対処法を解説していきます。
タコノキによくあるトラブルは以下の4つです。
- 根腐れ
- 根詰まり
- 葉焼け
- 葉が赤くなる
対処法を知っておくと、いざトラブルが起きても安心して対処できます。それぞれ見ていきましょう。
根腐れ
タコノキの根腐れでは、以下の症状が見られます。
- 株がグラグラする
- 葉が茶色・黄色に変色している
- 葉が枝垂れている
- 葉先が枯れている
- 幹や気根が柔らかく黒ずんでいる
- 土から腐敗臭がする
- 土の表面にカビが生えている
- 根が黒く変色している
根腐れは、土の酸素濃度が低下して土壌環境が悪くなることで発症します。また、土が常に湿っていると、根は呼吸できずに枯れてしまい、根自らが腐る症状でもあります。
根腐れの対処法は以下の通りです。
- 土の乾湿サイクルが早くなるように、1回り小さな鉢に植え替える
- 古い土を落として新しいものに交換する
- 根の傷んでいる部分、腐っている部分をカットする
- 風通しがよく明るい日陰で管理する
※1週間を目安に水が乾くコンディションで管理する - 発根剤を与える
- 傷んだ葉・ポロポロと落ちる葉はすべてを取り除く
- 殺菌剤に浸す
根腐れが起こった場合は、植え替えをして土の環境を変えることが大切です。傷んでしまった根は取り除き、健康な根が伸びる状態にしてください。
ケイ酸塩白土・ゼオライトなどの根腐れ予防効果のある土壌改良材も新しい用土に混ぜ込むと、より根腐れしにくくなります。タコノキは水はけのよい土を好む植物です。
植え替えに使用する土は、水はけのよい観葉植物用の土を使うようにしましょう。
根腐れの症状や具体的な対処法が気になる方は、「観葉植物の根腐れ」の記事を参考に対処してみるのもおすすめです。
根詰まり
根詰まりとは、鉢の中が根でいっぱいになることで起きる症状のことです。
タコノキは根詰まりすると、以下のような症状が見られます。
- 新芽が出てこなくなる
- 葉色が全体的に薄くなる
- 下葉からポロポロと落ち始める
根詰まり自体は、すぐに枯れる原因にはなりません。しかし、生育スピードが遅くなり、徐々に元気をなくしていくので注意が必要です。
対処法は、植え替えです。
5月~7月、または9月~11月に、土を優しくほぐして根を傷めないように植え替えます。株の大きさにもよりますが、1回り大きな鉢への植え替えで十分でしょう。
あまりにも根がガチガチに固まっている場合は、細い棒で突いたり水を張ったバケツ内で根鉢を揺らしたりして土を落とします。
急に大きな鉢に植え替えると、根腐れする原因になるので気を付けましょう。5号鉢であれば6号鉢に、大きくても7号鉢以内の大きさに留めてください。
植え替えするだけで、根詰まりが引き起こす上記の症状は解決します。
タコノキの根詰まりの見分け方がはっきりとわからない場合もあるかもしれません。そんな場合は「観葉植物の根詰まり」の記事を参考にして判断してみてください。
葉焼け
タコノキが葉焼けすると、以下の症状が出てきます。
- 葉先が茶色くなる
- 葉が黒く焦げたようになる
強い日差しを浴びすぎると、葉が傷んで「葉焼け」のトラブルが発生します。葉焼けの症状に気がついたら、直射日光を避けるように対策してください。
対処法は以下の通りです。
- 置き場所を変える
- レースカーテンやシェードなどで遮光する
- 葉焼けした葉は取り除く
葉焼けのトラブルが起きる場合、強い直射日光が当たりすぎている可能性が高いです。直射日光を弱めたり、置き場所を移動したりしてください。
株全体が強い直射日光で枯れていなければ、日差しの対処をすれば自然と新芽が出てきます。葉焼けした葉は、元には戻らないので、株全体のバランスを見ながら切り取ってください。
葉先だけが黒く葉焼けしている場合は、全体のバランスが悪くならないように葉先だけを剪定すると、葉姿がスカスカになりません。
葉焼けは太陽光によって細胞が壊されて起きる症状です。葉焼けが起きた際の対処法や起こさせない予防法について気になる方は、「観葉植物の葉焼け」の記事も併せてチェックしてみましょう。
葉が赤くなる
タコノキを育てていると、葉が赤くなるトラブルが起きることがあります。考えられる原因は、主に以下の2つです。
- 寒さ
- 真夏の直射日光
タコノキは南国の植物であるため、寒さに弱いです。10℃以下の寒さに当たり続けると、寒さから身を守るためにアントシアニンを生成して葉を赤くすることがあります。
また、アントシアニンは紫外線から葉を守る役割もあるので、真夏の直射日光に当たりすぎている場合に、生成されることも。真夏に葉が赤くなるのは、葉焼けの一歩手前の状態なので注意してください。
葉が赤くなる対処法は、以下の通りです。
- 冬は暖かい室内で育てる
- 真夏の直射日光には当てない
冬~早春の時期に葉が赤くなる場合は、寒さが原因です。暖かい室内へ移動させましょう。次第に葉の色は緑色に戻っていきます。
タコノキは本来、南国の直射日光を浴びながら生育しますが、鉢植えと自生地では環境が異なります。日光を好む植物ではありますが、葉が赤くなるほどの強い直射日光に当たっている場合は、明るい日陰に移動させてください。
タコノキの害虫トラブルと対処法

タコノキに発生しやすい害虫は以下の4つです。
- ハダニ
- カイガラムシ
- アブラムシ
- コバエ
それぞれ見ていきましょう。
ハダニ
ハダニの症状は以下の通りです。
- 葉にクモの巣のような糸がついている
- 葉の裏に小さな虫がついている
- 葉に斑点やカスリのような傷がある
- 葉の色が薄くなり枯れている
ハダニは繁殖力の強さと、薬剤耐性を持つ厄介な害虫です。
放っておくと糸を張って大量発生する危険性もあるので、早めに対処を行いましょう。
対処法は以下の通りです。
- 傷んだ葉は取り除く
- 葉の表裏、付け根や葉柄も水で洗浄する
- ハダニに効果のある液体を噴霧する(殺虫剤のほか、2倍に薄めた牛乳、重曹と水を混ぜたもの、濃いコーヒー、10倍に薄めた酢でも一定の効果あり)
ハダニが湧いてしまったら、市販の殺虫剤(ベニカXファインスプレー・オルトランなど)の使用が効果的です。ハダニは一度では駆除しきれないことがほとんどなので、状態を見ながら、定期的に噴霧してください。
2倍に薄めた牛乳などの液体を噴霧する対処法もありますが、匂いが気になる方は水で洗い流す方法がおすすめです。ハダニが現れたら、こまめに殺虫剤を吹きかけたり、ホースシャワーで株全体を水で洗い流したりしてください。
大株のタコノキの場合は、普段からベランダやテラスなどの屋外で株全体に水を浴びせるように、ホースシャワーで水やりして管理しているとハダニの予防になります。
ハダニは非常に小さいため、姿を確認しにくい害虫です。葉を触ってザラザラした感触がある場合はハダニがいるかもしれません。
大発生してクモの糸のようなものが目立ち始めたら注意です。そうなる前に「観葉植物に発生するハダニ」の記事で初期症状や対処法を確認しておきましょう。
カイガラムシ
カイガラムシの症状は以下の通りです。
- 貝殻のような殻を被ったり、粉状の物質で覆われたりしている虫がついている
- 黒いカビ(すす病)が発生している
- 葉や鉢、床がベタベタしている
カイガラムシは繁殖力の強さと薬剤耐性のある厄介な害虫です。
風通しの悪い環境で育てていると、葉と葉の隙間や株元の付け根にカイガラムシが発生しやすいです。そのままにしていると、大発生してすす病を併発させたり株が弱々しくなったりするので注意してください。
見つけ次第、早めに対処しましょう。対処法は以下の通りです。
- 柔らかい布やブラシで擦り取り除く
- 茂り過ぎている葉は取り除き、風通しを良くする
- カイガラムシに効果のある液体を噴霧する(殺虫剤のほか、2倍に薄めた牛乳、重曹と水を混ぜたもの、濃いコーヒー、10倍に薄めた酢でも一定の効果あり)
カイガラムシが発生したら、市販の殺虫剤(ベニカXファインスプレー・オルトラン・スミチオンなど)の使用が効果的です。
しかし、カイガラムシは殺虫剤が効きにくい害虫です。そのため、殺虫剤使用と布・ブラシでの拭き取りを合わせて行うと効率的に駆除できます。
タコノキは葉を多く茂らせる植物なので、一度カイガラムシが発生し始めると、駆除が大変です。普段から茂りすぎている葉や黄色い葉は取り除き、風通しよく育ててください。
水やりのタイミングで、葉の様子を確認しながら、もし見つけた場合はすぐに殺虫剤を噴霧したり、取り除いたりするようにしましょう。
カイガラムシに悩んでいる方は「観葉植物の白い虫はコナカイガラムシ」の記事の内容も、ぜひ参考にしてみてください。
アブラムシ
タコノキの葉を徒長させると、アブラムシが増えやすくなります。徒長した葉や生育不良の新芽は柔らかく、アブラムシが集まりやすいためです。
アブラムシが発生した際の症状は、以下の通りです。
- 新芽にアブラムシが密集している
- 新芽の葉の形がゆがんでいる
- 白~茶色い脱皮殻が目立つ
- 葉や鉢、床がベタベタしている
アブラムシは繁殖力が強いため短期間で増え、ウイルスを媒介する厄介な害虫です。
脱皮を繰り返して短期間で成虫になるので、アブラムシが増えると、葉に白~茶色の小さなチリのようなものが目立ち始めます。このチリのようなものは、脱皮殻です。
脱皮殻を見つけた際は、近くにアブラムシがいますので、注意深く観察して見つけてください。放っておくと生育が弱まり綺麗な新芽が出てこなくなるので、早めに対処を行いましょう。
対処法は以下の通りです。
- ゆがんだ新芽は取り除く
- アブラムシを取り除く
- 枯葉は取り除いて風通しをよくする
- 日当たりと風通しの良い場所に移動させる
- アミノ酸を多く含む有機系の肥料は与えない
- アブラムシに効果のある液体を噴霧する(殺虫剤のほか、2倍に薄めた牛乳、重曹と水を混ぜたもの、濃いコーヒー、10倍に薄めた酢でも一定の効果あり)
アブラムシを見つけたら、市販の殺虫剤(ベニカXファインスプレー・オルトランなど)の使用がおすすめです。殺虫剤が効きやすい害虫なので、すぐに対処すれば被害は大きくなりません。
アブラムシは、室内で管理しているタコノキにも発生します。アブラムシを発生させない対策は、「肥料を与えすぎない」「風通しを良くする」などです。
その他の発生させない対策が気になる方は、「観葉植物に発生するアブラムシ」の記事を参考にしてみてください。
コバエ
コバエの症状は以下の通りです。
- 土から虫が湧く
- コバエが植物の周囲を飛んでいる
コバエ自体は植物に無害ですが、タコノキを育てるうえでは不快害虫です。放っておくとコバエはどんどん増えていくので、早めに対処を行いましょう。
対処法は以下の通りです。
- 発酵不十分な堆肥や有機質肥料を与えることをやめる
- 新しい土や水苔に植え替える
- 土の表面に無機質な素材(赤玉土・鹿沼土・砂利など)を敷く
- トラップを仕掛ける
- コバエに効果のある殺虫剤を噴霧する
タコノキを育てるうえで、土に堆肥を混ぜ込んだり有機質肥料を与えたりするとコバエが発生する原因になります。コバエをどうしても発生させたくない方は、無機質用土を使って育てることをおすすめします。
もしコバエが発生したら、市販の殺虫剤(ベニカXファインスプレー・オルトラン・スミチオンなど)を使って退治しましょう。スプレーでうまく対処できない場合は、トラップを仕掛けて数を減らすのも一つの手です。
コバエのトラップは食器用洗剤やお酢、めんつゆなどで簡単に作ることができます。植物の近くに置いておくと、簡単にコバエを捕殺できるはずです。
土の中の卵や幼虫が気になる場合は、溜めた水に殺虫剤を溶かして、一時的に鉢ごと沈めてください。土の中にいる幼虫や卵は、殺虫成分と窒息の効果で退治できます。
コバエは有機質の匂いに反応して集まってきます。特に完熟していない不完全なたい肥には注意が必要です。コバエ発生の理由や対処法を詳しく知りたい方は、「観葉植物に発生するコバエ」の記事を確認しておくと対策に役立つでしょう。
タコノキの育て方に関するよくある質問

最後にタコノキの育て方に関するよくある質問とその答えを以下にまとめました。
- 成長速度は?
- 育てるのにおすすめの土は?
- 水耕栽培(ハイドロカルチャー)できる?
- タコノキとアダンの違いは?育て方も違う?
それでは具体的に見ていきましょう。
成長速度は?
タコノキの成長速度は速いとされています。しかし、年間を通して適切な環境でない場合は、あまり成長しないこともあるので、注意してください。
生育温度は15~25℃であるため、一年を通して20℃前後で日当たりの良い環境であれば、ぐんぐんと生育します。新葉を出しながら古葉が枯れ落ちる新陳代謝を繰り返しながら、樹高を大きくする様子を楽しめるでしょう。
タコノキには、アカタコノキやオガサワラタコノキなどの複数の品種があるため、品種による成長速度の違いがあります。とはいえ、環境が良いほど成長速度は速いので、大きく育てたい方は適切な環境を維持して育ててみてください。
育てるのにおすすめの土は?
タコノキを育てるのにおすすめの土は、腐植質を含んだ水はけのよい土です。海岸線に自生していることの多いタコノキは、水はけの良さを土に求めます。
そのうえで、腐葉土のような腐食質を土に含ませるとより生育が良いです。ただし、腐葉土やたい肥を入れすぎると、水はけが悪くなったりコバエ発生の原因になったりするので、全体の1~2割程度に抑えると良いでしょう。
AND PLANTSでは、オリジナル用土「AND PLANTS SOIL 観葉植物の土」を取り扱っています。観葉植物の生育に適した乾きやすさと、育てやすい保湿性を両立している土です。
原材料として使用しているダークピートは、腐食が進んだ良質なピートモスなので、タコノキの生育もより良くなるはずです。ぜひ用土に悩んでいる方は、使ってみてください。
[https://andplants.jp/products/andplantssoil-25l]水耕栽培(ハイドロカルチャー)できる?
タコノキは水耕栽培(ハイドロカルチャー)できます。ただし、幹から気根を出しながら葉を茂らせるため、頭が重くなり不安定です。
根がしっかり固定できる土の代用資材を用いたり、倒れにくい思い容器を使ったりして水耕栽培を楽しみましょう。
ハイドロカルチャーで育つ性質を利用して、水槽内でパルダリウムやビバリウムのように育てるのも人気があります。南国をイメージして大ヤドカリのビバリウムにも使用されることもあるほどです。
ぜひタコノキの水耕栽培を楽しんでください。
タコノキとアダンの違いは?育て方も違う?
タコノキとアダンは、どちらもタコノキ科タコノキ属の植物で非常に見た目が似ていますが、異なる植物です。
主な違いは、幹のトゲや樹形、果実の形です。タコノキは比較的まっすぐ上に伸びる樹形ですが、アダンは枝をグネグネと横に広げながら大きくなります。
また、タコノキの果実はとげとげしいほどに先端が尖った皮がボール状になっています。対して、アダンは全体的に丸みを帯びておりパイナップルのような見た目です。
タコノキとアダンは異なる植物ですが、同じような環境で育てることができます。タコノキとアダンは間違われやすいため、特徴の違いを知っておくと良いでしょう。
まとめ
タコノキは、気根がユニークな南国の雰囲気を感じさせる植物です。高温多湿環境に強いので、暑い夏にも耐えられます。
タコの足のように伸びる気根は、面白いインテリアプランツとして活躍するでしょう。日光を好む性質と寒さに弱い点を理解して育てると、美しい樹形を一年中楽しめます。
沖縄や小笠原諸島などの亜熱帯地域に自生しているため、大きなタコノキを見たことがある方は多いかもしれません。お部屋の雰囲気を南国チックにしたい方は、ぜひタコノキを育ててみてください。
[https://andplants.jp/collections/screwpine]