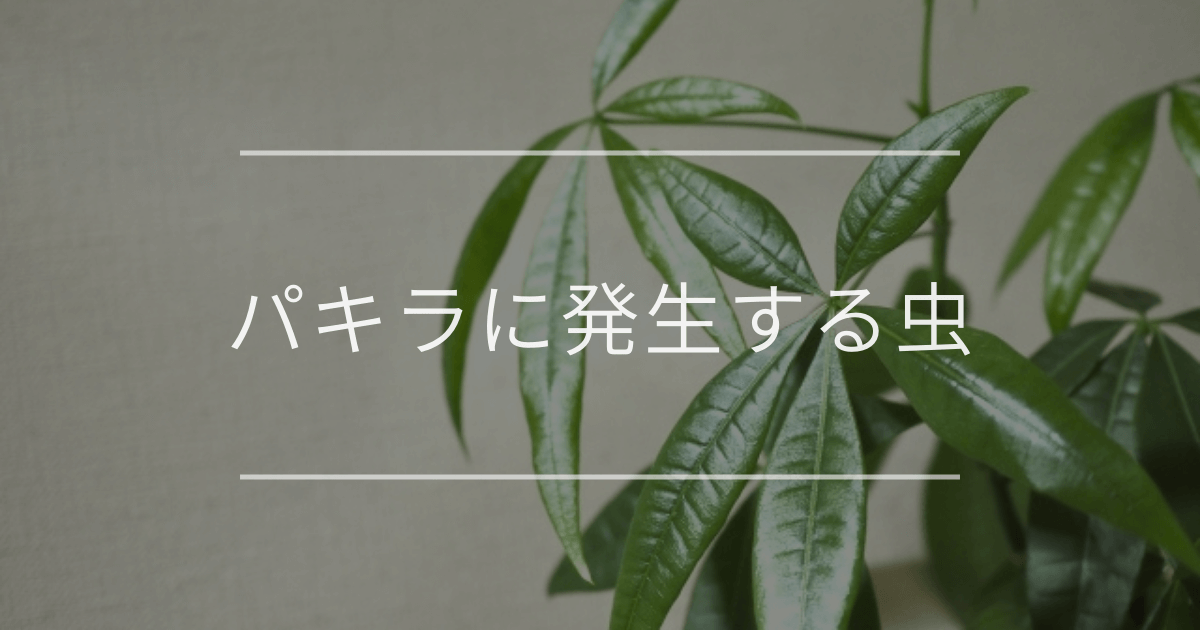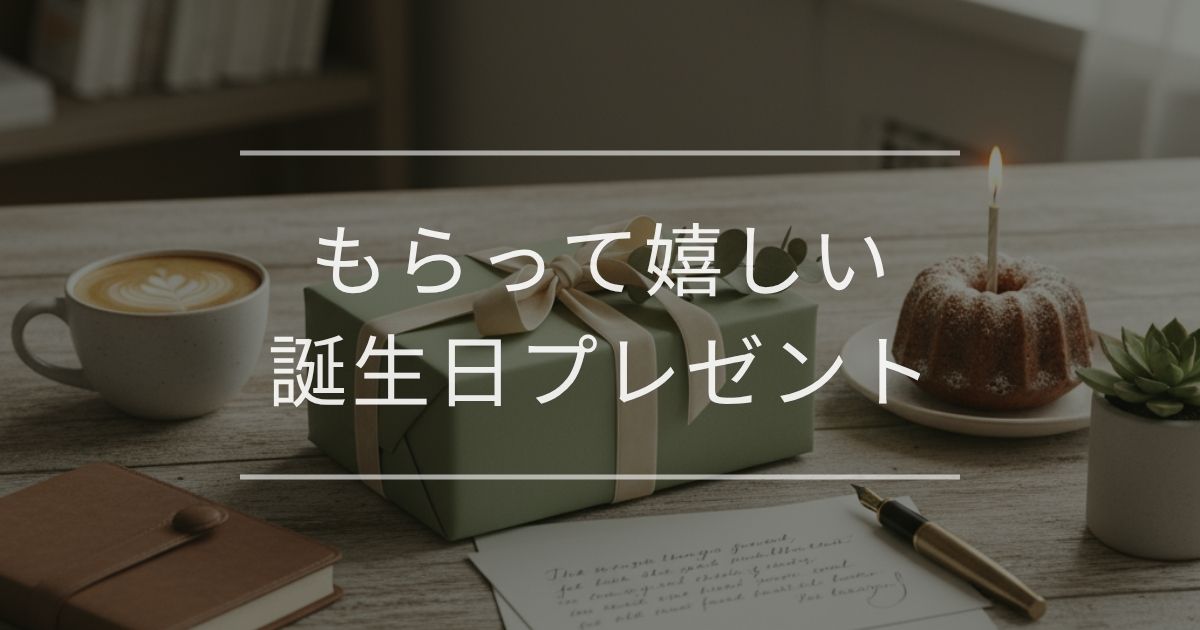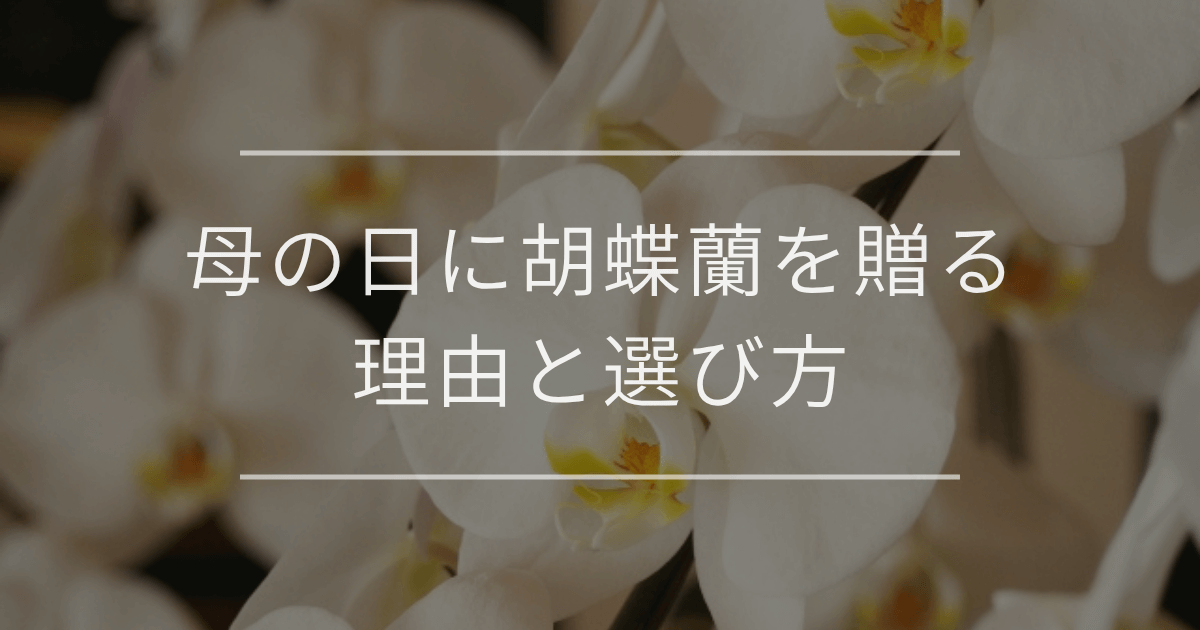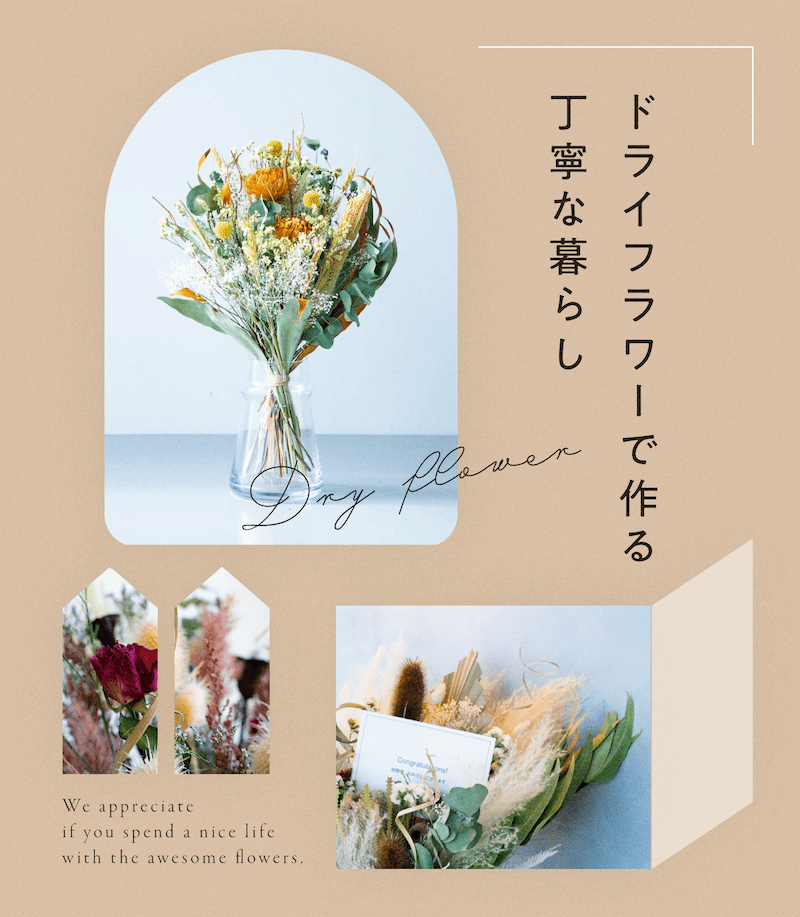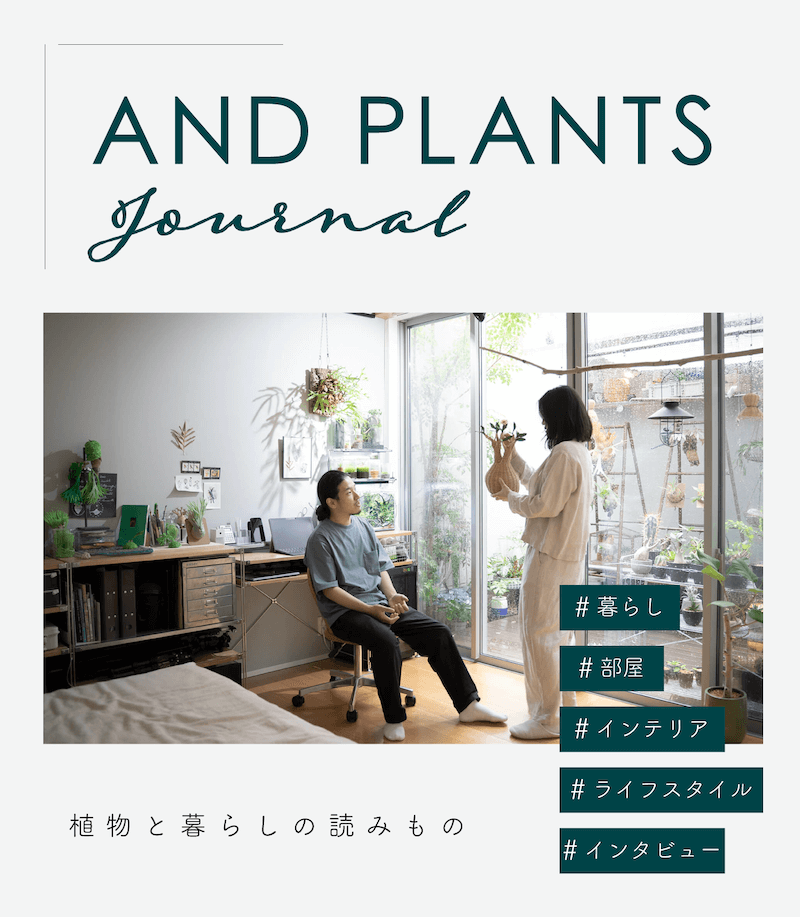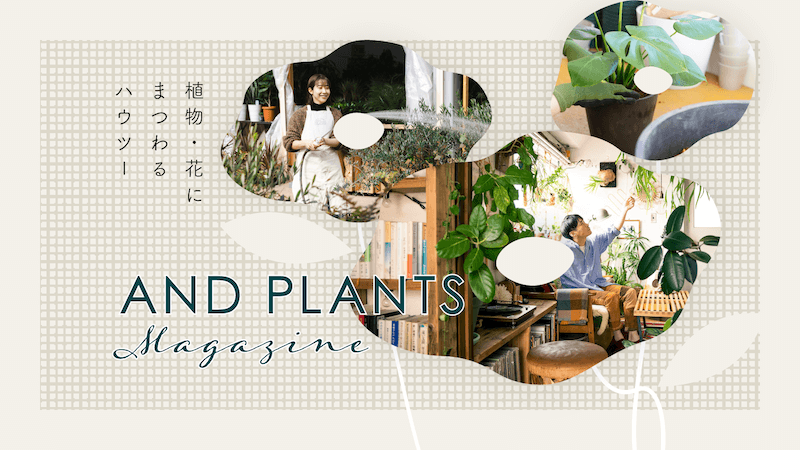育てているパキラに虫が発生した時の駆除方法に悩んでいませんか。虫の駆除が遅れると、被害が拡大したり虫が大発生したりするかもしれません。
そこで、今回はパキラに発生する虫について詳しく解説します。屋内と屋外で発生しやすい虫の種類から、駆除方法や予防法まで紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
どんな虫が発生していて、駆除方法や予防法まで知っておくと、パキラに虫が付いてもすぐに対処できます。被害を最小限に抑えて、パキラを元気に育ててあげましょう。
AND PLANTSでは自然由来の成分でのみ作られ、嫌な匂いもなく、室内でも安心して使える防虫スプレーを取り扱っています。ぜひ、虫が発生している植物や害虫にスプレーしてみてください。
[https://andplants.jp/products/evo_anti_insect_spray]屋内|パキラに発生する虫
屋内でパキラに発生しやすい虫は、以下の7種類です。
- ハダニ
- カイガラムシ
- アブラムシ
- コナジラミ
- コバエ
- トビムシ
- アザミウマ
それぞれの特徴や被害を詳しく見ていきましょう。
虫の発生は、育てている環境や育て方に影響しています。そのため、紹介した虫がパキラに必ず発生するわけではない点に注意してください。
ハダニ

ハダニはクモの一種で、英語では「Spider mlte」と呼ばれている虫です。クモの仲間であるため、大発生した際に白い糸を植物に巻き付ける被害も確認できます。
成虫でも0.5㎜ほどの体長しかなく葉裏に生息していることが多く、パッと見ただけでは見つけることは難しいです。ハダニが発生した際に現れる初期症状に、「葉がカスリ状に薄くなる」があります。
初期症状を見つけたら、すぐにパキラの葉の表裏を観察してください。ハダニが付いていると、触った際にザラザラとした手触りで気づくこともできます。
空気が乾燥した環境で増えやすいため、湿度管理に注意してパキラを育てると良いでしょう。ハダニが発生する原因や対策については、「観葉植物に発生するハダニ」で詳しく紹介しています。
カイガラムシ

カイガラムシはパキラをはじめ、多くの観葉植物に発生する代表的な虫です。観葉植物に限らず、果樹や庭木、多肉植物にも発生します。
カイガラムシは、葉や枝、幹に貼りついて養分を吸収して生育を妨げます。種類によって、形状や色が異なり、体長も2㎜~10㎜とさまざま。
小さなカイガラムシの場合は、特に見つけにくく、どの種類も全く動きません。発生初期に見つけられず、大発生して気づくことの多い虫です。
吸収した養分は、ねばねばした甘露として葉や幹、床などにまき散らします。その甘露にカビが生えて、すす病を併発させることもあるので注意してください。
観葉植物に発生しやすいカイガラムシについては、「観葉植物の白い綿はコナカイガラムシ」の記事でも詳しく紹介しています。対処方法や予防方法が気になる方は、ぜひ確認してみてください。
アブラムシ

アブラムシは植物の新芽やつぼみなど柔らかい部分に群生して、養分を吸収する虫です。成長サイクルが非常に早く、7~10日程度で卵から成虫になり、増えていきます。
カイガラムシ同様に、パキラの生育を妨げ甘露をまき散らすため、葉や幹、床がベタベタとしてきます。さらに、甘露は糖を多く含んでいるので、アリを集めやすいです。
甘露によってすす病を併発させるだけでなく、アブラムシそのものがウイルスの媒介者としてモザイク病をパキラに発症させることも。モザイク病にかかるとパキラの葉にモザイク状のまだら模様が現れたり、葉が縮れたりします。
アブラムシは薬剤で駆除しやすいので、見つけ次第すぐに対処しましょう。観葉植物にアブラムシが発生する原因や予防法については「観葉植物に発生するアブラムシ」の記事でも詳しく解説しています。
コナジラミ

コナジラミは白く細長いはねを持ち、体長が1~2㎜程度の小さな虫です。パキラの葉の裏から養分を吸収します。
主にウリ科やナス科、アブラナ科などの野菜に発生しやすいですが、稀にパキラをはじめとした観葉植物にも発生するので、注意してください。
養分を吸収された葉は、色が抜けてカスリ状の白い跡が残り、パキラの見栄えが悪くなります。繁殖力が強く、約28日間で卵から成虫まで成長します。
幼虫も同様の被害をもたらすので、見つけ次第、素早く駆除しましょう。普段は葉の裏に隠れていますが、手入れの際にパキラに触れると、小さな白い羽虫がふわっと飛んだら、コナジラミの可能性が高いです。
コナジラミの種類やトラブルに悩んでいる方は、「観葉植物に付くコナジラミ」の記事も併せてチェックしていただくと、対策を立てやすいと思います。
コバエ

パキラをはじめとして観葉植物に発生するコバエは、体長5㎜以下のハエやカに似た小さな羽虫の総称です。
コバエ自体は、観葉植物や私たち人間に直接の被害を与えませんが、飛び回ることで不快な気持ちにさせる不快害虫です。湿度が高い環境や有機物の多い土に集まって増殖します。
コバエが土に集まる場合は、完熟していない有機質が含まれていたり、根腐れしていたりする可能性があります。コバエの駆除も重要ですが、パキラの土の状況も確認した方が良いでしょう。
コバエの駆除方法にはトラップも効果的です。コバエに効くトラップの作り方は「観葉植物に発生するコバエ」の記事でも紹介しています。
トビムシ

トビムシは、土の表面でピョンピョンと飛び跳ねる体長2~3㎜程度の小さな虫です。世界中に生息しており、日本国内でも300を超える種類が存在しており、体色も白色から銀色、赤色、黒色などさまざま。
土の中のバクテリアや菌、腐葉土などを食べます。有機質も分解してくれるため、植物に利益をもたらす「益虫(えきちゅう)」です。
しかし、パキラの土の上で小さなトビムシがピョンピョンと飛び跳ねているのは、気持ちが良いものではありません。そのため、不快害虫とも言えるでしょう。
土に有機質が多かったり、常に湿っていたりすると発生しやすいです。土や水やりに注意してパキラを育てると、発生を予防できます。
トビムシを初めて見た方は、驚くと思います。トビムシ対策は「観葉植物に発生するトビムシ」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ一読してみてください。
アザミウマ

アザミウマは体長1~2㎜程度の細長い小さな虫です。黄色や黒色、褐色などの体色をしています。
パキラの葉の付け根などで発生して、気温の高い夏によく見られます。アザミウマは、パキラの養分を吸汁して生育に悪影響を与える虫です。
被害を受けた葉には、白い斑点が発生します。被害が拡大すると葉が茶色になり、新葉は縮れたような奇形で展開することも。
アザミウマは植物体内で生成されるアミノ酸を好む虫です。アミノ酸生成にかかわる窒素を多く与えている植物に集まりやすいので、肥料の与えすぎに気を付けましょう。
屋外|パキラに発生する虫

屋外でパキラに発生しやすい虫は、以下の5種類です。
- ハモグリバエ(エカキムシ)
- ケムシ
- コガネムシ(ネキリムシ)
- キャクトリムシ
- ナメクジ
屋外でパキラを管理している方は、屋内で発生しやすい虫の他にも、多くの虫から被害を受けやすいです。屋外で育てているから、室内で発生しやすい虫の被害は減るといったことはありませんので、注意してください。
それでは、屋外で発生しやすい虫のそれぞれの特徴や被害を詳しく見ていきましょう。
ハモグリバエ(エカキムシ)

ハモグリバエとは、植物の葉肉内部に卵を産み付ける虫です。卵から孵化した幼虫は、葉の内部から組織を食害して生育に悪影響を与えます。
食害した跡は、模様が描かれたような白い線が残るので「エカキムシ」とも呼ばれています。主に、農作物で発生しやすい虫ですが、パキラでも発生することも。
屋外でパキラを管理していて、近くに野菜や果樹がある場合は、注意してください。被害に遭っている葉は、取り除き処分したり、葉の中に幼虫がいる場合は潰したりしましょう。
成虫は素早く飛び回るので、直接殺虫剤を噴霧できなければ、駆除するのは難しいです。
ケムシ

ケムシはガの幼虫の総称です。ケムシに限らず、チョウの幼虫もパキラの葉を食害します。
屋外でパキラを管理している場合、ケムシに柔らかい新芽や新葉が食害されやすいです。ケムシによっては、群生して一晩で葉を食べてしまう種類もいるので注意してください。
さらに、ケムシによっては、触れると激痛を与える種類もいます。直接触れてなくても、落ちた毛に触れるだけで、肌に痛みやかゆみを生じさせる場合もあります。
ケムシを見つけたら、直接触らず殺虫剤で離れた位置から対処すると安心です。
コガネムシ(ネキリムシ)

屋外でパキラを管理している場合、コガネムシの幼虫の被害に遭うことがあります。パキラを育てている土に腐葉土を多く使っていると、コガネムシが産卵しやすいです。
卵が孵化して、生まれた幼虫はパキラの根を腐葉土と一緒に食べてしまいます。そのため、ネキリムシとも呼ばれることも。
同じようにネキリムシと呼ばれ、根を食害する虫にヨトウガの幼虫がいます。しかし、ヨトウガの幼虫は草花の柔らかい葉や根を食べるので、パキラに被害をもたらすことは少ないでしょう。
シャクトリムシ

シャクトリムシは、「シャクガ」と呼ばれるガの幼虫です。体を曲げて縮めては伸ばす独特な移動をします。
4月~9月に発生して、パキラの葉を食害します。見栄えが悪くなることはもちろん、大きなフンもするため、見つけ次第、駆除しましょう。
直接触ることに抵抗を感じる方は、殺虫スプレーで対処してください。
ナメクジ

ナメクジもパキラを食害します。パキラの幹や葉、枝にキラキラと光るねばついた液が付いている場合、ナメクジが通った後かもしれません
ナメクジは湿気を好む夜行性の虫です。明るいうちは、鉢底の湿った暗い場所に隠れており、夜になると活発に活動して葉を削り取るように食害します。
湿度の高い梅雨以降に発生しやすいです。屋外のテラスやベランダ、お庭でパキラを管理している方は、鉢底をチェックしたり夜に様子を見たりして駆除しましょう。
パキラに発生した虫の駆除方法

パキラに発生した虫の駆除方法には、以下の5つの方法があります。
- 直接取り除く
- シャワー・霧吹きで洗い流す
- トラップを使う
- 牛乳を薄めてスプレーする
- 殺虫剤を使う
それぞれの駆除方法を詳しく解説します。
直接取り除く
パキラに発生した虫は、直接取り除く方法が、素早く行える駆除の1つです。ブラシや布で擦り落としたり、箸で掴んだり、テープでくっつけたりして取り除きます。
虫が苦手でない方におすすめの駆除方法です。また、虫が少数であるほど、すぐに駆除でき、周囲やパキラへの薬剤の心配もいりません。
シャワー・霧吹きで洗い流す
パキラに虫が発生した際には、シャワーや霧吹きで洗い流すのもおすすめの駆除方法です。特に、水を嫌うハダニやアザミウマ、コナジラミなどに効果があります。
虫のいる大株のパキラであれば、ベランダやテラス、お庭などの屋外に移動させて、シャワーの水圧で、葉の裏までしっかりと洗い流してください。小さなパキラであれば、霧吹きを葉に近づけて一枚一枚噴霧してあげると良いでしょう。
[https://andplants.jp/products/groriapro5]トラップを使う
パキラに発生した虫の駆除にはトラップが有効な虫もいます。匂いに集まるコバエやナメクジ、黄色に反応するコナジラミにおすすめの駆除方法です。
コバエであれば、食器用洗剤・お酢・めんつゆ・水を混ぜ合わせ、コバエが発生しているパキラの近くに置くと、簡単に捕殺できます。ナメクジの場合は、ビールを入れた容器を近くに置くと効果的です。
コナジラミには、専用トラップとして黄色の粘着シートが市販で販売されています。それぞれのトラップで捕まえられる虫は限られますが、いずれも薬剤を使うことなく、虫にも触れる必要はありません。
ただし、トラップにかかった虫にしか効果はありませんので、完全に駆除するのは難しいでしょう。
牛乳を薄めてスプレーする
パキラに発生した虫には、牛乳を薄めてスプレーする駆除方法もあります。アブラムシやカイガラムシ、コナジラミなどに効果があるとされています。
薄めた牛乳が乾くことで、虫の体表に膜を作り、窒息させる効果があるそうです。牛乳以外にも、重曹や唐辛子など食品を使用して駆除する方法があります。
いずれも一定の効果はありますが、虫によっては全く効果がない場合もあり、完全に駆除することも難しいです。また、パキラに匂いや色が付いて見た目が悪くなるデメリットもあります。
無農薬にこだわりたい方は、市販の澱粉を利用した殺虫スプレーを利用すると良いでしょう。
殺虫剤を使う
パキラに虫が発生した場合は、殺虫剤を使いましょう。駆除方法の中で、確実性が高く、虫が苦手な方も気軽に虫を退治しやすいです。
ただし、虫の種類によって、効果的な殺虫成分が異なります。1種類の殺虫剤だけですべての虫を駆除できるわけではないので、注意してください。
また、1種類の殺虫剤を使い続けると、殺虫成分に抵抗力を持つ虫が生まれやすいです。徐々に殺虫剤の効果が薄くなってくるので、複数の殺虫剤(ベニカファインスプレーやオルトランなど)を準備しておくと良いでしょう。
AND PLANTSでは自然由来の成分でのみ作られ、嫌な匂いもなく、室内でも安心して使える防虫スプレーを取り扱っています。お手元に1つあると、パキラに発生している虫を見つけた時に便利です。
[https://andplants.jp/products/evo_anti_insect_spray]パキラに虫が発生しにくくなる予防法

パキラに虫が発生しにくくなる予防方法を7つ紹介します。
- 日当たりの良い場所に置く
- 風通しを確保する
- 葉水をする
- 水はけのよい無機質用土で育てる
- 肥料を与えすぎない
- 白~銀色のマルチングをする
- 鉢植えの落ち葉は取り除く
パキラに虫を発生させないためには、基本的な育て方を見直すことが重要です。健康的で元気なパキラには虫が発生しにくいためです。
以降で話す7つの項目に加えて「元気なパキラにするための育て方」記事も参考にしておくといいでしょう。
日当たりの良い場所に置く
パキラは日当たりを好む植物です。そして、パキラに発生する害虫の多くは、日光を嫌います。そのため、パキラに虫が発生するのを予防するためにも、日当たりの良い場所に置きましょう。
日差しが入らない暗い場所では、パキラは光合成を十分にできずに、葉や枝が徒長します。徒長した枝葉は組織が柔らかく虫の被害に遭いやすいです。
また、暗い場所は日光が差し込みません。ジメジメと湿気が溜まりやすい環境になるので、虫が繁殖しやすいです。
パキラを健康的に育てて、虫が発生しにくい環境にするためにも、日当たりの良い場所に置いてください。
風通しを確保する
風通しの確保も、パキラの虫発生予防につながります。風通しがあると、パキラの水やり後は土が乾きやすくなり、虫が増えにくい環境になるためです。
蒸れの予防にもなります。パキラの周囲の空気が常に動いていることで、虫も落ち着いて増えることができないでしょう。
窓を開けることが難しい場合は、サーキュレーターやエアコンで空気を動かすと効果的です。ただし、直風が当たり続けるとパキラの葉から水分が蒸発して葉が乾燥して枯れるため、直風が当たらないようにしてください。
葉水をする
パキラに虫が発生しにくくなる予防法として「葉水をする」も効果的です。特に乾燥を好むハダニ対策におすすめです。
霧吹きで葉水をしていると、湿度を維持できるため、乾燥を好むハダニは発生しにくくなります。冷暖房を入れた部屋では、空気が乾燥しやすいので、水やり時に葉水も与えると安心です。
また、普段から葉水をしていると、葉の変化に気づきやすいため、素早くパキラに発生した虫に気づけるでしょう。
水はけのよい無機質用土で育てる
パキラを水はけのよい無機質用土で育てることも、重要な虫発生の予防法です。土の有機質や湿気が原因で発生しやすいコバエやトビムシ対策に効果があります。
腐葉土やたい肥を除いた無機質用土を使用するだけで、コバエやトビムシは発生しにくくなります。発生原因となる有機質がないためです。
しかし、パキラそのものが有機質なので、水やりのやりすぎや受け皿に水を溜めていたりすると根腐れします。
根腐れした根の匂いにコバエが集まることがあるので、水はけのよい無機質用土を使用すると根腐れしにくくなるでしょう。
水やり後は受け皿に溜まった水は、こまめに捨てることも重要です。
AND PLANTSでは有機質無配合の水はけのよい「INLIVIG 観葉植物の土」を取り扱っています。マルチングとしても使用できますので、パキラの虫予防としていかがでしょうか。
[https://andplants.jp/products/inliving-soil-2l]肥料を与えすぎない
パキラに虫が発生しにくくなる予防法には、肥料を与えすぎないこともポイントです。葉を茂らせる窒素をパキラに与える方は多いと思います。
窒素を与えすぎると、虫が付きやすくなるので注意してください。植物は窒素を吸収すると、アミノ酸を生成します。
アミノ酸が多く生成されると、アミノ酸を好むアブラムシやアザミウマが増えやすいです。そのため、窒素を含む肥料を与えすぎないように気を付けましょう。
白~銀色のマルチングをする
パキラの土の上に、光を反射する白~銀色のマルチングをするのも効果的です。光を反射することで、葉裏にも光が届くようになります。
虫は葉裏に隠れていることが多いので、光が葉裏に届くことで予防に繋がります。また、土の上のマルチングは、有機質の匂いを防げます。
結果、有機質の匂いに集まりやすい虫が寄り付きにくくなるのです。
もし、すでにコバエやトビムシが土に発生している場合は、表土2~3㎝ほどを取り除いて、新しい土を入れてマルチングすると良いでしょう。
コバエやトビムシの卵は、表土2~3㎝ほどの部分にしかないためです。もしマルチングするスペースがなければ、新しい土を入れずにマルチングしても問題ありません。
鉢植えの落ち葉は取り除く
パキラの鉢植えに落ち葉がある場合は、取り除きましょう。枯れた葉が落ちたままだと、葉の下に虫が隠れたり、水やり後に湿った落ち葉に虫が集まったりするためです。
落ち葉は有機質であるため、湿った状態が続くとカビが生えたり腐植したりします。落ち葉を取り除くといったちょっとしたことでも、虫の発生予防に効果的です。
パキラの周囲に他の植物を並べていると、他植物の枯葉も落ちてきます。土の上は落ち葉がないように綺麗にしてください。
パキラの虫対策には水耕栽培もアリ

パキラの虫対策には、水耕栽培もおすすめです。虫が発生する原因となりやすい土を取り除くことで、虫が発生する心配が少ないパキラとして楽しめます。
ハイドロボールやセラミス、パフカルチップなどを使った水耕栽培であれば、有機質を含まないため、室内でも安心してパキラを育てられます。
ただし、パキラ自体が有機質なので、葉が枯れたり根が腐ったりすると、虫が集まる点には注意してください。水耕栽培は水を溜めて育てるため、溜めた水が腐らないように、定期的に水を入れ替えることも重要です。
パキラは土が常に湿っている環境を嫌うため、ハイドロボールやセラミス、パフカルチップなどによる水耕栽培であっても、容器内に水を溜めないように管理してください。
パキラに発生する虫に関するよくある質問

パキラに発生する虫に関するよくある質問とその答えを以下にまとめました。
- パキラの葉に穴が開く場合は虫がいる?
- パキラに虫が付かない土はある?
- パキラの土にムカデのような小さな虫が多くいる場合はどうしたらいい?
それでは具体的に見ていきましょう。
パキラの葉に穴が開く場合は虫がいる?
パキラの葉に穴が開くからと言って、必ず虫がいるとは限りません。新芽の時に、葉に傷がつくと大きくなった際に、その傷が穴のように広がることがあるためです。
植え替えや剪定時に新芽を傷つけたり、新芽を虫にかじられていたりすると、葉が展開した時に、虫がいないにもかかわらず穴が開いているといった現象があります。
また、炭疽病のように病状が進行すると、穴が開く病気もあります。虫による被害も含めて、葉に穴が開いた場合は、しっかりと観察しましょう。
パキラに虫が付かない土はある?
パキラに虫が付かない土はありません。腐葉土やたい肥などの有機質を除いた無機質の土であっても、パキラに虫は付くことはあります。
パキラそのものが生き物である限り、パキラの葉や養分を食べたり吸収したりする虫が付くためです。そのため、パキラに虫が発生しないように、健康的に育てましょう。
あらかじめ殺虫成分のある粒剤を撒いている土もあります。しかし、殺虫効果は限定的で、効果が切れると虫は付くので、虫が付かない土とは言えません。
パキラの土にムカデのような小さな虫が多くいる場合はどうしたらいい?
パキラの土にムカデのような小さな虫が多くいる場合は、植え替えてください。ムカデのような小さな虫は、ヤスデだと考えられます。
ヤスデは、分解が進んだ腐葉土やたい肥、落ち葉などに付く菌を好んで食べる虫です。土を豊かにする分解者でもあるため、益虫に分類されます。
しかし、パキラの土から出てきた場合は、驚く方がほとんどだと思います。有機質の土でパキラを育てている生産者の鉢から出てきやすい傾向があります。
屋外でパキラを育てている場合も、いつの間にか鉢の中に住み着くことも多いです。室内にヤスデを入れたい方は少ないと思いますので、古い土はすべて取り除き、新しい観葉植物の土に植え替えてください。
まとめ
パキラに発生する虫について、駆除方法や予防法をお話させていただきました。「パキラには、こんな多くの虫が付くの」と驚いた方が多いと思います。
「パキラ育てるのやめようかな」と思う必要はありません。屋外でパキラを育てない限りは、室内で発生しやすい虫だけを気を付ければ、問題ありません。
さらに、基本の育て方を守り、健康的なパキラを維持すれば、虫の発生はより少なくなります。もし発生しても、どんな虫なのかが分かれば、すぐに駆除できるでしょう。
この記事を参考にパキラの虫発生の予防に努めて、発生した際は駆除方法を参考にしてください。虫を見つけた時に、すぐに対処できるように、ぜひAND PLANTSおすすめの防虫スプレーを、手元に置いておくと便利ですよ。
[https://andplants.jp/products/evo_anti_insect_spray]