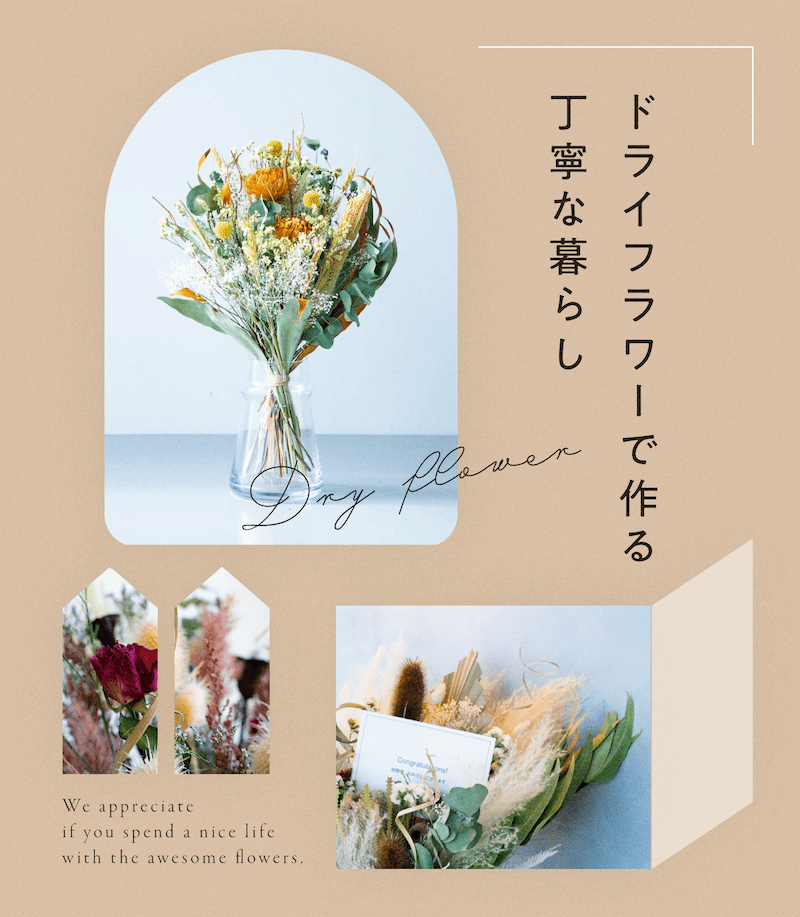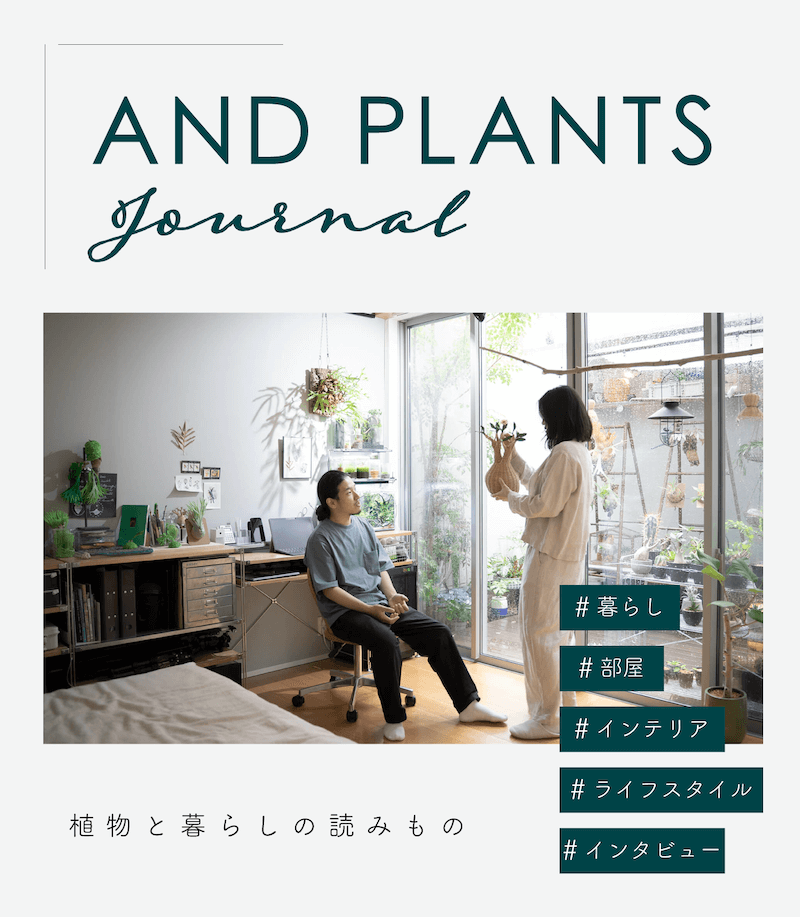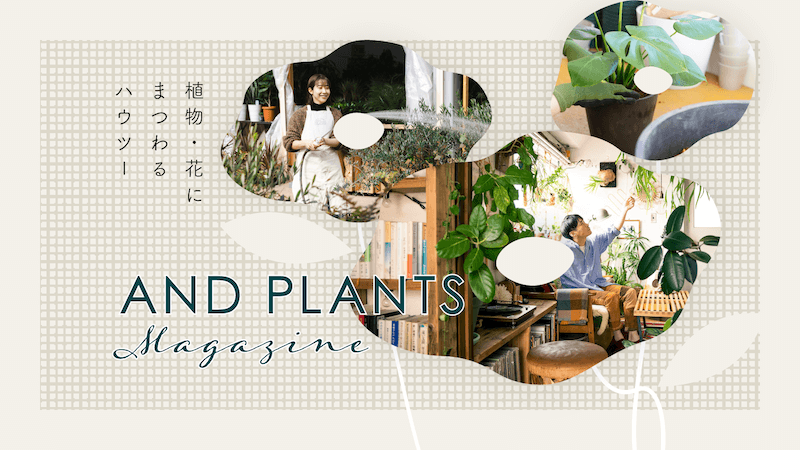この記事では、観葉植物の基本的な育て方を紹介します。
「初めての観葉植物でどう育てればいいかわからない」という方でも大丈夫なように、わかりやすく、網羅的に解説しました。
ぜひブックマークしていただき、何かトラブルがあった時に辞書的に使ってもらえれば嬉しいです。
観葉植物を育てるために必要なケアグッズをまとめました。肥料や霧吹きなど今時期に活躍できるものを厳選しています。
詳しくは「その他園芸グッズを見る」をタップしてください。
[https://andplants.jp/collections/caregoods]観葉植物を育てる上での3つのポイント
まずは植物を育てるにあたって大事な3つのポイントをまとめました。まず大事なのは下記の3つ。初めての方でもこれさえわかっていれば、元気に植物を育てることができます。
- お水やり|メリハリが大事
- 日光|日当たりの良いところに飾る
- 空気|風通しのよい場所に置く
それぞれについて下記でより詳しく紹介していきます。
また、動画でも植物バイヤーによる育て方のポイントを紹介しているので、こちらも合わせて見てみてください
1.お水やり|メリハリが大事

水やりはメリハリやタイミングが重要です。根っこ(植木鉢の中央部分)まで土が乾いたら、お水やりをしてください。
土を手で触ってサラサラまたはカラッと表面が乾いたら、土の全体を湿らせるようにたっぷりとあげましょう。土の中に溜まっている老廃物を鉢底の穴から押し流すことができます。
植物も人間と同じく栄養が必要で、植物は「栄養を作り出す」「栄養を吸収する」のどちらかで栄養を摂取しています。
| 栄養摂取の方法 | 具体例 |
| 栄養を作り出す | 水・二酸化炭素・日光を使った光合成 |
| 栄養を吸収する | 土の中にある栄養素を、根から吸収 |
水と二酸化炭素、日光を使い光合成をすることで「栄養を作り出し」、雨などで染み出した土の栄養素を根から吸うことで「栄養を吸収する」のです。
栄養を摂取するのにお水が欠かせないことがわかりますね。
また、お水やりは大事ですが、受け皿や鉢内のインナーポットにお水を溜めないように注意してください。土が常に湿っていると、根腐れを引き起こしてしまうためです。
お水やりのポイントは、土が完全に乾いてからたっぷりあげて鉢底から水を出すことです。土の乾燥具合がわからない場合は、鉢を持ち上げてみたり、土に竹串を刺したりして乾いているかどうかを確認するとよいでしょう。
AND PLANTSでは、土壌中の水分が不足した際に、自動で水が排出される「自動給水機」を扱っています。ガラス製のおしゃれなディスペンサーで、インテリアとしてもおすすめです。
「お水やりのタイミングがわからない…」といった方におすすめの道具ですので、お水やりで失敗をしたくない方はぜひ検討してみてください。
[https://andplants.jp/products/twotonewaterdispenser-l-by-1]2.日光|日当たりのよい場所に置く

植物は光合成をおこなうため、日の光が欠かせません。植物によっては半日陰や日陰のような暗い環境を好む種類もいますが、基本的に日当たりのよい場所に飾りましょう。
ただし、真夏の直射日光や西日は強すぎるので、チリチリと葉焼けする可能性があります。日当たりの理想は、レースカーテン越しの柔らかい明るい光が1日3~4時間入る環境です。
今まであまり元気がない植物でも、日当たりを変えるだけで急に元気になる場合もあるので、日当たりはぜひ工夫してみてください。
もし日当たりが改善できない場合は、蛍光灯や植物を育成するLEDライトで光を補うと健康的に育ちます。
3.空気|風通しのよい場所に置く

お水やりや日光と同じくらい大切なのが風通し。健康で丈夫な株に育てたい場合は、風通しのよいところに置くのが大切です。
| 項目 | 風通しが良い場合 | 風通しが悪い場合 |
| 土の乾き | 根腐れを起こしにくい | 乾きにくく、根腐れを起こしやすい |
| 植物の成長 | 葉や幹がたくましくなる | 湿気がこもり、弱りやすくなる |
| 病気・害虫のリスク | カビや害虫の発生リスクが少ない | 湿度が高まり、カビや害虫が発生しやすい |
風通しのよいところで植物を管理できれば、土も適度に乾き根腐れが起きにくくなります。加えて、風の力を浴びることで葉や幹もたくましくなるでしょう。
一方、風通しが悪ければ土が乾きにくいため、根っこも湿った状態が長く続きます。結果、根っこが腐ってしまい、株全体がダメになる可能性も。
植物を育てるうえで風通しには重要な役割があるので、意識して観葉植物を育ててください。窓を開けることが少ない室内であれば、エアコンやサーキュレーターで風の流れを意図的につくるとよいです。
以下に風を作る際のポイントをまとめました。
風を作る際のポイント
- 直風は避けて、部屋全体の空気が回るイメージで設定する
- 1日に数時間ほど空気を循環させるだけでも効果的
- 「風がそよそよ通る」程度の弱い風量を意識する
私たち人間も強い直風をずっと当てられていると、肌が乾燥したり風邪を引いたりしてしまいます。そのため、室内で育てる観葉植物にサーキュレーターやエアコンを使用する場合は、直風が当たらないようにしてください。
常に風を作る必要はないので、1日数時間だけでも空気を循環させると観葉植物は元気に育ちます。
観葉植物を育てる上で知っておきたいこと
基本を押さえたら、次は育て始めてからの予備知識を知っておきましょう。
- 肥料|5月~9月に与える
- 温度|各植物に適した気温下で管理する
- 剪定|生育期直前を目安に行う
- 植え替え|1〜2年に1回は鉢を植え替える
肥料|5月~9月に与える

肥料は真夏を除いた5月~9月に与えると効果的です。即効性のある液体肥料と、ゆっくりと栄養を与える緩効性肥料の2種類に分かれます。
緩効性肥料は植物の植え付け時に元肥として土に混ぜ込んだり、生育期に追肥として土にふりかけたり置いたりして使用してください。
お水やりをする際に溶け出し、植物に栄養を送ってくれます。追肥として与える場合は、2か月に1回のペースで与えるとよいでしょう。
液体肥料は水に混ぜて希釈するタイプのものが多くあります。お水やりのタイミングで、薄めた液体肥料を1か月程度水やり代わりに与えると効果的です。
お花が咲きやすかったり生育が早かったりする観葉植物の場合は、秋にも肥料を与えるとより元気に育ちます。与え方は生育期と同様ですが、固形の緩効性肥料は冬までに肥料分が残っていることがあるため、注意が必要です。
生育が緩慢になる冬に肥料を与えると、観葉植物の根が傷む可能性があります。秋に固形の緩効性肥料を与える場合は、冬に入る前に取り除いてください。
肥料は植物にとって大切なものですが、人も栄養を摂りすぎると負担になるように、植物に肥料を与えすぎると「肥料焼け」を起こし状態が悪くなることがあります。用法容量を守って適切に活用してください。
[https://andplants.jp/products/andplants_fertilizer]温度|各植物に適した気温下で管理する

市場に流通している植物の多くは、熱帯など暑い地域が原産地のものが多いです。そのため、日本では暖かい時期に最も活発に育ちます。
一方、寒さの厳しい日本の気候では冬越しできない種類もあるため、生育が止まったり枯れたりするケースも多いです。
植物は、寒さに耐えられる耐寒温度が決まっているので、なるべく下回らないように管理をするのが好ましいとされています。
目安としては5℃〜10℃程度なので、気温が下がりそうな時期には暖かい場所へ移動させるのがよいです。また、冬の間はじっと休眠期間を過ごしていた植物が春になって芽吹く姿は、たいへん感慨深いものがあります。
ただし、近年の日本の夏は世界的に見ても酷暑です。植物もあまりに熱い環境では夏バテしてしまうので、30℃を上回る環境では半休眠することがあります。
人が過ごしやすい気温は植物にとっても過ごしやすい気温です。できれば15〜28℃の温度を保って成育させてください。
関連記事:観葉植物の温度|適温や調節方法について
剪定|生育期直前を目安に行う

特に年をまたいで植物を育てる人にとって大切な作業が剪定です。
育ってきた枝を切ってしまうのは取り返しのつかない作業なだけに、少し気が重く感じる方もいるかもしれません。
剪定は、風通しをよくするとともに、樹形を整える役目にもなっています。植物は最も光に近い部分を伸ばす性質があるため、剪定をしないと枝が長く伸びていき、不揃いになりやすいです。
不要な枝を剪定すると、他の枝に栄養を届けられるので、植物全体を活気付けることができますよ。ぐんぐん伸びる生育期前に行なっておくとよいです。
また、ほぼ全ての葉を切り落とし「ボウズ」の状態を作る「強剪定」という剪定方法もあります。こちらは、株が完全に弱ってしまった時や冬越し前に体力を溜めるために行うものです。
AND PLANTSでは、軽くて切れ味のよい剪定バサミを用意しています。剪定をする際は、ぜひ植物専用のハサミを使ってください。
[https://andplants.jp/products/sakagen-flower-shears]植え替え|1〜2年に1回は鉢を植え替える

植物は購入してからも定期的に植え替えが必要です。葉や茎が成長するように、根も伸びていきます。植え替えをしないと鉢の内部で根が詰まっていき、適切に呼吸できない可能性があるのです。生育に障害が発生することも。
植え替えをする際は、現状の鉢より1号大きい鉢へ移すのをおすすめします。それ以上大きい鉢に植え替えを行うと、根が吸収できる量より多い水を含むことになり、根腐れを引き起こす危険があります。
植え替え自体は慣れてしまえば30分ほどで済むので、必要時にサクッと行なってしまうのが後々のためにもいいでしょう。
観葉植物の育て方に起因する主なトラブルと対処法
 上記のお世話で植物は育ちますが、成長に伴いトラブルもつきものです。代表的なトラブルとその対処法を次にまとめました。
上記のお世話で植物は育ちますが、成長に伴いトラブルもつきものです。代表的なトラブルとその対処法を次にまとめました。
- 根腐れ|水やりを控える
- 根詰まり|植え替えをする
- 葉焼け|直射日光を避ける
- 害虫|市販の薬を使用する
上記4つの対処法が分かっていれば、もう植物を育てるのに心配はありません。では、さっそく見ていきましょう。
根腐れ|水やりを控える
根腐れは、水を与えすぎてしまい根が酸素を吸えず、腐る状態のことをいいます。
土が湿った状態かつ葉が黄色く変色していたら、根腐れを疑ってみるといいかも知れません。さらに進行すると腐敗臭がして、茎がプニプニと柔らかくなり、手遅れになることも。
対処法はまず水やりを控えるのがよいです。それでも改善しない場合は、植え替えを行います。植え替えの際には、土をある程度まで綺麗に洗い流し、腐っている根は切るのが得策です。
植え替えが完了したら、しばらく風通しの良い場所に置いてください。数日経ち、土が乾いていたら、普段通り水やりをして問題ありません。
また、根腐れと気づかず安易に肥料を与えると、かえって悪化する恐れがあります。状態に異変を感じたらお水やりや肥料などは一旦、ストップするのが無難です。
根詰まり|植え替えをする
根詰まりは鉢の中いっぱいに根が伸びて、隙間がなくなってしまった状態のことです。そのままにしておくと株が弱り、酸素を吸う隙間がないので根腐れを起こす可能性があります。
鉢の底から根が飛び出していたり、土が乾くスピードが早く保水できなかったりする場合は、根詰まりの可能性を考えてみてください。
土は適度な隙間があると水分や栄養を保ちますが、根詰まりを起こしているときは隙間がないため保水ができないのです。
根詰まりが起こった場合は、一回り大きなサイズの鉢に植え替えましょう。
サイズを大きくしたくない場合は、鉢から取り出し根を半分ほどカットして元の鉢に植え替えるのがよいです。その際は、枝も剪定してバランスを整えておくのをおすすめします。
葉焼け|直射日光を避ける
葉が白もしくは黄色く変色し、元気がなくなっていたら葉焼けを起こしているかもしれません。日光の当てすぎにより、植物がヤケドをした状態になっています。状態が悪化すると、葉が茶や黒に変色し落葉する可能性も。
日光の当てすぎや、高温であることが原因です。長いあいだ日陰などの暗い場所で過ごしていた植物を、突然日当たりの良い場所に移した時にも葉焼けが起きます。
移動させる際は、徐々に明るい場所に移すのが得策です。加えて、日光と窓の間にレースカーテンを1枚挟むと葉焼けになる可能性が下がります。
残念ながら、葉焼けした葉を元通りに回復することはほぼ不可能です。
変色した葉は「日の当たり過ぎを教えてくれた」と思うようにして、生育の糧にするのがいいでしょう。
害虫|市販の薬を使用する
屋外で植物を育てている方は、ハダニやカイガラムシなどの虫に悩まされた経験もあるのではないでしょうか。害虫の多くは植物の栄養を吸って弱らせますが、虫の種類によっては病気を運び、トラブルを引き起こします。
害虫が発生した際は、市販の薬・殺虫剤などを使用するのが効果的です。即効性もあるため、被害を最小限にできます。 対処を行った後は、再発を防ぐために防虫剤を散布するのがよいです。日常から行える予防であれば、葉水を行うのもいいかもしれません。害虫は水分を弱点とする種類が多いからです。
「大事に育てている植物に薬を撒くのはなんだか抵抗がある」といった方もいらっしゃるかもしれませんが、虫は1匹見逃すと繁殖してすぐに増えるため、植物の為にも早めに対処してあげてください。
[https://andplants.jp/products/evo_anti_insect_spray]害虫対策に「虫を寄せ付けない水(防虫スプレー)」を使った方からのレビュー
「虫を寄せ付けない水(防虫スプレー)」を使用した方からのレビューを以下にまとめましたので、購入を検討している方は参考にしてみてください。



自然由来の成分のみで作られているため、ペットやお子さんがいるご家庭にも安心して使えるのがいいですね。スタイリッシュなデザインなので、お部屋のインテリアとも馴染みやすいでしょう。
[https://andplants.jp/products/evo_anti_insect_spray]トラブル別の対処法一覧
 観葉植物のトラブルと代表的な対処法を表にまとめました。
観葉植物のトラブルと代表的な対処法を表にまとめました。
| 葉のトラブル | 代表的な対処法 |
| パリパリ | 水やりの頻度改善 |
| 変色(黒) | 水やりの頻度改善 |
| 変色(白) | 直射日光を当てない |
| 変色(黄色) | 肥料を与える |
| 傷 | 虫害は補殺・殺虫剤を散布する |
| 垂れ | 暖かい場所に移動させる |
| 葉焼け | 直射日光を当てない |
| 虫のトラブル | 代表的な対処法 |
| ハダニ | 殺虫剤を散布する |
| カイガラムシ | 殺虫剤を散布する |
| アブラムシ | 殺虫剤を散布する |
| コナジラミ | 牛乳を吹きかける |
| コバエ | 鉢ごと水に浸す |
| トビムシ | 風通しをよくする |
| 病気のトラブル | 代表的な対処法 |
| うどんこ病 | 酢や重曹を薄めて散布する |
| すす病 | ティッシュや歯ブラシで除去する |
| 炭そ病 | 病変した葉を切り取る |
| 灰色カビ病 | 病変した葉を切り取る |
| 斑点病 | 病変した葉を切り取る |
各トラブルの対処法は、以下の記事で詳しく解説しています。
観葉植物の育て方に関するよくある質問
 最後に観葉植物の育て方を調べる方からのよくある質問とその答えをまとめました。
最後に観葉植物の育て方を調べる方からのよくある質問とその答えをまとめました。
- 冬場の管理で気をつけておくことは?
- 日光が入らない場所でも育てられるの?
- 観葉植物の土はどんなものを選んだらいい?
- 肥料と活力剤の違いは?
順にそれぞれ見ていきましょう。
冬場の管理で気をつけておくことは?
冬場は、植物が温度変化に耐えられるようにサポートしてあげる管理が必要です。
寒さに強い冬越しが可能な植物であれば安心ですが、暖かい地域で育ったものは特に注意しなければいけません。屋外で育てている場合は植物を部屋の中に入れて、冷気が漂う窓際から距離を置くのが大切です。
トラブル別の対処法一覧また冬場は、観葉植物の多くは「休眠期」に入ります。休眠期の植物は、成長が遅くなり、樹液を濃くして寒さから身を守ろうとするそうです。
「休眠期」にお水やりをたっぷりしてしまうと、樹液が薄くなって寒さをしのぐことができません。加えて、ゆっくりとしか水を吸えないため根腐れの可能性も高まります。そのため、冬場のお水やりは、量・頻度に気をつけて行いましょう。
日光が入らない場所でも育てられるの?
日光の入りづらい場所でも元気に育つ耐陰性といった性質を備えている観葉植物があります。たとえば、パキラやモンステラは「耐陰性」の高い植物です。
ある程度、日が当たらなくても育てられますが、可能であれば定期的に当ててあげると元気に育ちます。
とはいえ、お家の間取りの都合などで日当たりが悪い場合もあるでしょう。その場合は、植物育成用のLEDライトを使用するのがおすすめです。
成長に必要な太陽の赤色と青色の光が強く放つように設計されています。
日光が入らなくても、植物がもつ性質や道具を活用すれば、うまく育てることができるでしょう。
観葉植物の土はどんなものを選んだらいい?
元気に育ってくれるように元肥入りとなっている肥料を選ぶとよいです。肥料がすでに入っているため、そのまま使用できます。特に観葉植物を育てるのに慣れていない方にはよいかもしれません。
「虫が発生するのは困る」と考えていたら、ハイドロボールもおすすめです。高温で作られた土なので、虫・臭いも発生しません。繰り返し洗って使用できるため、とてもエコです。
植物をクリーンに育てたいなら、ぜひハイドロボールも検討してみてください。
肥料と活力剤の違いは?
肥料と活力剤の違いは肥料成分の強さです。肥料は観葉植物にしっかりと栄養を届けますが、活力剤は補佐的な役割として働きます。
活力剤は成分が強くないので、植物の状態にかかわらず使用できる点がメリットです。ただし、「株に栄養を与えたい」「葉色をキレイにしたい」といった場合は、肥料を与えた方がよいでしょう。
肥料は成分が強いため、観葉植物が弱っていたり冬で生育が緩慢になっていたりするときに与えると根が傷みます。また、植え替えの時に根を傷めた場合も注意が必要です。
肥料は生育期の元気な観葉植物に与えることを押さえておくと、安心して育てられます。
まとめ
観葉植物の育て方の基本をまとめました。ここまで紹介したお手入れをすれば、きっと元気に育てることができるはずです。
最初のうちは「どうするべきなのか」と迷うかもしれません。
しかし、毎日植物のお世話をしていると、次第に「今は水はいらないんだな」「ちょっと日当たりを変えて欲しいのかも」などが分かるようになってきます。
専門的なことが分からなくても、親が自転車の乗り方を子どもに教えるように、手を差し伸べたり後ろを押したり、大切に成長を見守る気持ちがあれば元気に育つでしょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
[https://andplants.jp/collections/caregoods]